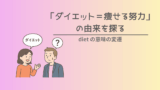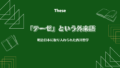私たちが何気なく使う「かわいい」という言葉。
今ではアニメやファッションを通じて “Kawaii” として世界にも広まりました。
けれども、もともとの「かわいい」は「気の毒」「いたわしい」といった意味から生まれた言葉です。
時代を超えて変化してきたこの言葉の歴史をたどると、日本人の“情のあり方”が見えてきます。
現代の「かわいい」とは
現代の日本では「かわいい」は、もはや単なる形容詞ではなく、一つの文化や価値観を表す言葉になっています。
現代の「かわいい」の辞書的な意味
「かわいい」という言葉を国語辞典で調べると、「小さくて愛らしい」「親しみを感じさせる」といった意味で説明されています。人や動物、キャラクター、さらには雑貨や食べ物まで、あらゆるものに対して使われる万能語です。
「かわいい」は、外見の美しさというよりも、「見た人の心を柔らかくする存在」に向けられた言葉といえるでしょう。
英語の “Kawaii” の使われ方
この「かわいい」という日本語はそのまま “Kawaii” として海外にも広まりました。
ファッション・アニメ・ポップカルチャーを象徴する言葉となり、英語の “cute” よりも幅広い意味を持つようになっています。
特に海外では、「奇抜」「個性的」「不思議な魅力」というニュアンスで使われることもあり、文化としての「Kawaii」は世界共通語になりつつあります。
「かわいい」という言葉の変遷
今でこそ肯定的で明るいイメージを持つ「かわいい」ですが、その原点はまったく異なる感情にありました。
古語「かはゆし」 ― 哀れみの感情
古代日本語の「かはゆし(可愛し/かはゆい)」は、上代から用例があり、
もともとは「かほ(顔)」+「ゆし(〜し)」という構成で、
語源的には「顔をそむけたいほど気の毒・見ていられない」という意味が根底にあります。
『源氏物語』では、幼い子どもや弱い立場の人に向けて「かはゆし」と表現される場面が多く見られます。
「いといたう泣きたまふさま、いとかはゆし。」
(あまりに悲しげに泣く様子が、見ていて胸が痛むほどいじらしい)
― 源氏物語

つまり、「かわいい」とはもともと同情や慈しみの感情を表す言葉だったのです。
ただし、平安文学の中でも、恋愛対象に「かはゆし」が用いられている例もあり、「愛おしさ」と「いたわしさ」が共存していたと考えられています。
中世「かはゆらし」 ― 守りたい美
中世に入ると、「かはゆし」から派生した形として「かはゆらし(可愛らし)」が登場します。
それまでは子どもや弱者は「保護対象」であり、同情の対象でしたが、鎌倉期以降、「幼さ」「あどけなさ」そのものを“美しいもの”として見る感性が生まれました。
「かはゆらし」は、まさにその感性の転換を反映する語であり、これが後の「かわいい文化(小さく、儚く、守りたい美)」の礎となります。
この「〜らし」は、感情をやわらげたり、「〜のようである」といった推定や親しみを込める接尾辞です。「かはゆらし」は、元々の“いたわしい” という重さが薄れ、より軽い愛情・親しみを表す語として使われるようになります。

例えば、『徒然草』(14世紀頃)にはこのような例があります。
「幼き子の、うたた寝するさまの、いとかはゆらしきこと」
(幼い子がうたた寝する様子の、なんと愛らしいことか)
― 徒然草
ここでは、すでに「かわいらしい」「愛くるしい」という現代語的なニュアンスが生まれています。
かわいそう ― 「哀れみ」の表現の分岐
中世以降、「かはゆし」や「かはいい(かわいい)」という形容詞が定着していく中で、その「哀れみ」「同情」の側面を強調した言い方が生まれました。
それが「かわいそう」です。
「〜そう」は、本来「〜のように見える」「〜の様子だ」という意味の接尾辞で、
「かわいそう」は直訳すれば“かわいく(いたわしく)見える”という構成になります。
| 系統 | 形態 | 感情の方向 | 現代語 |
|---|---|---|---|
| A | かはゆらし → かわいらし | 愛情・親しみ・保護したい | かわいい |
| B | かはゆし → かわいし → かわいそう | 哀れみ・同情・憐れ | かわいそう |
つまり、
- 「かわいい」= 同情+愛情 → プラス方向の感情
- 「かわいそう」= 同情+哀れみ → マイナス方向の感情
というように、共通の根(いたわしさ)から枝分かれした語なのです。
江戸期 ― 「かわいらしい」の定着
江戸時代の庶民文化では、子どもや動物、精巧な小物などへの親しみを示す言葉として「かわいらしい」が定着しました。

※ 根付とは、帯に提げた小物を留めるための留め具で、職人の技と遊び心が凝縮された小さな彫刻です。
職人たちの作る小さな玩具や人形、浮世絵に描かれる子どもや猫の姿などにも、この「かわいさ」が色濃く表れています。
明治~昭和 ― 西洋語「キュート」との融合
明治以降、「かわいい」は英語の “cute” に近い意味として使われ始めました。
少女雑誌(『少女の友』など)や広告では「可愛い服」「可愛い顔立ち」といった表現が増え、「愛らしさ」はより外見的・装飾的な方向へと拡張されていきます。
.png)
昭和中期には、リカちゃん人形や漫画などを通じて、少女文化の中心的なキーワードとなり、“かわいい”の大衆定着に大きく影響しました。
関連記事:「ダイエット」の変遷と正しい用法 ー 明治から昭和に定着した外来語
元々は医学用語として使われていたダイエットという外来語は、明治から昭和期に意味を変えて広まりました。以下の記事では、言葉の変遷と共に正しい英語の意味を紹介しています。
現代 ― 「萌え」や「尊い」へと拡張
21世紀に入ると、「かわいい」は外見だけでなく、存在そのものへの愛情や癒しの感情をも含むようになります。
.png)
アニメやゲームのキャラクターに「かわいい」と言うとき、そこには「大切にしたい」「尊い」といった想いが込められています。
つまり現代の「かわいい」は、美的評価から感情的共感へと進化した言葉といえるでしょう。
「かわいい」の形態変化まとめ
日本語音韻史では、平安末期から鎌倉期にかけて、「は行音」が次第に「わ行音」に変化しました。これにより、「かはゆらし」は「かわゆらし」と発音されるようになります。
さらに中世後期〜近世にかけては、母音の融合や省略によって「かわゆい」「かわいい」などの形が並立し、最終的に「かわいい」が標準的形として定着しました。
| 時代 | 形態 | 意味的特徴 |
|---|---|---|
| 上代 | かはゆし | 気の毒・見ていられない(哀れ) |
| 中世 | かはゆらし | いとおしい・愛らしい(情的) |
| 近世 | かわゆい/かわいい | 愛らしい・小さい・可憐(親愛) |
| 現代 | かわいい | 愛らしい・個性的・萌え(多義化) |
日本人として日本語を知る
「Kawaii」という言葉は、いまや世界中で使われるようになりました。日本の文化や言語が広く知られることは、私たちにとって誇らしいことです。
しかし一方で、「日本の“かわいい”とは本来どういう意味なのか」と尋ねられたとき、うまく答えられない自分に気づくこともあります。
正しい言葉の背景を知ることは、単に知識を増やすだけでなく、日本人としてのアイデンティティを育むことにもつながるのです。
最近では「可哀想は可愛い」という言葉を耳にすることがあります。
実際、これらはもともと同じ言葉から派生した兄弟のような存在です。意味は違っていても、その根底には「弱きものを愛しむ心」という共通の感情があり、それは現代の私たちの中にも息づいているのです。
身近な言葉にも歴史があるものです。
何気なく使っている日常の言葉にも、少しだけ興味を向けてみると、新しい発見があるかもしれません。
関連記事:もののあはれとは ― 日本人固有の美的理念
「かわいい」という言葉の背景には、日本人が古くから抱いてきた“情の細やかさ”があります。
その源流をたどると、平安時代の文学や、江戸時代の国学者・本居宣長が説いた「もののあはれ」の思想にもつながります。
宣長は、外来思想の儒教や仏教を「からごころ」として批判し、日本人固有の感受性「やまとごころ」を重んじました。
彼が語った「もののあはれ」とはどのような美意識だったのか。以下の記事で詳しく解説しています。