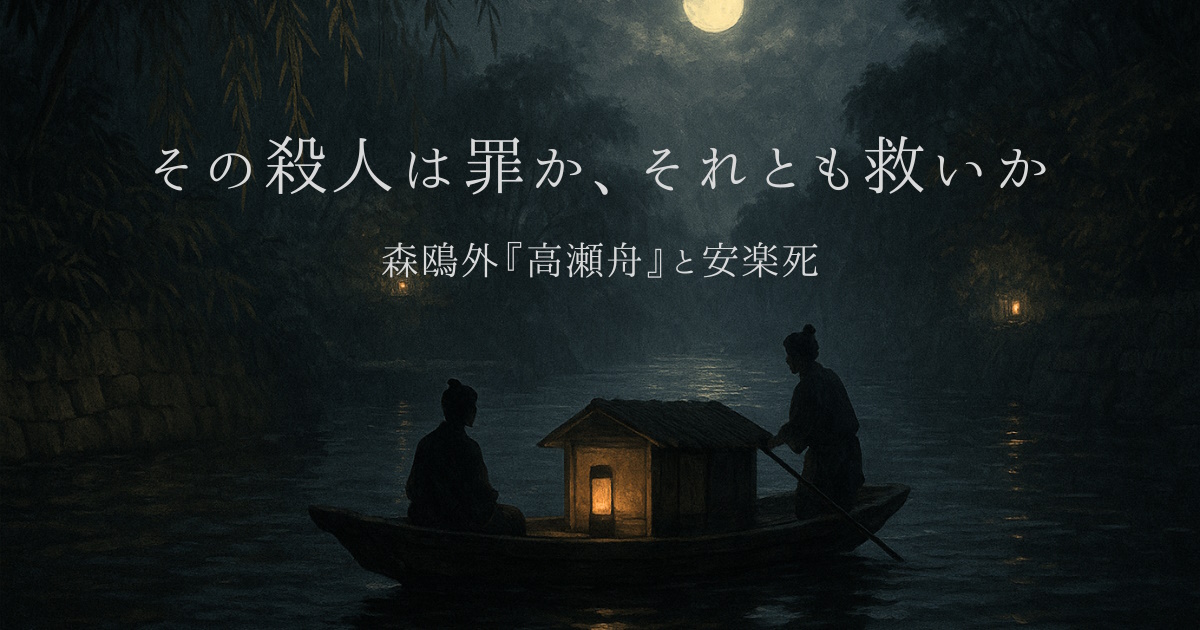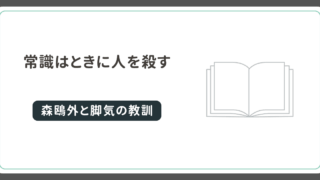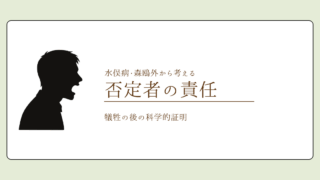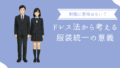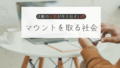その殺人は、罪なのか。それとも救いだったのか。 森鷗外『高瀬舟』は、答えのない問いを静かに突きつけます。
これは昔の話ではありません。 今を生きる私たちにも向けられた問いでもあるのです。
高瀬舟とはどんな物語か
江戸時代、罪人を京都から島流し先まで運ぶ小舟――それが「高瀬舟」です。
森鴎外の短編『高瀬舟』は、この舟の上で交わされる、わずかな時間の会話から始まります。
登場人物は二人だけ。罪人の喜助と、彼を護送する同心・庄兵衛。
大きな事件や劇的な展開があるわけではありませんが、その静かな物語の中には、人の命・苦しみ・罪と救いに関する深い問いが潜んでいます。
作品の背景とあらすじ
舞台は江戸後期の京都。
役目として罪人を舟で送り届ける庄兵衛は、ある男・喜助を乗せています。
喜助は「兄を殺した罪」で島流しとなった人物です。
しかしその様子は、普通の罪人とは少し違っていました。泣くことも怯えることもなく、むしろ晴れやかな顔で、穏やかに舟に揺られています。
興味を抱いた庄兵衛が事情を尋ねると、喜助は淡々と語り始めます。
貧しさと病に苦しむ兄を、見かねて手にかけたこと。
兄は「これで楽になれる」と安堵したこと。
自分は罪を犯したとは思っていないこと――。
その語り口には悔いも悲しみもありませんでした。
「殺した」というのに、なぜ安らかなのか
普通であれば、兄を殺すという行為は取り返しのつかない罪です。しかし喜助には、涙も恐れもない。舟の上で穏やかな風を感じながら、むしろ肩の荷を下ろしたような表情すら浮かべています。
このとき庄兵衛は、心の中で引っかかりを覚えます。本当にこの男は、人を殺した罪人なのか。
なぜ喜助は兄を殺めたのか
兄を手にかけたという事実だけを見れば、喜助は明らかに罪人です。
しかし、その行動には単なる殺意とは異なる背景がありました。
貧困と絶望の果てに
喜助の家は極度の貧困にあり、兄は長い病に伏せり、食べることすらままならない生活でした。
兄の状態については、作中では以下のように描かれています。
(要旨・要約を含みます)
- 兄は長く病床に伏している
「兄は久しく病臥していて、もう働くこともできなかった。」 - 極度の貧困と栄養失調
「銭は尽き、米はなく、わずかの粥をわけあって食うばかりであった。」
「薬も買えず、医者を呼ぶこともかなわず…」 - 精神的な疲弊(生きる気力の喪失)
「兄はもう起き上がる力もなく、ただ苦しげな息をしていた。」
「その顔には、死ぬよりも生きる方が辛いという色が見えた。」
そしてある夜、苦しむ兄のそばで、喜助は手を下します。殺意ではなく、苦しみから解放してやりたいという思いからでした。
作中では、兄が「死にたい」と直接語る場面はありません。
しかし、長い病と飢えに苦しみ、生きる力を失った姿が淡々と描かれています。
喜助はその姿を見て「兄を楽にしてやりたい」と思い、手をかけた――と語られます。
「殺したのに罪悪感がない」という異様さ
喜助はその行為を隠していたわけでも、悪いと思っていないわけでもありません。ただ、「兄が楽になった」という結果に、心から安堵しているのです。この態度に、庄兵衛は強い衝撃を受けます。
兄を殺したのに、悲壮感がない。 むしろ、心の重荷から解き放たれたように見える。
それこそが、彼の心に疑問を生みます。
その殺人は罪か、救いか
喜助の語った出来事は、単なる殺人ではありませんでした。
兄を想う気持ちと、命を奪ったという事実。
そのあいだで、庄兵衛の心は揺れ始めます。
法では罪だが ― 言葉にならない葛藤
武士であり役人である庄兵衛にとって、「人を殺した者が罪人である」というのは当然のことです。しかし喜助の話を聞くうちに、その「当然」が揺らぎ始めます。
- 法では殺人は罪
- でも、苦しむ人を楽にした行為も同時に否定していいのか
- 自分が同じ立場だったら、どうしていただろうか
庄兵衛の胸の中で、答えの出ない問いが大きくなっていきます。
人を救うことが、罪になるのか?
庄兵衛は喜助の話を聞きながら、心の奥底でこんな思いを抱きます。
「人を救おうとした行為が、罪になるのだろうか」と。
その問いは鴎外自身の声であるとも解釈されますが、鴎外は作品の中で決して結論を語りません。ただ、庄兵衛の揺れる心が淡々と描かれます。
作者「森鴎外」という人物
森鷗外は文豪として知られていますが、本業は医師でした。若くしてドイツに留学し、西洋医学を学び、日露戦争では日本陸軍の軍医総監――軍医の最高位に就きました。
軍医としての仕事柄、戦傷や病で苦しむ多くの兵士・患者と向き合ってきたはずです。中には、回復の見込みがなく苦しみ続ける者や、自ら死を望むような状況に追い込まれた者もいたかもしれません。
『高瀬舟』が鷗外自身の経験に直接結びついているかどうかは分かりません。
しかし、苦しむ命を前にして「救いとは何か」「生かすとは何か」を考えざるを得ない立場にあった人間であることは確かです。
そう考えると、作中の静かな葛藤は、鷗外自身の胸の内から生まれたものなのかもしれません。
関連記事:命より大事なものはあるのか
私たちは常識として「命が一番大事」と考えます。しかしそれは普遍の真理なのでしょうか。
以下の記事では、命よりも大事とされた殉教や忠義といった歴史の紹介や、現代のAED論争、裁判例などを紹介しています。興味のある方は是非こちらもご覧ください。
現代の「安楽死・尊厳死」とどうつながるのか
高瀬舟の物語は江戸時代を舞台にしていますが、語られる葛藤は決して昔の話ではありません。
私たちが生きる現代にも、同じ問いが姿を変えて存在しています。
苦しみからの解放は、罪か救いか
21世紀の日本では、高齢化・医療技術の進歩とともに、「延命治療」「尊厳死」「安楽死」といった言葉が日常的に語られるようになりました。延命が可能になった分、「どこまで生かすべきか」「苦しむ人の願いをどう扱うのか」という新たな葛藤も生まれています。
喜助の行為と、現代の安楽死・尊厳死の議論は、根底では同じ問いに触れています。
「命を延ばすこと」と「苦しみから救うこと」、どちらが本当の“慈しみ”なのか。
安楽死と尊厳死の違い
『高瀬舟』の喜助の行為は、現代の言葉でいえば「安楽死」に近いものです。
ただし、似た概念として「尊厳死」があり、両者は明確に区別されています。
| 用語 | 行為の性質 | 死への関与 | 日本での扱い |
|---|---|---|---|
| 安楽死 | 積極的に死を与える | 医師などが 意図的に命を終わらせる | 原則として違法 (殺人・自殺幇助) |
| 尊厳死 | 延命治療を行わない | 自然死を受け入れる | 条件付きで容認されるケースあり |
世界と日本の考え方の違い
- オランダ・ベルギー:条件付きで安楽死が合法
- スイス:自殺幇助が容認される
- 日本:安楽死は違法。ただし尊厳死(延命治療をやめる)は議論され始めている
どの国にも共通するのは、「苦しみから解放することは正しいのか」という迷いがあること。誰も完全な答えを出せていないという点です。
答えを探し続ける社会
庄兵衛は、最後まで自分の中に答えを見つけることができませんでした。鴎外もまた、明確な結論を語ることはしません。そして、それはこの記事でも同じです。
苦しむ人の命を、どう扱うべきなのでしょうか。
救いのための行為は、罪と呼ばれるべきなのでしょうか。
この問いに、いまのところ正解はありません。
しかし、私たちは問い続けることをやめてはならないのだと思います。
もし自分が苦しむ立場になったら、何を望むでしょうか。
もしあなたが喜助と同じ立場に立たされたなら、あなたはどうしますか。
関連記事:森鷗外という人物をもっと知る
森鷗外は文豪として知られていますが、同時に医師・軍医として人の命と向き合い続けた人物でもあります。
ペスト防疫、脚気対策、衛生行政――その歩みは、ただの文学者という枠には収まりません。
以下の記事では、鷗外の医師としての活動や、歴史的な判断から見える「現代への教訓」を紹介しています。「高瀬舟」で描かれる“命と苦しみの問い”は、彼の生涯全体にも通じるテーマなのかもしれません。
ビタミンの発見や公衆衛生の進展など、現代医療の根本にも、鷗外の選択と葛藤が影を落としています。興味のある方は、ぜひこちらもお読みください。