日本の歴史に関係している記事全般です。主に日本が中心となっている出来事をまとめたものを対象としていますが、一部日本に関係した事に言及した記事も対象となることがあります。
 思想
思想 日本人にとっての赤色 ― なぜ縁起のいい色とされてきたのか
赤はなぜ縁起のいい色とされてきたのでしょうか。鳥居や紅白、赤子といった身近な例から、日本人が赤色に抱いてきた感覚を、神道的な背景や文化の視点から整理します。
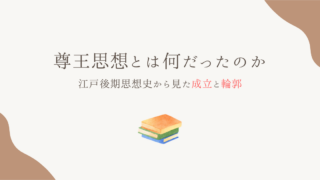 思想
思想 尊王思想とは何だったのか ― 江戸後期思想史から見た成立と輪郭
尊王思想は、感情的な熱狂や偶然から生まれたものではありません。本記事では、垂加神道・水戸学・国学といった江戸時代の学問的探究を手がかりに、尊王思想がどのように成立し、思想化していったのかを構造的に整理します。
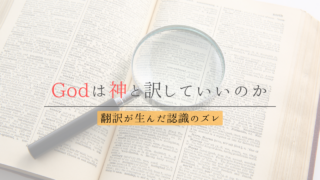 言語
言語 Godは神と訳していいのか ― 翻訳が生んだ認識のズレ
Godはなぜ日本語で「神」と訳されたのか。その翻訳の背景と、英語と日本語における「神」の捉え方の違いから、言葉が生んだ認識のズレを整理します。
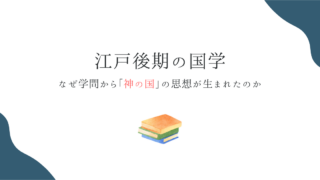 思想
思想 江戸後期の国学 ― なぜ学問から「神の国」の思想が生まれたのか
江戸後期の国学は、なぜ「神国日本」という思想に至ったのか。江戸中期国学の方法論、平田篤胤の思想と時代背景を手がかりに、学問が思想へと変化した過程を整理します。
 思想
思想 江戸中期の国学 ― 全てを理屈で説明できるのか
国学というと尊王思想や愛国主義を連想しがちですが、その始まりは人の心の動きを見つめ直す学びでした。江戸中期の国学を、契沖・賀茂真淵・本居宣長の思想の流れから読み解きます。
 思想
思想 江戸中期の陽明学 ― なぜ社会は良くならないのか
江戸時代、朱子学が広がる社会の中で「なぜ正しさが行き届かないのか」という違和感が生まれました。本記事では、江戸中期に陽明学がどのように受容され、社会や思想の中でどのような意味を持ったのかを読み解きます。
 言語
言語 意外と新しい「宗教」という言葉・概念 ― religionの翻訳史
宗教という言葉は、実は近代日本で西洋の religion を翻訳する中で再定義された概念でした。語の歴史から、日本人の宗教観と現代的な違和感を考えます。
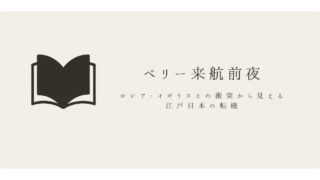 歴史
歴史 ペリー来航前夜 ― ロシア・イギリスとの衝突から見える江戸日本の転機
ペリー来航以前、日本はすでにロシアやイギリスと接触し、外圧を経験していました。衝突の歴史とその影響を通して、江戸後期日本が迎えつつあった転機を整理します。
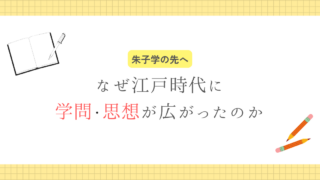 思想
思想 なぜ江戸時代に学問・思想が広がったのか ― 朱子学の先へ
江戸時代には、朱子学を基盤としながらも多様な学問・思想が広がっていきました。朱子学の成功とその限界、識字率や出版文化の発達から、その背景を読み解きます。
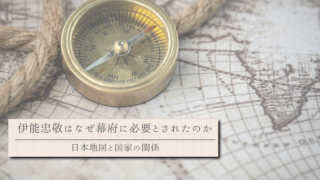 歴史
歴史 なぜ伊能忠敬は必要とされたのか ― 個人の探究が社会を動かすとき
伊能忠敬は、なぜ幕府に必要とされたのでしょうか。私的な学問として始まった測量が、国家事業へと転化し、日本列島の見え方を変えた背景を解説します。