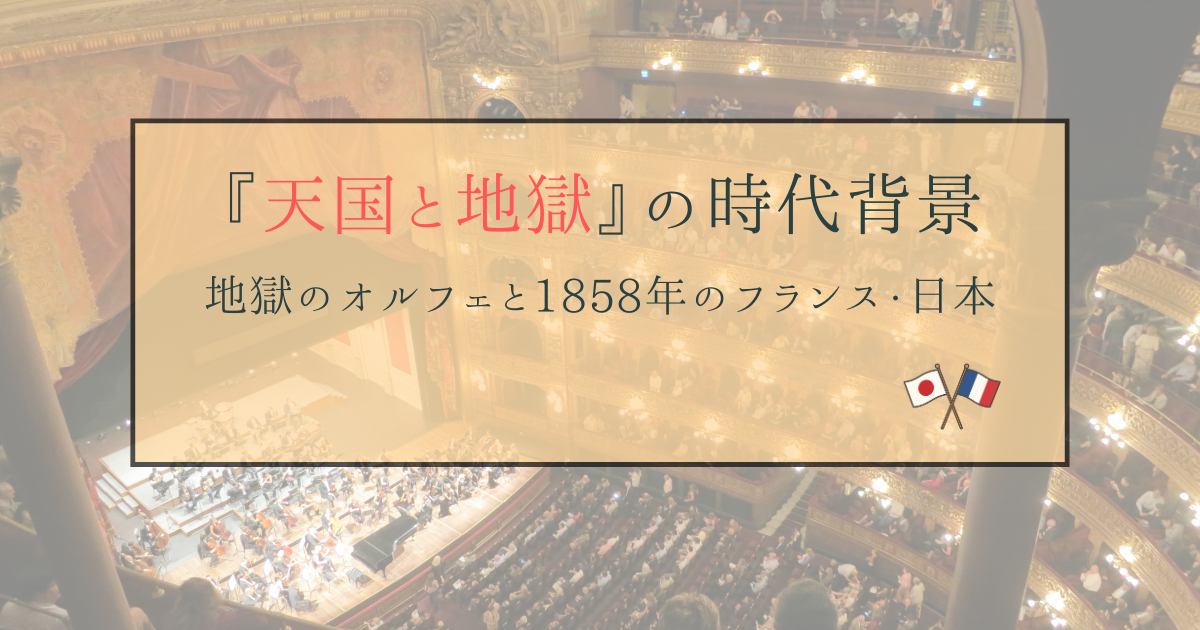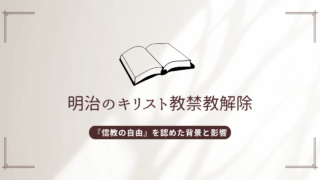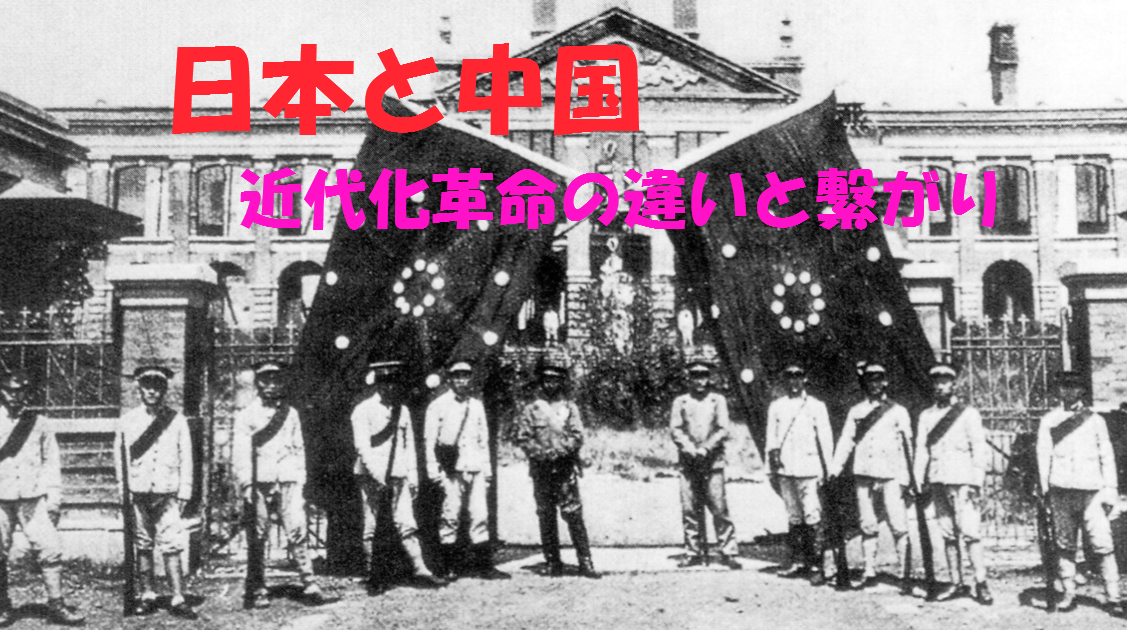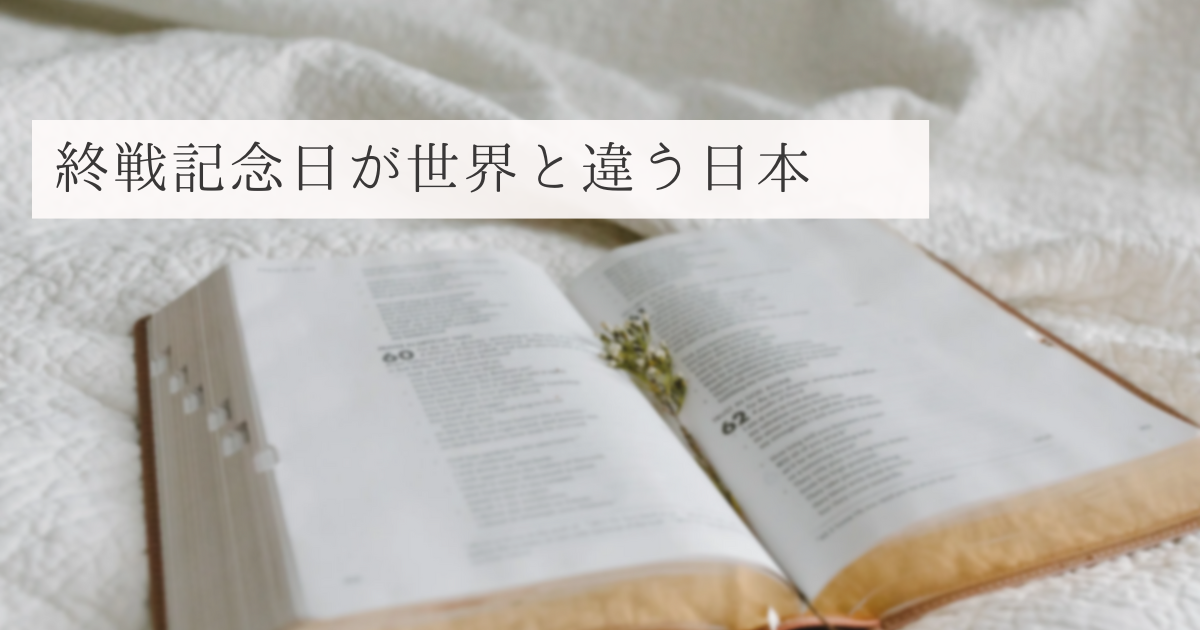1858年、パリでは人々を笑いに包むオペレッタ『地獄のオルフェ』が上演され、
同じころ日本では、国の未来を左右する条約交渉が進んでいました。
華やぎと緊張――対照的な空気の中で生まれた一つの音楽は、やがて海を越え、日本でも愛される存在となります。
本記事では、この作品を軸に、フランスと日本それぞれの「1858年」を見つめ直します。
『天国と地獄』と『地獄のオルフェ』の関係 ― 作品の基礎知識
日本では運動会やテレビ番組などで耳にする軽快な曲が「天国と地獄」として知られていますが、これはもともと、フランスの作曲家ジャック・オッフェンバックが1858年に発表したオペレッタ『地獄のオルフェ(Orphée aux Enfers)』の一部です。
作品全体の正式名称と、日本で広く知られる部分曲の名称が異なるため、まずは両者の関係を整理しておきます。
1858年初演版と1874年改訂版 ― 二つの「地獄のオルフェ」
最初の『地獄のオルフェ』は1858年にパリで初演された、全2幕の比較的コンパクトなオペレッタでした。
のちに1874年に大規模改訂が行われ、全4幕の作品として再構成されます。
この改訂版では、初演時には存在しなかった新曲が複数追加され、その中に、現在「天国と地獄(カンカン)」として知られる軽快なギャロップも含まれています。
現代でよく演奏される「天国と地獄」は、この改訂版で初めて登場した楽曲であり、元の1858年初演版には存在しません。
日本だけで定着した「天国と地獄」という呼び名
日本では、この部分曲が「天国と地獄」という独自の名称で広まり、作品全体の名前として扱われることさえあります。
しかし世界ではこの呼称は一般的ではなく、作品は正式名称である Orphée aux Enfers(オルフェ・オ・ザンフェール)として知られています。
英語圏では、主に次のような名称が用いられています。
- “Orpheus in the Underworld”(作品名)
- “The Can-Can”(部分曲の俗称)
- “Galop Infernal”(楽譜タイトル)
“ Heaven and Hell ” のような直訳名が楽曲タイトルとして定着しているわけではありません。
日本で別の名称が広まった背景
日本で「天国と地獄」が一般名称として浸透したのは、明治期以降の音楽教育が大きく影響しています。
軽快でわかりやすい旋律が学校教材として採用され、行進曲や運動会のBGMとして頻繁に演奏されるようになりました。やがて部分曲が独り歩きし、作品名とは別に“曲名としての天国と地獄”が広く認知されていきます。
現在では、部分曲の呼び名が作品名であるかのように理解されることも珍しくありません。
こうした状況は世界的にもあまり例がなく、「天国と地獄」という名称が広く使われるのは日本特有の受容のあり方といえます。
本記事では、1858年に初演された『地獄のオルフェ』を軸に、その当時のフランス社会と日本の幕末期を比較していきます。
ナポレオン3世の時代 ― フランスが抱えていた不安と期待
『地獄のオルフェ』の背景を理解するには、ナポレオン3世の第二帝政期を知ることが欠かせません。
この時代は、安定を求める社会と、変革を望む社会が入り混じる複雑な時期でした。
『地獄のオルフェ』初公演時のフランス ― 革命とクーデターで不安定な時代
19世紀のフランスは、1789年の大革命で王政を一度は終わらせましたが、その後は王政復古と共和政が入り混じる不安定な時代が続きました。
| 年代 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1789–1799 | フランス革命 → ナポレオン時代 | 絶対王政が終わり、近代国家の基盤が形成される。(第一共和政) |
| 1815–1848 | 王政復古期(ブルボン王朝の復活) | 革命後の揺り戻しで王政が再び成立し、政治は不安定なまま推移。 |
| 1848–1852 | 1848年革命(第二共和政) | ヨーロッパ同時革命の年。フランスでは市民革命が再発し、共和政が樹立。 |
| 1852–1870 | 第二帝政(皇帝=ナポレオン3世) | ルイ=ナポレオンがクーデター後に皇帝へ。共和政が終わり帝政が復活。 |
1848年には再び革命が起こり、第二共和政が成立します。この共和政の大統領に選ばれたのが、ナポレオン1世の甥にあたるルイ=ナポレオン(後のナポレオン3世)でした。
1851年にナポレオン3世がクーデターによって議会を制圧し、第二共和政は崩壊します。
翌1852年には皇帝に即位し、フランスは再び帝政へと移行します。
第二帝政は、経済発展やパリ大改造などの近代化を推し進める一方、言論統制や政治的抑圧も強まり、市民の間には期待と不安が入り混じっていました。
こうした緊張と活気の入り混じる社会状況の中で、1858年に『地獄のオルフェ』の初公演が行われます。
風刺と笑いを武器にしたこの作品は、当時の空気を映し出す象徴的な存在でもありました。
パリ改造と近代都市の誕生
この時期、オスマン知事が主導したパリ大改造が始まり、道路の拡幅、上下水道整備、公園建設など都市インフラが刷新されます。
華やかなパリの景観は確かに第二帝政の産物ですが、その裏では都市問題や格差の問題も存在し、光と影を併せ持つ都市でした。
ヨーロッパ全体に広がった不安定さ
ヨーロッパは外交的にも不安定でした。クリミア戦争後の国際秩序、イタリア統一運動など、国民国家形成をめぐる激動が続いていました。
第二帝政期が生んだ文化の多様性
政治的には揺れていた時期とはいえ、美術、演劇、そして音楽では革新が続きました。
万国博覧会の開催など、国際文化交流が盛んになったのもこの時代です。
こうした文化の土壌が、オッフェンバックの風刺的な作品を受け入れるパリを形づくります。
同じ1850年代、日本は幕末の渦中にあった
同じ1858年、日本は幕末の真っただ中にありました。
フランスほどの都市文化はありませんでしたが、日本もまた政治・社会の大転換期を迎えていました。
『地獄のオルフェ』初公演時の日本 ― 開国と条約交渉が迫った1858年
フランスで『地獄のオルフェ』の初公演が行われた1858年、日本では日米修好通商条約の締結を皮切りに、諸外国との交渉が次々に進み、開国への道が大きく開かれていきました。
これに伴い、国内では尊王攘夷思想が高まり、幕府の求心力が揺らぎ始めます。
| 年代 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1853–1854 | ペリー来航と開国要求 | 鎖国体制が動揺し、日米和親条約の締結へ。 幕府は外交方針の転換を迫られる。 |
| 1858–1860 | 安政五カ国条約と通商開始 | 日米修好通商条約をはじめとする諸外国との条約締結。 開国が本格化し、国内に大きな動揺が広がる。 |
| 1860–1867 | 尊王攘夷と政治混乱の時代 | 公武合体・攘夷運動・長州征討など、政治抗争が激化。 幕府の求心力が低下していく。 |
| 1867–1868 | 大政奉還と明治維新 | 江戸幕府の終焉。王政復古によって近代日本への道が開かれる。 |
政治的不安定さは欧州と同様であり、日本もまた大きな変化の波に呑まれていました。
文化流入はまだ始まりの段階だった
幕末期には、写真技術や軍楽隊など、西洋文化のいくつかは徐々に日本へ入り始めていましたが、一般に広まるのは明治期に移ってからでした。
音楽文化に限れば、『地獄のオルフェ』のような作品が知られるようになるのは、教育制度の整備が進んだ後のことです。
日本でオペレッタ全曲が本格的に上演されたのは、大正3年(1914年)に帝国劇場で『天国と地獄』として上演されたのが初めてとされています。その後この邦題が広く定着しました。
一方、明治期には「天国と地獄(カンカン)」の旋律だけが先に広まり、軍楽や教育曲として親しまれていきました。
幕末に日本で初めて聞かれた「西洋の音」
軍楽隊のラッパ、行進曲などは、比較的早い段階で日本に伝わりました。
後に西洋音楽が教育として組み込まれる際、この“最初期の音”が基盤となっていきます。
幕末から明治初期にかけて、日本はフランスを近代的国家のモデルとして軍制など多くを学びます。その過程で日本に定着した服飾用語は、現代でも外来語として使われています。
💡関連記事:ズボンやボタンはフランス語? 語源でたどる明治日本の西洋化
宗教・思想の揺れが社会に影響を与えていた
幕末は宗教的にも揺れた時期でした。
キリスト教への対応や、外交をめぐる思想対立が錯綜し、日本社会は価値観の再編を迫られます。
文化としての西洋音楽受容が遅れた背景には、こうした社会状況も影響していました。
明治に入ると、幕末から続いていた潜伏キリシタンへの処罰が外交上の大きな障害となっていきます。
欧米の新聞では日本の政策を批判する論調が広まり、フランスを含む4カ国から正式な抗議文が提出されました。これにより日本は、長く続いてきたキリスト教禁止政策の見直しを迫られることになります。
💡関連記事:明治のキリスト教禁教解除 ― 『信教の自由』を認めた背景と影響
音楽が伝える「時代の空気」 ― フランスと日本の比較から見えるもの
同じ1858年でも、フランスと日本では置かれていた状況が異なっていました。
しかし、どちらも「変革の前夜」であったという点では共通しています。
揺れ動く社会で娯楽が求められたフランス
政治的緊張が続く中、人々は娯楽文化に活路を求めました。
オッフェンバックの軽快な作品は、
市民が日常の不安を忘れ、「笑い」と「風刺」を楽しむための音楽
として支持されました。
変革前夜の日本における文化の静けさ
一方の日本では、依然として江戸文化が色濃く息づいていました。
歌舞伎や講談といった大衆芸能は盛んでしたが、西洋音楽が日常に流れるようになるのは、まだ先の時代のことです。
その点では、すでにオペレッタが庶民の娯楽として定着していたフランスとは対照的でした。
とはいえ、フランスで人々を楽しませた娯楽音楽『地獄のオルフェ』は、後に日本にも伝わり、明るく軽快なその旋律は日本人にも広く受け入れられました。現代では『天国と地獄』の名で、運動会やテレビなど、日常のさまざまな場面で親しまれ続けています。
1858年を“世界史の交差点”として読む
1858年という年を覗き込むと、音楽、政治、社会が複雑に重なり合う姿が見えてきます。
作品を知ることは、作曲家の意図だけでなく、その時代に生きた人々の空気を知ることにもつながります。
音楽は社会の写し鏡である
『地獄のオルフェ』は、19世紀フランスの大衆文化がどのように形成されていったかを理解するうえで重要な作品です。
時に軽やかで、時に風刺的な音楽は、第二帝政期の社会状況を映し出す鏡のような存在でした。
日本とフランス、異なる場所で同じ「変革」が進んでいた
日本とフランスは遠く離れていましたが、どちらの国もこの時期に大きな変化を迎えていました。
世界を並列に見ることで、幕末史もフランス史も、より立体的に理解できるようになります。
日常にある音楽から、歴史を感じ取る
私たちはいま、運動会やテレビ、動画のBGMとして『天国と地獄』を当たり前のように耳にしています。しかしその背後には、第二帝政フランスの社会不安、パリの都市改造、幕末日本の外交交渉といった、複雑な歴史の積み重ねがあります。
音楽は単なる娯楽に留まらず、時代を超えて“当時の空気”を運んでくれる存在です。
日常の中でふとこの曲を耳にしたとき、その背景にあった1858年の世界に思いを寄せてみると、音楽は一層深みを増して感じられるのではないでしょうか。