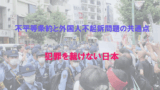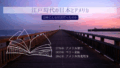令和時代の日本では、自衛隊が軍隊であり憲法違反だという意見もあるようです。その一方で、諸外国からは日本が再軍備を進めているようにも見えているようで、YouTubeなどで日本の自衛隊の話題も多く見受けられるようになりました。
元々国土を守る軍を持っていなかった日本は不平等条約を結ばされ、その解消のために軍備を整え、列強の仲間入りを果たしました。今回は、日本の急速な近代化の中心にあった比叡(ひえい)という軍艦の歴史と共に、日本の国防について考えます。
三隻の比叡
日本の歴史には、比叡(ひえい)という名前の軍艦(戦後は護衛艦)が三種類あります。
それぞれの比叡は、近代化を目指した日本の歴史の中心にあり、船の辿った歴史は、日本の近代化への苦難の道のりを教えてくれます。
比叡(コルベット)
最初の比叡は、明治時代に入ってすぐの頃にイギリスから購入した「コルベット」と呼ばれる小型の軍艦です。
江戸時代末期に、欧米諸国から軍事力を背景にした威圧的な外交を受け、不平等な内容の条約を締結させられた日本の最初の目標は「力を付けて不平等条約を解消する事」でした。
イギリスと日本の関係 – 不平等条約と同盟
比叡の購入元であるイギリスは、不平等条約(安政の五か国条約)の相手国の一つです。
日本で不平等条約というと、対アメリカの日米修好通商条約(1858年)が有名ですが、実際にはイギリス、フランス、オランダ、ロシア、アメリカの五か国と同様の条約を締結しており、これらを総称して「安政の五か国条約」と呼びます。
イギリスは明治維新前の日本とは縁が深く、下関戦争や薩英戦争などを通して日本(特に薩摩)の力を一定程度認めていたと考えられています。
明治時代の日本は、比叡など軍艦の取引や軍艦の製造技術など、イギリスに牽引されて成長した側面があり、第一次大戦前には日英同盟を結ぶに至ります。(日本は日英同盟を理由に第一次大戦へ参戦し、アジア方面のドイツ軍と交戦します)
イギリスとの不平等条約の解消は1894年、1911年と段階的に行われて行きます。時系列を少しまとめてみましょう。
| 西暦 | 出来事 |
|---|---|
| 1858 | 日英修好通商条約 |
| 1863 | 薩英戦争 |
| 1868 | 明治維新 (明治元年) |
| 1878 | 比叡(コルベット) 竣工 |
| 1890 | エルトゥールル号遭難事件 (後述) |
| 1894 – 1895 | 日清戦争 |
| 1894 | 日英通商航海条約 ※1 |
| 1902 | 日英同盟 |
| 1911 | 通商航海条約の改正 ※1 |
| 1914 | 第一次世界大戦に参戦 (日本) |
※1
1894年の日英通商航海条約の締結によって、治外法権(領事裁判権)の撤廃が成されます。日本で罪を犯した外国人が、日本の法律で裁けるようになりました。その後、1911年の条約改正によって関税自主権も回復します。
この年表からは、不平等条約がありながらも軍艦の取引は行われ、その上同盟関係にもなるという、イギリスと日本の不思議な結びつきが見えてきます。
比叡(コルベット)の活躍 – エルトゥールル号遭難事件
エルトゥールル号遭難事件は、日本では2015年に公開された映画「海難 1890」でも扱われたことで注目されました。1890年(明治23年)に日本の和歌山県海岸で、オスマン帝国(現トルコ)の軍艦エルトゥールル号が海難事故を起こし、500名以上の犠牲者が出た事件です。

画像引用元 : 海難1890 | 日本トルコ合作映画 | 田中光敏 監督
救助された乗組員は付近の村で手当てを受けて回復しますが、祖国に帰る術がありませんでした。明治天皇の命により「乗組員をオスマン帝国まで送り届ける」こととなり、比叡と金剛の二隻がその任にあたります。
比叡の遠洋航海実績と解体 – 近代国家の仲間入り
幕末期に喉から手が出るほど欲しかった「遠洋航海能力」を手に入れた日本は、比叡を手に入れて一度だけホノルル方面に向けて遠洋訓練を行っていましたが、オスマン帝国のある「地中海方面は未踏の地」でした。
この人道支援活動は、日本とトルコの友好関係にも大きく影響しており、イラン・イラク戦争(1985年)時には、現地に取り残された邦人を救出するためにトルコが航空機を派遣してくれています。
外交的にも大きな効果が得られた比叡と金剛の任務ですが、大日本帝国海軍としても「当時最高の軍艦で遠洋航海を成功させた」実績は非常に大きな成果となりました。
日本の近代化の象徴のような軍艦比叡(コルベット)は、不平等条約が解消された1911年に役目を終えて、売却・解体されています。
比叡(戦艦)
二隻目の比叡は、コルベットの比叡が解体された後(1911年)に起工され、1914年に竣工されます。
戦艦比叡の建造は、不平等条約を解消して晴れて列強の仲間入りを果たした日本が、いよいよ「軍拡競争」に乗り出した証でもあります。
先にイギリスで建造された金剛(巡洋戦艦)の技術を基に、日本で改造して建造されたのが比叡(戦艦)です。戦艦は、大規模な砲撃戦で強力な相手に勝つことを目的にした軍艦で、強力な艦砲と装甲を装備していました。
大艦巨砲主義と軍縮の波
第一次世界大戦を終結に導いたイギリスの「超ド級戦艦の力」を知った日本は、巡洋戦艦と戦艦を組み合わせた艦隊の建造計画(八八艦隊)を立てますが、軍縮条約の関係で中止となっています。
列強国が軍拡に次ぐ軍拡を続けてしまう状況を危惧し、軍拡に一定のルールを設けることになっていきますが、やっと列強に追いついた日本としては「投資したのに回収できない」という状況になっていきます。
ワシントン海軍軍縮条約(1921年 大正10年)によって軍縮の機運が高まり、1929年に比叡は第一次改装が始まります。その後、ロンドン海軍軍縮条約(1930年 昭和5年)の影響で、改装中だった比叡が戦艦から練習戦艦に改装されることに決定します。
戦艦機能の回復 – 大改装される比叡(戦艦)
1936年(昭和11年)に、ロンドン軍縮条約の期限切れを待って、日本は比叡の大改造に着手します。練習戦艦から改装し、戦艦としての機能を回復させるこの改装は、イギリスからも非難されます。
高速戦艦に生まれ変わった戦艦比叡は、その後の第二次世界大戦(大東亜戦争)でも活躍することになります。
戦艦比叡の沈没と発見
戦艦比叡は、1942年のガダルカナル島周辺海域で起こった第三次ソロモン海戦で沈没します。
1200名近くが登場できる比叡沈没時の戦死者は188名、負傷者は152名で、生存者は雪風などの駆逐艦で退避しています。航行不能となっていた比叡は、日本軍により沈没させるはずでしたが、退避後に戻った時には見つからなくなっていたと記録されています。
酷い豪雨の中での海戦で探照灯(サーチライト)を使った比叡は、敵だけでなく味方からも総攻撃を受けて大きな被害を出します。その後何とか味方の支援を受けながらも退却を試みますが、被害が拡大する危険性が高くなり、止む無く処分が決定されるという、何とも後味の悪い最期を迎えます。
沈没した比叡は、2019年にアメリカの調査チームが水深約1000mの海底で発見しています。
ひえい(護衛艦)
三隻目の比叡は、海上自衛隊の護衛艦で、名前は漢字ではなく平仮名の「ひえい」となっています。1970年(昭和45年)に起工され1974年(昭和49年)から就役していましたが、2011年に退役しています。
護衛艦「ひえい」は、就役期間は36年3か月と海上自衛隊最長で、航行距離は地球44周分にも上ります。

国防のための軍事力の是非
令和時代の世界情勢は緊張状態が続いており、日本も国防や安全保障の議論が絶えません。軍事力のなかった時代の日本がどのような事態に陥ったのか、私たちは歴史から学ぶ必要があります。
「三隻の比叡」の歴史からは、日本が被植民地化の危機から脱し、独立と平和を手に入れるまでの苦難の道が見えてきます。
国を守るための抑止力として軍事力が必要な世界は悲しいですが、安直な軍事力の放棄をするのではなく、永続的な安全保障を得るための建設的な議論を進めたいものです。
日本の不平等条約(特に治外法権)については以下の記事でも詳しくまとめてありますので、興味のある方は是非ご覧ください。