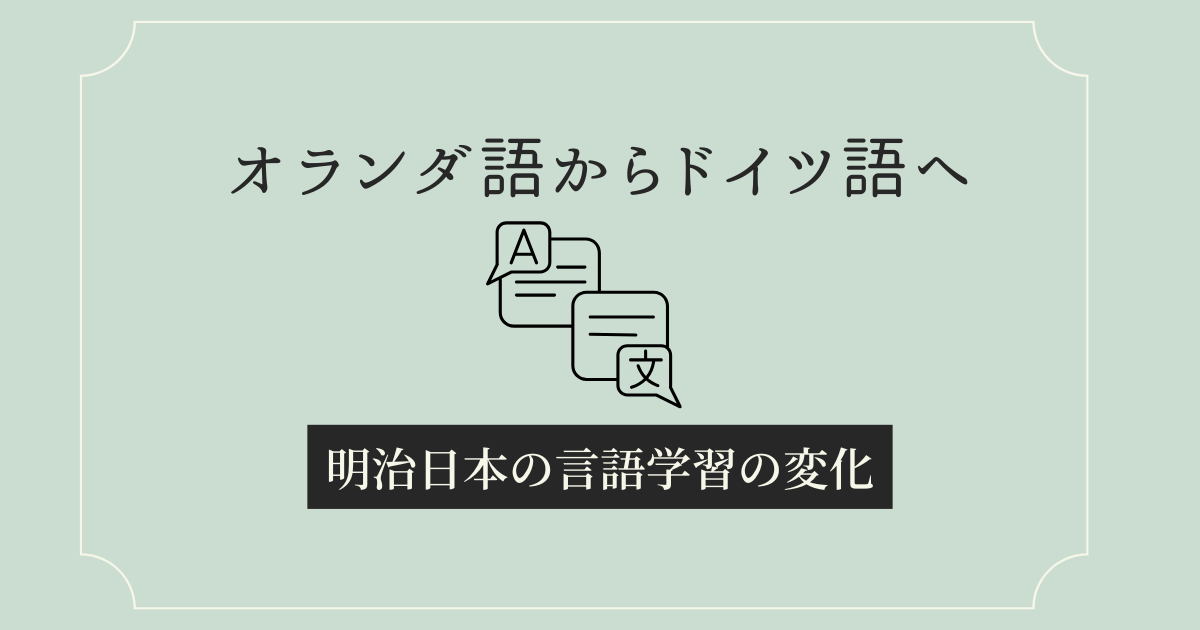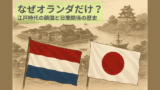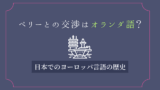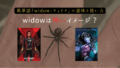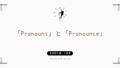💡この記事は、「日本とオランダ特集」の一部です。
かつて日本人が最も熱心に学んでいた外国語は、英語でも中国語でもなくオランダ語でした。
蘭学者たちが夢中で読み解いたオランダ語の医学書や天文学書は、日本の近代化の礎となりました。ところが明治の世になるや否や、学びの舞台はドイツ語に一変します。この急転換の理由はどこにあったのでしょうか。
幕末日本の外国語事情 – なぜオランダ語だったのか
江戸時代、日本がヨーロッパ世界と接点を持つ唯一の窓口は、長崎の出島に置かれたオランダ商館でした。鎖国政策の中でもオランダとの交易は例外的に許され、そこからもたらされる品物や書物が、当時の日本にとって唯一の西洋情報源となっていました。
このため、出島でオランダ商館員と交渉する通詞(通訳官)や、蘭学者と呼ばれる知識人が、西洋語としてのオランダ語を習得する必要がありました。オランダ語文献は、医学、航海術、砲術、天文学、化学など多岐にわたる分野をカバーしており、「オランダ語が読める=最新の西洋知識にアクセスできる」という図式が成立していたのです。
日本が鎖国時代にオランダと交易を続けていた歴史的背景などについては、以下の記事で詳しく扱っていますので、興味のある方は是非ご覧ください。
江戸時代のオランダ語教育
長崎のオランダ通詞は世襲が多く、子どもの頃から語学教育を受けました。教育方法は、現在の会話中心型とは違い、ほとんどが翻訳訓練でした。オランダ語の文章を単語ごとに日本語へ置き換える「逐語訳」を繰り返し、文法や語彙を身につけたのです。
使用された教材には、蘭和辞典『ハルマ和解』や『ドゥーフ・ハルマ』があり、これらは当時の必携書でした。
私塾でもオランダ語が学ばれました。大阪の緒方洪庵の適塾や江戸の芝蘭堂などでは、医師や志士たちが蘭書を片手に解剖学や化学を学び、オランダ語の専門用語を暗記しました。藩によっては、佐賀藩のように藩校とは別に蘭学所を設け、軍事技術や測量術を教える例もありました。
佐賀藩は幕末・明治維新期に活躍した「薩長土肥」の「肥 : 肥前(ひぜん)」で、オランダから学んだ武器製造技術は戊辰戦争などでも活かされました。
また、有名な「ペリー来航」も、当時日本人は英語が出来なかったため、条約交渉は日本語ーオランダ語ー英語という形式で通訳しながら行われました。詳しくは以下の記事をご覧ください。
オランダ語由来の外来語
実は日本の外来語には、オランダ語経由の言葉が多く存在しています。これは江戸時代のオランダとの交易や、開国後の外国とのやり取りがオランダ語を仲介としていたことが原因と考えられています。
現代でも使われている代表的な「オランダ語由来」の外来語には、以下のようなものがあります。
カルテやギプスなど一部の言葉は、ドイツ語でも同じ発音で、どちらの言葉に由来しているのか断言することは難しい状況にあります。江戸期にオランダ語経由で入ってきた後、明治期にドイツ語経由で広く普及、という二段階で定着した言葉が多いのです。
飲食関連
- コーヒー:koffie(コーフィー)→ コーヒー
- ビール:bier(ビール)
- ラム酒:rum(ラム)
- キャラメル:karamel(カラメル)
日用品・生活用品
- ガラス:glas(フラス/グラス)
- カンナ(鉋):kanna(鉋の道具名として定着)
- ランドセル:ransel(ランセル)
- ドンブリ(丼):kom(鉢)からの影響も指摘あり
医学・科学関連
- ピンセット:pincet(ピンセット)
- ギプス:gips(ギプス=石膏)
- カルテ:kaart(カード)→ ラテン語経由も絡む
- コレラ:cholera(ラテン語経由、オランダ語読みで定着)
その他
- スコップ:schop(スホップ)
- ドック(造船所):dok(ドック)
- ポンプ:pomp(ポンプ)
- ブリキ:blik(ブリク)
- オルゴール:orgel(オルゲル=パイプオルガン)
私たちの身近な飲み物ビール。最初に持ち込まれたのはペリー来航の時で、幕府への献上品だったといわれています。以下の記事でビールの歴史をまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。
明治政府がドイツ語を選んだ理由
明治政府が近代化を進める中で、外国語の選択は重要な政策課題でした。結果として、医学・軍事・法制度の分野でドイツ語が選ばれます。
- 医学:19世紀後半、ドイツ医学は解剖学・衛生学・臨床医学の分野で世界のトップレベルにあり、ドイツ人医師エルヴィン・ベルツらが日本で医学教育を指導しました。
- 軍事:普仏戦争(1870-71)でのドイツ勝利が、陸軍におけるドイツ式戦術の優位性を示しました。明治陸軍は参謀制度や訓練法をドイツから導入しました。
- 法制度:ロエスレルなどのドイツ人法律顧問の助言のもと、プロイセン憲法をモデルに大日本帝国憲法を制定しました。
このように、国家の根幹分野でドイツの制度や知識を導入する必要が生じ、そのための言語としてドイツ語が重視されたのです。
ドイツに訪問・留学した日本人
明治期にドイツへ訪問・留学した日本の政治家や文化人には以下のような人たちがいます。
政治・法学
- 伊藤博文
1882年、憲法制定の参考にするため、プロイセンやオーストリアを視察。ビスマルクと会談し、プロイセン憲法の影響を受けた。 - 井上毅(いのうえ こわし)
伊藤と共に憲法調査に関わった法学者・政治家。ドイツの憲法学・行政法を研究。 - 金子堅太郎
ハーバード出身だが、ドイツ法学の知識も習得し、憲法草案や国際法分野で活躍。
医学
- 森鷗外(森林太郎)
陸軍軍医として1884〜1888年にドイツ留学。衛生学・軍陣医学を学び、帰国後は近代衛生制度を整備。文学者としても有名。 - 高木兼寛(ただし彼はイギリス派)
対照的な例として、ドイツ医学ではなく英医学を導入した人物。森鷗外とよく比較される。 - 緒方正規
ドイツで内科学を学び、日本の近代内科学の基礎を築く。
軍事
- 川上操六
陸軍参謀本部長。ドイツの参謀本部制度や軍制を学び、日清戦争戦略の立案に影響。 - 児玉源太郎
ドイツ式軍事教育の影響を強く受けた指揮官。
ドイツ語由来の外来語
明治期に、プロイセン・ドイツから輸入した概念や技術に付随してたくさんの外来語が作られ、定着しました。一部の言葉は、本来の意味とは違う使い方で定着したものもあります。(アルバイトやゲレンデなど)
現代でも使われるドイツ語に由来する外来語には、以下のようなものがあります。
日常生活・一般
- アルバイト (Arbeit):仕事・労働 → 日本では「学生や短時間労働」
- テーマ (Thema):題目・主題
- エネルギー (Energie):エネルギー・力
- ゲレンデ (Gelände):地形・斜面 → スキー場のコース
- リュックサック (Rucksack):背嚢・リュック
- ランドセル (Ranzen):学童用かばん
- カッター (Kutter):小型艇、刃物名は転用
医学・科学・音楽など
- ワクチン(英語由来だが、ドイツ語読みで広まった経緯あり)
- レントゲン:発見者の名前(Wilhelm Röntgen)から
- アレルギー:Allergie
- リューマチ:Rheuma(ドイツ語発音)
- シューベルト/ベートーヴェン (作曲家名) → 固有名も多い
- オルガン (Orgel):パイプオルガン
- ソナタ、シンフォニー(イタリア語起源ですがドイツ語経由で用語化)
- カノン:Kanon
工業・技術
- ポンプ (Pumpe)
- ドリル (Drill)
オランダ語経験者がドイツ語へ移行できた背景
江戸時代のオランダ語教育は、明治期のドイツ語導入において大きなアドバンテージとなりました。理由は二つあります。
- ゲルマン語同士の近さ
オランダ語とドイツ語は共に西ゲルマン語派に属し、語彙や文法が似ています。
例:- 水:オランダ語 water/ドイツ語 Wasser
- 手:オランダ語 hand/ドイツ語 Hand
- 医師:オランダ語 dokter/ドイツ語 Doktor
オランダ語で文献を読めた人なら、ドイツ語の構造にも比較的早く慣れることができました。
- 翻訳技法の継承
蘭学者は、逐語訳や辞書活用法、専門用語の整理といった「外国語文献の攻略法」をすでに確立していました。これらはそのままドイツ語文献の読解に転用できたのです。
分野別の移行事例
- 医学
幕末にオランダ語医学書『ターヘル・アナトミア』で学んだ医師たちの多くが、明治になるとドイツ語の医学書を教科書に用いました。東京大学医学部では1870年代に授業言語をオランダ語からドイツ語へ切り替えましたが、教員の多くは元蘭学者でした。 - 軍事
蘭学砲術を修めた藩士や幕臣が、明治陸軍でドイツ式戦術を学び直しました。通訳官や翻訳係には、元オランダ通詞が起用されることもありました。 - 法学
蘭書の翻訳経験を持つ法律家が、ドイツの民法典や憲法草案の翻訳を担当しました。専門用語の置き換えには、蘭学時代の語彙整理のノウハウが活かされました。
言語的比較:オランダ語とドイツ語
オランダ語とドイツ語は似ている部分も多いですが、違いもあります。
- 共通点:語順や単語の形が近いこと、動詞の活用や複合語の作り方も類似していることです。
- 相違点:ドイツ語は格変化(主格・対格・与格・属格)が多く、文法が複雑です。オランダ語は格がほぼ消失していますが、発音や綴りに独自の癖があります。
蘭学者にとっては、文法の複雑さよりも既知の単語が多いことの方が心理的ハードルを下げたといえます。
もし江戸にオランダ語がなかったら?
もし江戸時代にオランダ語教育がなかったなら、明治初期のドイツ語導入はもっと時間と労力がかかったでしょう。英語やフランス語を中心に据える政策もあり得ましたが、その場合、医学・法学・軍事の導入ルートや近代化のスピードは大きく異なっていた可能性があります。
オランダ語からドイツ語への移行は、単なる外国語の切り替えではありません。そこには、江戸時代から続く「外国語で知識を吸収する文化」と、「西洋の知を翻訳・体系化する技術」の連続性がありました。
明治日本の近代化は、幕末の蘭学者たちが築いた語学と知識の基盤の上に成り立っていたのです。
関連記事:友好国から敵国へ ― オランダに宣戦布告した日本
江戸時代には、ヨーロッパで唯一の交易相手国だったオランダから、日本は多くの事を学びました。しかし、近代化の流れの中で、日本はオランダに対して宣戦布告する運命を辿ります。
以下の記事では、明治以降の日本とオランダの関係をまとめていますので、興味のある方は是非ご覧ください。