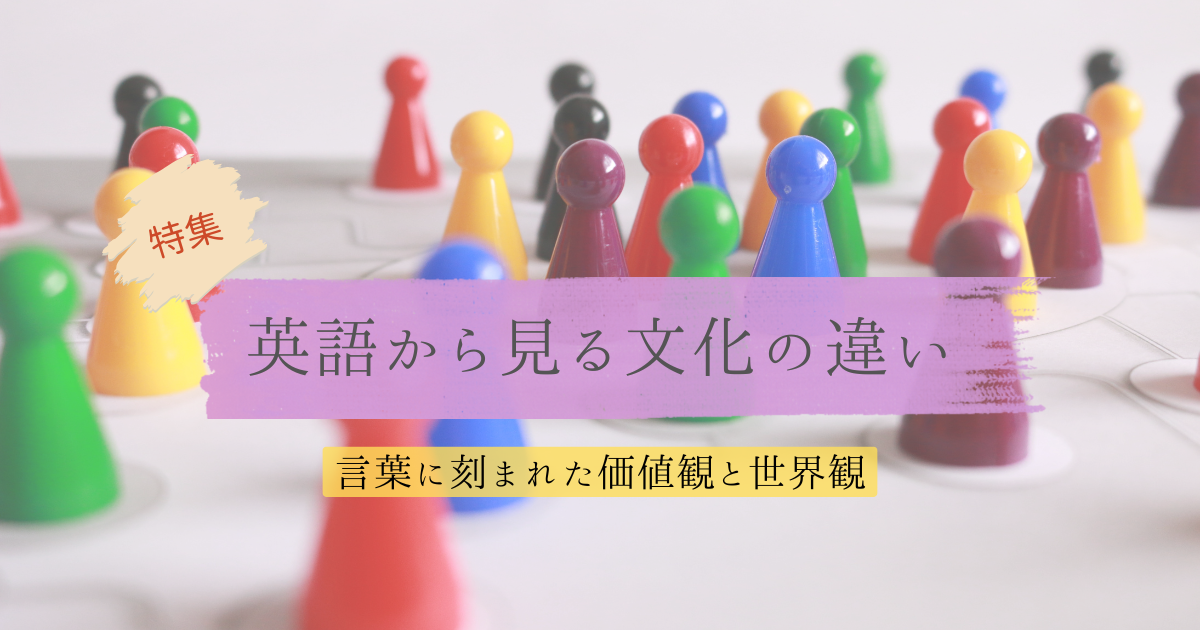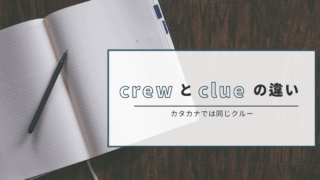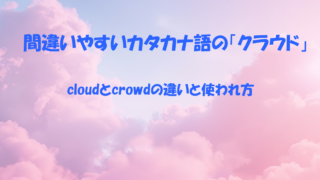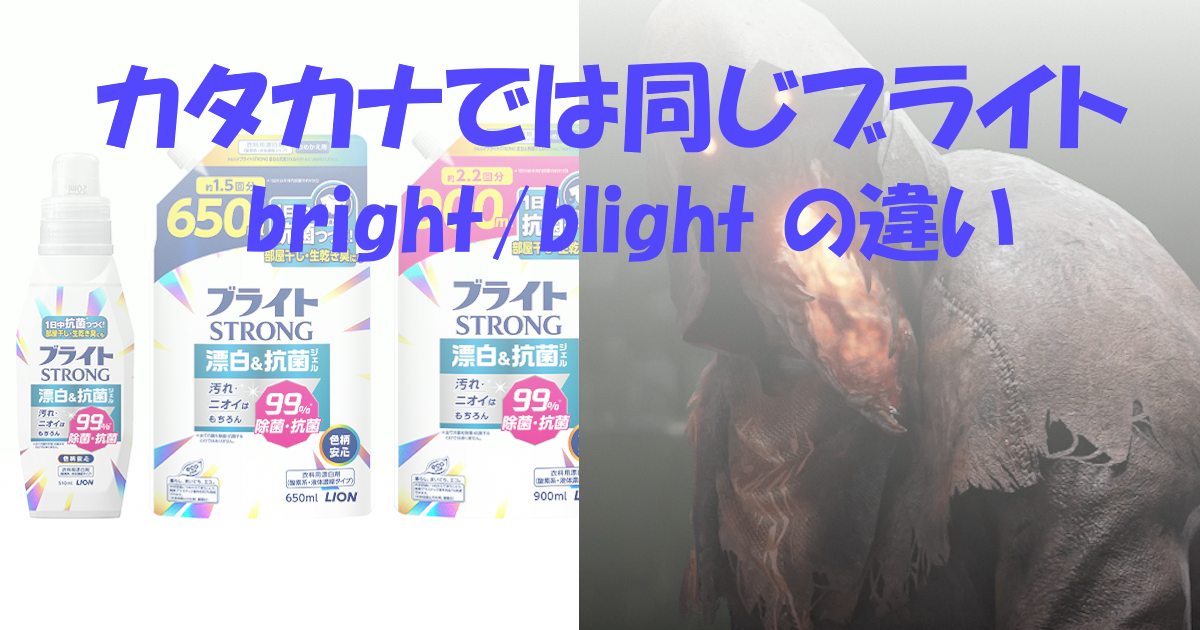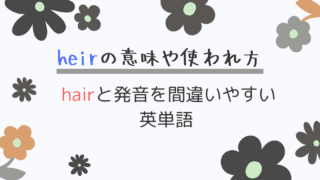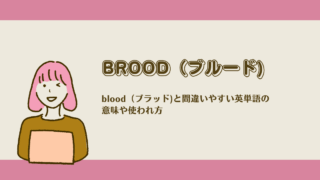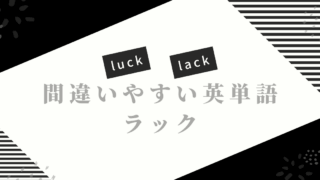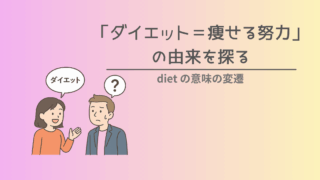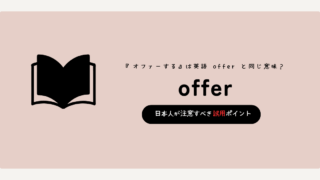英語と日本語は、同じものを指しているようで、実は異なる価値観や世界観を背負っています。
本特集では、英語の言葉を手がかりに、文化や宗教観の違いを読み解いていきます。
言葉の違いは、文化の違いでもある
言葉は、文化や価値観と切り離して存在することはできません。
英語も日本語も、それぞれ固有の歴史や宗教観を背景に持っています。
辞書に載っている「翻訳」は、最も妥当な言葉を当てて説明したものです。
しかし、その過程で、本来のニュアンスが十分に伝わらなくなっている言葉も少なくありません。
元の単語は状況や意味合いによって使い分けられていても、
翻訳語では同じ単語・言葉としてまとめられてしまうことがあります。
辞書に書かれた簡単な説明だけで、こうした違いを理解することは容易ではありません。
この特集では、翻訳の成否を評価するのではなく、
言葉の背景にある前提の違いを可視化することで、文化や世界観のズレを読み解いていきます。
宗教的背景を持つ言葉と、その翻訳
宗教は、英語と日本語の意味のズレが最も表れやすい分野の一つです。
同じ言葉で訳されていても、前提となる神観や世界観が異なるため、受け取られ方に違いが生まれてきました。
ここでは、宗教的背景を持つ言葉を手がかりに、その翻訳や理解のズレを整理します。
関連記事:間違いやすい英単語
発音や綴りが紛らわしい英単語について、実際の英会話で使ったり、英単語を聞き分けるのに役立つ記事を集めています。語源や由来など、印象に残りやすい雑学も多く紹介していますので、楽しみながら単語を習得できます。
発音が紛らわしい単語
日本語には外来語(カタカナ語)がある関係で、カタカナ表記した時に同じになってしまう英単語があります。特にRとLは、カタカナのラ行になってしまうため、日本人にとっては「紛らわしい」と感じる事がよくあります。
こういった発音が紛らわしい単語は、日本人からするとよく似ていますが、英語話者からすると「全く異なる単語」なので、会話で使う場合には注意が必要です。
意味が違う「カタカナ語」
日本語として一般的になっている外来語の中には、元の英単語と違う意味で使われるようになっている言葉も多くあります。
カタカナ語の意味のつもりで英単語を使ってしまうと、相手には意図が伝わらない可能性があるため、注意が必要です。