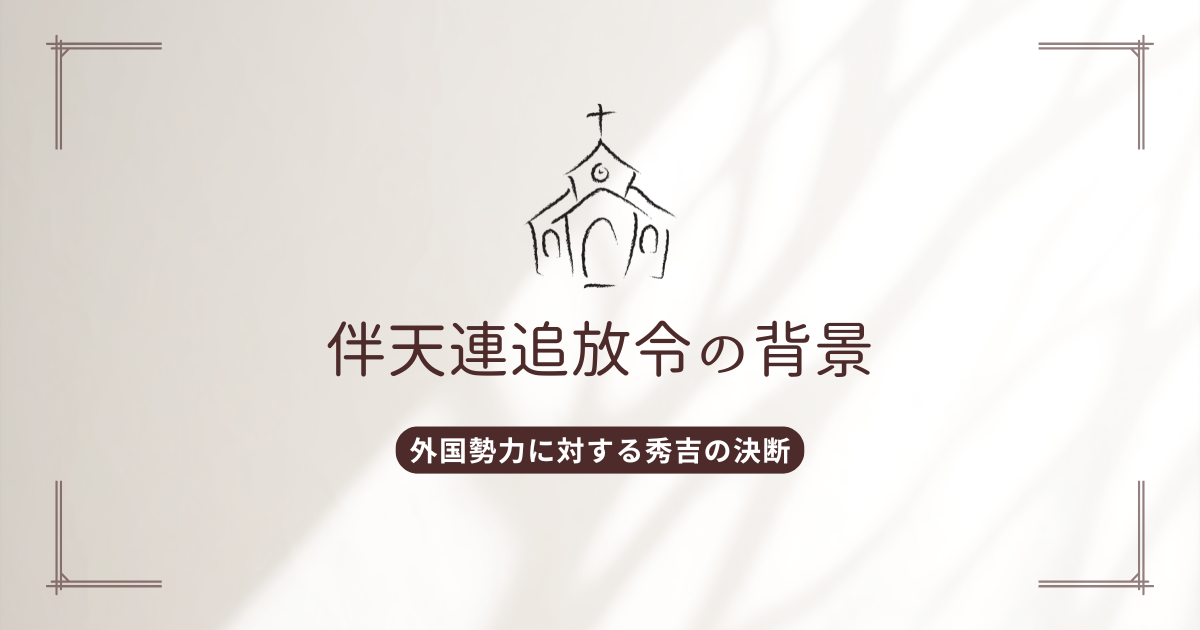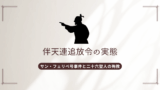💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
1587年、豊臣秀吉が発した「伴天連追放令(バテレン追放令)」は、日本史における最初の本格的な禁教政策として知られています。
しかしその意図は、単なる宗教弾圧ではありませんでした。
秀吉が見据えていたのは、外から静かに入り込む「支配の種」でした。宗教の陰に潜む外国勢力の影を察知し、日本の主権を守ろうとした政治的決断だったのです。
伴天連追放令とは
1587年6月、九州平定を終えた秀吉は、博多に滞在中に伴天連追放令(ばてれんついほうれい)を発しました。
内容は、宣教師の国外退去と布教活動の禁止を命じるものでした。
ただし、南蛮貿易自体は引き続き認められています。
つまり秀吉は、貿易の利益は維持しつつも、宗教による民心の支配を防ぎたかったのです。法令は信仰そのものを否定するものではなく、「国家秩序を守るための政治的対応」として出されたものでした。
雑学:伴天連(ばてれん)とは
「伴天連(バテレン)」という言葉は、ポルトガル語 padre(パードレ=神父、司祭)から転じた日本語化・音変化の形で、ポルトガル宣教師(イエズス会など)を指す言葉です。
| 言語 | 語形 | 意味 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラテン語 | pater | 父 | 「神父」の語源 (英語のfatherと同源) |
| ポルトガル語 | padre(パードレ) | カトリックの司祭・神父 | 宣教師が自称として用いた |
| 日本語(16世紀) | バテレン(伴天連) | 外国の宣教師 | 音変化+漢字表記による当て字 |
江戸時代の公文書や禁教令でもこの表記が用いられ、正式な行政語としても定着しました。
江戸時代以降はキリシタン・宣教師全般への蔑称的表現として用いられ、現代では史料・史学用語としてのみ使用されます。
秀吉が見た外国勢力の実態
秀吉がキリスト教に警戒心を抱いたのは、宗教が領国支配に影響を及ぼしていたからでした。
九州で広がる布教と改宗
16世紀後半、九州ではポルトガル人宣教師を通じてキリスト教が急速に広まりました。
特に、大村純忠、有馬晴信、大友宗麟といった「キリシタン大名」たちは、積極的に布教を支援し、寺院を壊し、領民を改宗させるなど、信仰を政治に利用する動きが顕著でした。
ポルトガル人に寄進された「長崎の港」
その中心地となった長崎では、教会の鐘が鳴り響き、仏像が破壊され、町そのものがキリスト教文化に染まっていました。

さらに大村純忠は長崎の港をポルトガル人に寄進し、実質的に外国の支配地のような状態にまでなっていたのです。
大村純忠による「長崎港寄進」の実態
1571年(元亀2年)、純忠はポルトガル船の入港を受け入れ、自身の領内の小村だった長崎を開港します。それまで口之津港などを利用していたポルトガル商人や宣教師たちは、これを機に長崎へと拠点を移しました。
この年が、現在に続く長崎港の歴史のはじまりとされています。
開港後、純忠はイエズス会の活動をさらに支援し、
港およびその周辺の土地・税収権を教会(イエズス会)に寄進しました。
結果として、長崎では教会が行政や治安維持を担い、宣教師が町を統治するという、宗教自治都市のような体制が形成されました。
町には教会や修道院が建ち並び、南蛮風の文化が息づいていました。
外国勢力による“植民地の前兆”
秀吉は九州平定の際、こうした状況を目の当たりにします。彼の脳裏に浮かんだのは、アジアの各地で展開されていたスペイン・ポルトガルの植民地支配でした。
宣教師が先に布教を行い、その後に武力・貿易で支配を進める――マカオやマニラがその典型です。
日本が同じ道をたどる危険を感じた秀吉は、「宗教の背後に国家がある」と見抜きました。
そして、布教そのものを制限するという政治判断に踏み切ったのです。
植民地政策を把握していた秀吉
秀吉は、アジア各地でスペインやポルトガルが進めていた植民地支配の仕組みを、現代のように体系的に理解していたわけではありません。しかし、宣教師や南蛮商人を通じて得た情報から、布教と貿易、そして軍事力が連動していることを察知していたと考えられます。
イエズス会の宣教師ルイス・フロイスやガスパル・コエリョは、マカオやルソン、インドといった地域の情勢を秀吉に伝えていました。このため秀吉は、ポルトガルがマカオを、スペインがルソン(フィリピン)を支配していることを知っており、同じ構図が日本にも及ぶ危険性を強く意識していたようです。
実際、コエリョが長崎周辺で砦の建設を提案した際、秀吉は「これは布教のためではなく軍事拠点化の前兆だ」と直感したと伝えられています。
このような警戒心は、伴天連追放令を発布する大きな要因の一つになりました。
さらに秀吉は、後年フィリピンのスペイン総督へ書簡を送り、「日本の支配下に入るべきだ」と挑発的な文面を送ったことも知られています。
こうした行動からも、秀吉が当時のアジアの国際情勢をある程度把握し、宗教の背後にある国家の意図を見抜いていたことがうかがえます。
日本人奴隷貿易と秀吉の怒り
秀吉に伴天連追放令を決断させたのは、さらに衝撃的な報告でした。
それは「日本人が海外で奴隷として売られている」という事実です。
海外で売られる日本人
当時、南蛮貿易の一環として、日本人の女性や子供がポルトガル商人の手によってマカオやルソンに送られ、奴隷として売られていました。中には、キリスト教徒を名乗る者が人身売買に関わっていた例もあり、秀吉の怒りは頂点に達します。
彼は宣教師コエリョを呼び出して厳しく問い詰め、即座に奴隷貿易の停止を命じました。

さらにローマ教皇に宛てて抗議文を送り、日本人を奴隷として扱うことを禁じるよう要請したと伝えられています。この訴えを受けて、教皇庁も「日本人奴隷の売買を禁止する勅令」を出すに至りました。
秀吉の外交的感覚
この行動は、単なる宗教政策ではなく、国家元首としての外交的主張でした。
秀吉は、信仰の自由よりもまず「日本人の尊厳」と「主権の独立」を優先したのです。
伴天連追放令は、こうした一連の怒りと警戒の延長線上にありました。
秀吉の決断とその影響
追放令の最大の特徴は、「貿易を維持しつつ布教を禁じた」点にあります。
この線引きは、秀吉が宗教を排除する意図ではなく、外国勢力の政治的干渉を防ぐ意図だったことを示しています。
宣教師=外国の使節という認識
秀吉は宣教師を「神の使い」ではなく、「国の使い」として見ていました。
彼らは宗教家であると同時に、スペイン・ポルトガルの国策を担う外交官でもあったのです。
この認識は後に徳川幕府にも受け継がれ、「キリスト教=外圧」という構図が定着していきます。
長崎の没収と直轄化
追放令と同じ1587年、秀吉は長崎を没収して直轄地としました。
それまでイエズス会の支配下にあった港を「日本の港」として取り戻したのです。
この政策は、単なる宗教統制ではなく、国家主権の回復を意味していました。
長崎直轄化の実態と影響
長崎直轄化の命が出されると、ポルトガル商人や宣教師たちの間に強い不満が広がりました。
しかし、イエズス会やポルトガル勢が実力で抵抗することはありませんでした。
彼らには兵力がなく、秀吉と対立すれば南蛮貿易そのものが断たれてしまう恐れがあったためです。ルイス・フロイスの記録によれば、宣教師たちは秀吉の決定を「神の御心に反する」と嘆きつつも、最終的には従わざるを得なかったとされています。
秀吉は長崎の支配権を取り戻した後、中央の管理下に置くために「長崎奉行」を設置しました。
実際の運営は寺沢広高に任され、商人や外国人との取引を調整しながら、秩序ある貿易港として再建していきます。経済活動そのものは維持されたため、大規模な混乱や戦闘は発生しませんでした。
長崎直轄化は、後の徳川幕府による鎖国政策や朱印船制度の原型ともいえる、対外政策上の大きな転換点となりました。
現代への示唆 ― 多文化共生と主権のバランス
伴天連追放令は、異文化とどう向き合うかという永遠の課題を私たちに突きつけます。
秀吉の決断は、排外主義ではなく、「日本という国の軸を保つための自己防衛」でした。
「信仰」と「国家」を分ける難しさ
現代社会でも、宗教・思想・文化が政治や経済と深く結びついています。
多文化共生を進める中で、外から流入する価値観を無条件に受け入れることが「良いこと」とされがちですが、その背後には国家の形や社会の秩序を揺るがすリスクも潜んでいます。
秀吉の時代から学ぶ視点
異文化を排除する必要はありません。
しかし、自国の文化・価値観・主権を守るためには、時に明確な線を引く勇気が求められます。
伴天連追放令は、その難題に最初に直面した歴史の教訓でもあるのです。
共存と自立の線引き
伴天連追放令は、単なる宗教弾圧ではなく、「国家をどう守るか」という問いへの答えでした。
秀吉の決断は、外からの圧力に対し、日本が自らの立場を示した最初の防衛線とも言えます。
異文化の波が再び押し寄せる現代、私たちもまた、問われています。
「共存」と「自立」は、どこで線を引くべきか――。
秀吉の時代に下された一つの命令は、いまも静かにその問いを投げかけています。
関連年表:
【年表】伴天連追放令の歴史 ― ザビエルから秀吉の死まで
ザビエルの来日から秀吉の死までの流れを、時系列で整理しています。
関連記事:伴天連追放令の実態
伴天連追放令は、秀吉が国を守るために定めた警告としての布告でした。
しかし、その後も活動を続けた宣教師の行動や、日本に漂着したスペイン船・サンフェリペ号の事件を通じて、キリスト教の禁止は警告から実行に移ることになります。
伴天連追放令の実態については、以下の記事をご覧ください。
また本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。