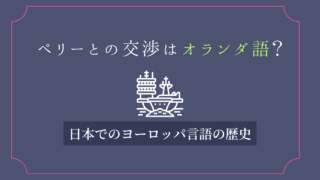ペリー来航は、日本史の大きな転換点として知られています。
本記事では、その直前の時代に起きたロシア・イギリスとの接触と衝突に目を向け、日本がすでに外圧と向き合い始めていた過程を辿ります。
ペリー来航は「始まり」だったのか
日本史において、ペリー来航は「開国の始まり」として語られることの多い出来事です。
黒船の来航によって、鎖国体制が終わりを迎え、日本が外の世界と本格的に向き合い始めた――多くの人が、そうしたイメージを思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし本当に日本は、ペリー来航(1853年)によって初めて外圧に直面したのでしょうか。
外圧によって変化し始める日本 ― 本記事で扱う内容
実際には、ペリー来航以前から、日本はすでにロシアやイギリスと接触し、時には衝突さえ経験していました。それらはペリー来航ほど有名ではありませんが、日本の政治や人々の考え方に少なからぬ影響を与えています。
本記事では、ペリー来航の「前夜」にあたる時代に目を向けます。
ロシアとの交渉と武力衝突、イギリス軍艦の侵入といった出来事を通して、日本社会がすでに揺れ始めていた過程を整理していきます。
泰平の世だった江戸時代が、外からの刺激によって変化を迫られるようになる「その瞬間」の歴史を辿ることで、江戸時代後期に起きた政治や学問、価値観の揺らぎについて理解を深めていきます。
ロシアとの接触と衝突
ペリー来航以前、日本が最初に本格的な接触を持った列強はロシアでした。
その関係は、最初から武力衝突として現れたわけではなく、段階的に緊張を高めていきます。
最初の公式接触 ― アダム・ラクスマン来航(1792年)
1792年、ロシア使節アダム・ラクスマンは、蝦夷地の根室に来航しました。
来航の名目は、日本人漂流民の送還でしたが、その背後には通商の可能性を探る意図がありました。
この時点での接触は、あくまで外交的な試みにとどまっています。
日本側もロシア側の要求を即座に受け入れることはなく、かといって強硬に排除することもありませんでした。
松前藩経由で慎重に対応が進められ、日本政府(幕府)と正式な外交交渉を行う場として、長崎に寄港することができる信牌(しんぱい:通行証)が与えられました。
ラクスマン来航は、日本とロシアが国家として初めて正面から向き合った出来事でしたが、この段階では、双方ともにまだ「探り」の域を出ていなかったと言えるでしょう。
本格的な通商要求 ― ニコライ・レザノフ来航(1804年)
ラクスマン来航から十数年後の1804年、ロシアは全権使節ニコライ・レザノフを長崎に派遣します。
レザノフは、漂流民送還を名目とした前回とは異なり、ロシア帝国の国家意思を背負い、正式な通商を求めて来航しました。
幕府はこの要求に対し、長期間にわたって慎重な対応を取ります。
しかし最終的には、従来の鎖国体制を維持する立場から、ロシアの通商要求を拒否しました。
この交渉過程では、武力が用いられることはありませんでした。
それでも、正式な外交交渉が決裂したことで、日露関係は明らかに緊張を深めていきます。
レザノフ来航は、日本が「外交による解決」を試みた結果として行き詰まりを迎えた、重要な転換点でした。
交渉から武力へ ― 文化露寇(1806–1807年)
1806年から1807年にかけて、ロシアは日本の北方地域で武力行動に及びます。
ロシア艦隊は択捉や樺太周辺で日本の拠点や商船を襲撃しました。これに対して日本側も松前藩を中心に防備や応戦を行いましたが、地理的条件や軍事力の差から、ロシア側の行動を完全に抑止するには至りませんでした。
この一連の事件は、一般に文化露寇(ぶんかろこう)と呼ばれています。
事件の背景 ― 両国の思い
文化露寇は、突発的に起きた事件ではありませんでした。
当時のロシアは、ヨーロッパで続く戦争に国力を割かれており、シベリアやカムチャツカなど太平洋側の拠点を十分に維持する余裕を失いつつありました。
- 補給が不安定
- 生活物資が不足
そのため、近隣に位置する日本との通商は、太平洋側の補給や交易を安定させる現実的な手段として重視されており、交渉も正式かつ穏便に進められました。
しかし日本側は、鎖国体制という秩序維持を優先し、その要求を拒否します。
- ロシアが困っているかどうかは、日本の統治責任ではない
- 一国に例外を認めれば、制度全体が揺らぐ
- 鎖国は「外交遮断」ではなく「秩序維持の仕組み」
ロシア側から見れば、通商要求は正当なものであり、日本側の対応は誠意を欠くものと映っていました。ロシアは交渉を打開するため、恒久的な占領を目的としない示威的な武力行動に踏み切ります。
しかし、日本側から見れば、これは明確な主権侵害でした。ロシア艦隊による拠点や商船への攻撃は、交渉の延長というよりも、突然の暴力として受け止められます。
事件の影響 ― 高まる海防意識
この事件によって、日本は北方からの脅威を現実のものとして認識するようになります。
文化露寇そのものは短期間で収束しましたが、その衝撃は大きく、北方警備の強化や海防意識の高まりへとつながっていきました。
なお、こうした緊張状態は文政年間に入っても尾を引き、北方情勢への警戒が続いたため、文献によっては「文化・文政露寇」と総称されることもあります。
ただし、文政期に文化露寇と同規模の軍事衝突が再び起きたわけではなく、主に影響と警戒が継続した時代として理解するのが適切でしょう。
なお、こうした緊張状態は文政年間に入っても尾を引き、北方情勢への警戒が続いたため、文献によっては「文化・文政露寇」と総称されることもあります。
ただし、文政期に文化露寇と同規模の軍事衝突が再び起きたわけではありません。
イギリスとの衝突
ロシアとの関係が、外交交渉の積み重ねの末に武力衝突へと至ったのに対し、イギリスとの接触は、まったく異なる形で日本に衝撃を与えました。
それは、交渉や通商要求を伴わない、突発的な軍事的接触でした。
交渉なき外圧 ― フェートン号事件(1808年)
1808年、イギリス軍艦フェートン号は長崎港に侵入します。
当時、日本とイギリスの間に正式な外交関係や通商交渉は存在していませんでした。
フェートン号はオランダ船を装って港内に入り、オランダ商館関係者を拘束した上で、食料や水などの物資提供を要求します。
日本側は有効な軍事的対応を取ることができず、最終的に要求を受け入れざるを得ませんでした。
この事件は、日本にとって「交渉を経ない外圧」を初めて体感する出来事となります。
事件の背景 ― ヨーロッパ情勢と情報の断絶
フェートン号事件の背景には、当時のヨーロッパ情勢があります。
1808年はナポレオン戦争の最中であり、イギリスとフランスは激しく対立していました。
日本と交易関係にあったオランダは、フランス側に立っていたため、イギリスから見れば、長崎は敵国関係者が活動する可能性のある港でした。
この時期のオランダは、以下のような変遷をたどりながら、フランス体制下に組み込まれていました。
- 1795年:フランス革命軍に占領
- 1795–1806年:バタヴィア共和国(フランスの衛星国)
- 1806–1810年:ホラント王国(ナポレオンの弟が国王)
フェートン号の目的は、日本との外交交渉ではなく、敵対国オランダの船舶や拠点を牽制し、必要な補給を得ることにありました。
一方、日本側はヨーロッパの戦争状況を十分に把握しておらず、なぜイギリス艦が長崎に現れたのか、その意図を即座に理解することができませんでした。
この情報の断絶こそが、フェートン号事件を、日本にとって「理由の分からない外圧」として受け止めさせる要因となりました。
日本とオランダの関係について詳しく知りたい方は、是非以下の特集記事もご覧ください。
💡関連記事:日本とオランダ特集 ― 日蘭関係から読み解く世界と歴史
事件の影響 ― 動揺と危機意識
フェートン号事件は、日本社会に強い心理的衝撃を与えました。
とりわけ、外国船の侵入を防げなかった責任を問われ、長崎奉行が切腹したことは、幕府がこの事件をどれほど深刻に受け止めたかを示しています。
この出来事は、ロシアとの衝突とは異なり、通商や外交交渉の延長として理解できるものではありませんでした。
理由も目的も分からないまま、軍艦が港に侵入し、人質を取り、要求を突きつける――
その体験は、日本にとって「理不尽な外圧」として記憶されます。
フェートン号事件を通じて、日本は、鎖国体制のもとでは把握しきれない国際情勢と、
軍事力を背景にした一方的な行動の現実を突きつけられることになりました。
外圧がもたらした変化
これらの外圧は、単なる外交上の事件にとどまりませんでした。
日本の政治や、人々の考え方に、じわじわと影響を及ぼしていきます。
政治・政策への影響
ロシアとの接触や文化露寇、フェートン号事件は、いずれも個別の事件としては一過性の出来事として収束しています。
しかしそれらは、共通して「外国勢力が日本の秩序を脅かし得る存在である」という現実を突きつけました。この認識は、幕府や知識人層の間で、徐々に共有されていきます。
1810年代から1820年代にかけて、外国船の出没は各地で続きました。
その都度、場当たり的に対応するのではなく、沿岸防備の方針を明文化し、全国的に統一した対応を取る必要性が意識されるようになります。
こうした問題意識の蓄積の結果として、1825年に出されたのが異国船打払令(いこくせんうちはらいれい)です。
異国船打払令は、日本の沿岸に接近する外国船のうち、オランダ・中国・朝鮮・琉球を除く船舶に対し、理由を問わず砲撃して撃退することを命じた法令でした。外圧を「例外的な出来事」ではなく、「想定すべき危険」として制度の中に位置づけた点に特徴があります。
ロシア・イギリスとの衝突は、日本が外からの脅威を現実のものとして認識し、それに対応するための政策が動き出したきっかけの出来事だったと言えるでしょう。
社会・思想への影響 ― 静かに揺らぎ始めた世界認識
ロシアやイギリスとの衝突は、直ちに日本社会全体の価値観を大きく変えたわけではありません。
多くの人々にとって、日々の暮らしや社会秩序が急激に変化した実感は乏しかったでしょう。
しかし一方で、知識人層や一部の武士の間では、日本を取り巻く世界に対する認識が、徐々に揺らぎ始めていました。
異国船の来航や武力衝突は、もはや想像上の出来事ではなく、現実の問題として受け止められるようになります。それは、日本が長く前提としてきた「外の世界は一定の距離を保てる存在である」という感覚に、疑問を投げかけるものでした。
こうした状況の中で、海防や軍事に関する関心が高まり、砲術や測量といった実学的知識への注目が集まります。それらは単なる学問的興味ではなく、「いざという時に何が役に立つのか」という、切実な問題意識に基づくものでした。
また、外国勢力との接触を通じて、日本の制度や秩序が普遍的なものではないという認識も、少しずつ広がっていきます。鎖国体制は依然として維持されていましたが、その内側では、「この仕組みは、どこまで有効なのか」という問いが、静かに芽生え始めていました。
こうした変化は、後に幕末期に顕在化する海防論や開国論、さらには学問・思想の転換を支える土壌として、静かに積み重なっていったと言えるでしょう。
江戸時代の学問・思想の歴史については、以下の特集記事にまとめています。
💡関連記事:江戸時代の学問・思想特集 ― 時代と系統で読み解く知の全体像
ペリー来航との違い ― 何が決定的に異なっていたのか
ここまで、ペリー来航以前に起きたロシアやイギリスとの接触と衝突を見てきました。
結局のところ、ペリー来航とそれ以前の出来事は、何が違っていたのでしょうか。
結論から言えば、ペリー来航は、それ以前の外圧と質的に異なる側面を持っていました。
両者の違いを整理することで、ペリー来航の意味も、より立体的に見えてきます。
軍事力と外交交渉の関係
ロシアやイギリスとの接触では、武力が用いられる場面はありましたが、
それが一貫した外交交渉と結びついていたわけではありませんでした。
交渉と衝突が分断され、状況ごとに対応が変わる、散発的な関係だったと言えます。
これに対してペリー来航では、軍事力による威嚇と、明確な外交要求が最初から一体となって示されました。
ここで初めて、日本は「軍事力を背景にした外交交渉」という形で外圧を受けることになります。
ペリー来航は、軍事力を背景に外交交渉を迫る、いわゆる砲艦外交の典型例といえます。
継続性と国家意思の明確さ
ペリー来航以前の外圧は、特定の地域や状況に依存した出来事として現れることが多く、必ずしも国家としての一貫した意思が明示されていたとは言えませんでした。
一方、ペリー来航は明確な国家意思に基づき、再来航の予告を含めた継続的な圧力として提示されました。
この点で、偶発的な衝突と、本格的な外交圧力との違いがはっきりと表れています。
日本社会に与えた影響の広がり
ペリー来航前のロシアやイギリスとの衝突は、主に幕府や知識人層の間で深刻に受け止められた一方で、庶民にとっては生活と直結する問題として共有されるまでには至っていませんでした。
ペリー来航は、それ以前から一部の人々の間で意識されていた変化や疑問を、政治・社会・学問といった分野を越えて、日本社会全体の課題として可視化した出来事だったと言えるでしょう。
日本の転機としての「ペリー来航前夜」
ペリー来航は、日本史における大きな転換点であることは間違いありません。
しかし、それは何もないところに突然現れた出来事ではありませんでした。
ロシアやイギリスとの接触と衝突を通じて、日本はすでに外の世界と向き合い始めていました。
平穏に見えた江戸社会の内側では、政治も学問も、人々の考え方も静かに揺れ動いていたのです。
「正しさ」と「強さ」
江戸時代の価値観の土台といえる朱子学では、世界や人間を次のように捉えていました。
- 世界には理(正しさ・秩序)がある
- 人は本来、その理に従う存在である
- 正しくない行為は無知・徳の欠如・教化不足の結果
と考えられていました。
しかし、ロシアやイギリスの行動は
- 理に反しているように見える
- 徳によって動いているように見えない
- それでも、実際に力を持っている
として、朱子学的世界観にとって極めて受け止めにくい現実を突きつけました。
「正しさ」と「強さ」は同じものではなかったのです。
「正しさ」を守るために「強さ」が必要となる――。
これは現代にも通じることでしょう。
学問や思想の前提が問い直されはじめ、政治は「強さ」をどのように実現するかを模索していく動きが、次第に表面化していくことになります。
ペリー来航に関連した以下の記事も、是非ご覧ください。