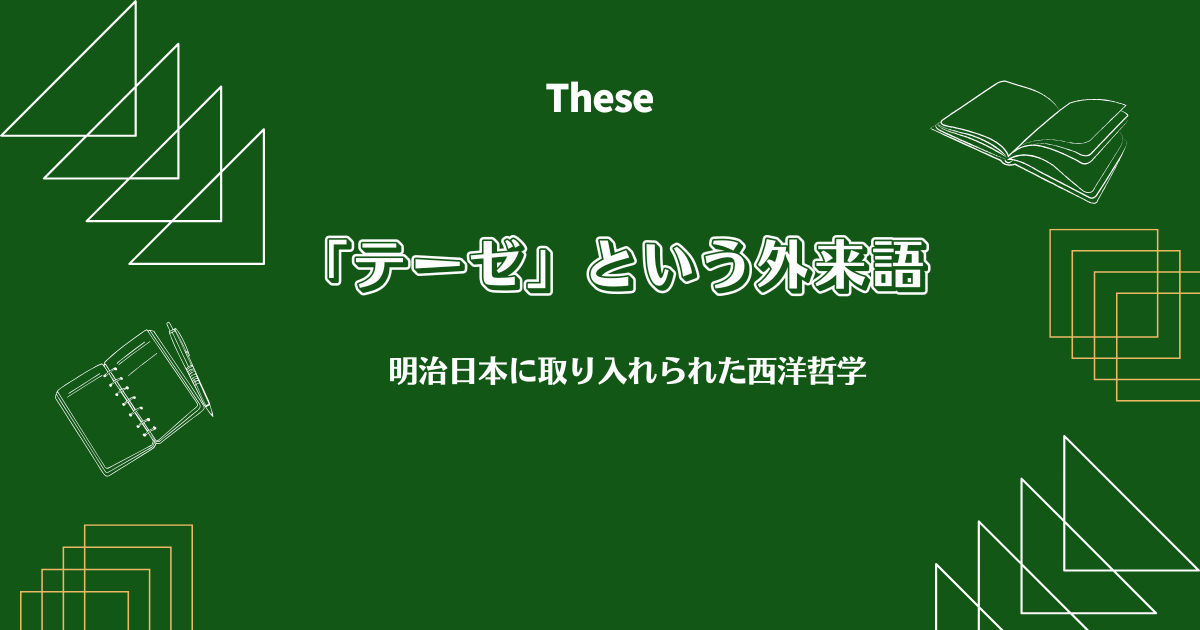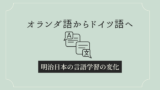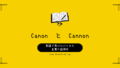「テーゼ」という外来語は、どこから来たのでしょう。
「アンチテーゼ」という言葉や、アニメの歌にも登場する「テーゼ」。
本記事では、その意味や使われ方とともに、言葉がたどった歴史をひもときます。
「テーゼ」とは何か ― 外来語の意味と使われ方
西洋哲学の専門語が、いつの間にか私たちの日常語に溶け込んでいることがあります。「テーゼ」もそのひとつです。アニメのタイトルや評論などで耳にすることがありますが、もともとは哲学の用語として日本に入ってきました。
意味と語源 ― テーゼは「命題」「主張」
「テーゼ(These)」とは、ドイツ語で「命題」「主張」を意味します。
語源をたどると、ギリシャ語の “thesis(テーシス)” に行き着きます。これは「置くこと」「立てること」を意味し、「自分の立場を提示する」というニュアンスが込められています。
英語では “thesis(スィーシス)” といい、大学の「卒業論文(thesis)」の語源も同じです。
つまり、「テーゼ」は自分の考えを“立てる”行為そのものを指しているのです。
哲学ではこの「テーゼ」に対して
反対の立場を示す「アンチテーゼ(Antithese)」、そして
両者を統合する「ジンテーゼ(Synthese)」
があり、この三段階が「弁証法」と呼ばれます。
アンチテーゼの「アンチ(anti)」は何語?
アンチテーゼ(Antithese)の“アンチ(anti)”は、ギリシャ語由来の接頭辞で、英語もドイツ語も同じ形で使われます。
英語でのアンチテーゼは“antithesis(アンチシス)” となります。
現代での使われ方
現代日本では、「アンチテーゼ」の方が耳にする機会が多いかもしれません。
たとえば、「彼の作品は現代社会へのアンチテーゼだ」といえば、現代の常識や価値観に対する批判・対立の立場を意味します。このとき、批判の対象となる「現代社会」こそがテーゼ(主張・前提)にあたります。
また、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌「残酷な天使のテーゼ」は、多くの人にとって「テーゼ」という言葉を知るきっかけになりました。ここでは「天使の命題」という意味に近く、哲学的な響きをもつタイトルとして機能しています。
雑学:なぜ「アンチテーゼ」だけがよく聞くのか
「アンチ」という響きがキャッチーで、反発や対立を表す言葉として使いやすいためです。
英語文化圏でも、“thesis” より “antithesis” の方がメディアで取り上げられやすい傾向があります。
人は「肯定」よりも「反発」に惹かれやすいのかもしれません。
明治時代に取り入れられた「テーゼ」
「テーゼ」という言葉は、単なる外来語ではありません。明治時代、日本が西洋の学問を吸収していく過程で、ドイツ哲学の一部として導入されたものです。
明治政府が導入した「哲学」という学問
明治初期、日本政府は「文明開化」を進める中で、西洋の学問を体系的に取り入れました。
そのとき活躍したのが西周(にしあまね)です。
彼は“philosophy”を「哲学」と訳し、日本に初めて学問としての「哲学」を根づかせました。(1870年代)
哲学という単語は、日本で作られた「和製漢語」です。
当初、日本の知識人たちは主にイギリスやフランスの思想を学びましたが、やがてドイツ哲学が主流となっていきます。
ドイツ思想は国家や秩序を重視する傾向があり、明治政府の求めた「近代国家建設」と親和性が高かったからです。
関連記事:日本で作られた和製漢語
明治期に日本で作られた「和製漢語」の多くは中国にも逆輸入された他、ベトナムなどアジア諸国の近代化にも役立てられました。
現在の中国の国名に含まれる「人民」や「共和国」は、日本で作られた和製漢語ですが、中華民国の「民国」は違います。以下の記事では、誇り高い孫文の選択と、当時の中国の状況を紹介しています。
また「迷惑」という言葉も日本で作られた和製漢語です。ただ、「哲学」や「共和国」のように翻訳で作られた単語ではないため、海外に該当する概念は存在しません。外国との価値観の違いなどに興味がある方は、是非こちらの記事もご覧ください。
大学で教えられたヘーゲル哲学
やがて東京大学を中心に、ドイツのヘーゲル哲学が講義で紹介されるようになります。
その中心人物のひとりが井上哲次郎(いのうえてつじろう)でした。彼は「弁証法」や「テーゼ/アンチテーゼ/ジンテーゼ」といった概念を日本に紹介し、学界に広めました。
当時の学生たちは、ヨーロッパから輸入された新しい概念をそのままカタカナで受け入れるしかありませんでした。「テーゼ」という言葉が翻訳されずに残ったのは、その抽象的なニュアンスをうまく言い換えることができなかったからです。
日本語への定着と翻訳の難しさ
「テーゼ」は「命題」「主張」と訳されることもありますが、どちらも微妙に違います。
「命題」は論理学的で、「主張」は感情的すぎる――その中間を埋める言葉がなかったのです。
結果として、「テーゼ」はそのままカタカナ語として日本語に溶け込みました。
この時代、「イデア」「ロゴス」「エゴ」など、カタカナでしか表現できない外来語が次々と登場しました。明治は、言葉の面でも“翻訳の限界”と格闘していた時代といえるでしょう。
雑学:ヘーゲルは本当に「三段論法」を唱えたのか?
実は、ヘーゲル自身は “Thesis–Antithesis–Synthesis” という定式を直接使っていません。
この三段階は後世の研究者が整理した便宜的なまとめであり、日本では「ヘーゲル=三段論法」として広まったのです。つまり、「テーゼ」「アンチテーゼ」「ジンテーゼ」という並びも、翻訳と受容の歴史の中で生まれた“日本的ヘーゲル像”なのです。
外来語が映す「ドイツに学んだ日本」
明治日本が学問のモデルとして選んだのは、イギリスでもフランスでもなくドイツでした。
オランダ語からドイツ語へ ― 学問言語の転換
江戸時代、ヨーロッパの知識は「蘭学」としてオランダ語経由で伝わっていました。
しかし明治期になると、学問の主流は一気にドイツ語へと移ります。
医学・法学・哲学――日本の「近代知」の多くがドイツ語から吸収されたのです。
「テーゼ」という言葉は、まさにその象徴といえるでしょう。言葉をたどると、そこに日本がどの国に学んできたかが見えてきます。
以下の記事では、オランダ語やドイツ語から日本語に取り入れられた外来語についても紹介しています。(ビール、ピンセット、テーマ、ゲレンデなど)
森鴎外とドイツ ― 文学・医学をつないだ橋
森鴎外もまた、ドイツに学んだ知識人の代表です。
彼はドイツ留学で医学を修め、脚気やペスト対策などに尽力しました。
鴎外の作品「舞姫」は、自身のドイツ留学の体験を基にした小説と言われています。
同時に、文学者としてもヨーロッパの思想を日本語で表現しようと試みました。彼の作品には、理性と情熱、個と社会といった対立を描く“弁証法的”な構造が見られます。
森鴎外は、日露戦争時には軍医総監として脚気の対応にあたり、最新医学を信じて疑わなかったため、結果として大勢の犠牲者を出すことになります。以下の記事では、海軍との比較や、日本で発見されたオリザニン(後のビタミン)の歴史について紹介しています。
言葉に歴史あり
「テーゼ」は単なるカタカナ語ではありません。
それは、明治日本がドイツに学び、西洋の思想を自らの言葉で理解しようとした努力の証です。外来語は時に違和感をもたらしますが、それこそが「学びの跡」です。
日本語の中に残る「テーゼ」という音は、近代日本が「考える国」へと変わろうとした、その響きの名残なのかもしれません。
関連記事:”かわいい”って何?
「かわいい」という身近な言葉は、近年では海外でも”Kawaii”として定着しつつあります。
英語のCuteとも違う「日本独特の感性」として言葉として広まることは、日本人としては誇らしいものでもありますが、その一方で、”かわいい”って具体的には何だろうという疑問も浮かんできます。
以下の記事では、歴史の中で変化してきた「かわいい」という言葉を、時代ごとにイラストを交えながら解説していますので、言葉の由来などに興味のある方は是非ご覧ください。