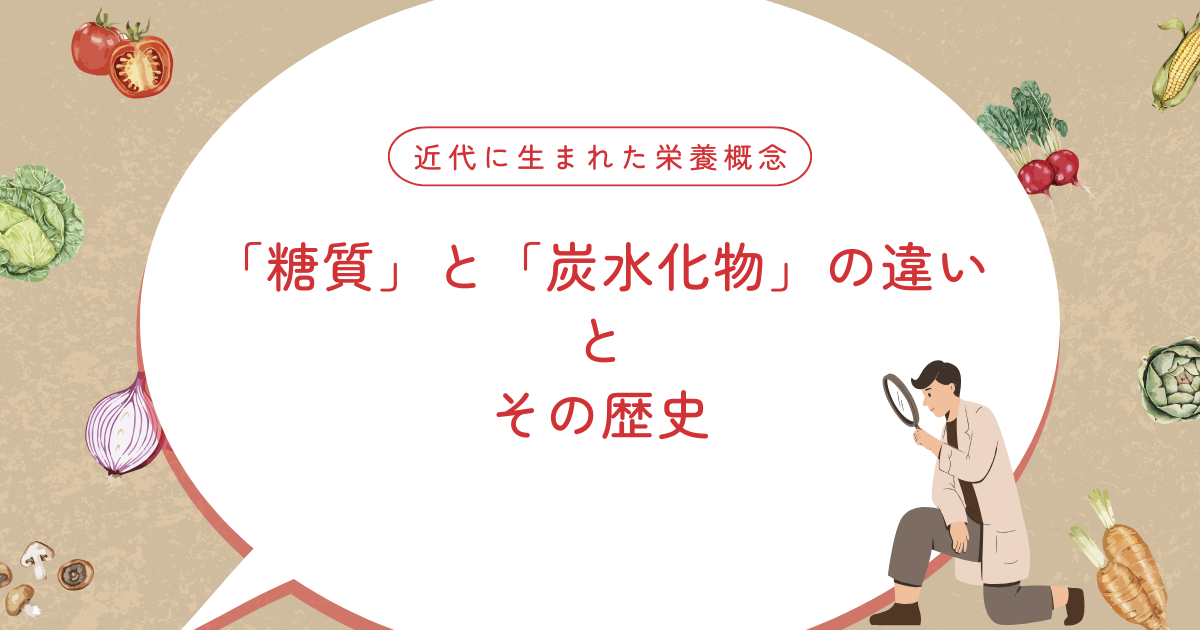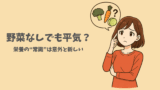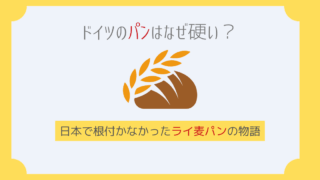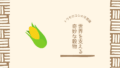私たちは当たり前のように「炭水化物」と「糖質」という言葉を使っていますが、その違いを明確に説明することは意外と難しいものです。
実は、この二つの概念は近代の栄養学の中で生まれました。白米と脚気、そしてビタミン発見の歴史をたどりながら、言葉の背景にある「身体と食の関係」を見ていきます。
「炭水化物」と「糖質」の違い
私たちが日常で使っている「炭水化物」と「糖質」という言葉は、似ているようで実は異なる概念を指しています。
まず、この二つの違いを確認することで、後に登場する歴史の流れが理解しやすくなります。
炭水化物 = 糖質 + 食物繊維
炭水化物とは、本来は糖・でんぷん・食物繊維などを含む、物質としての大きなグループを指す言葉です。その中で、体内でエネルギーとして利用される成分が「糖質」にあたります。
一方で、食物繊維はほとんどエネルギーになりません。しかし、腸内環境や血糖値の調整において重要な役割を果たします。
つまり、
- 炭水化物 = 糖質 + 食物繊維
- 糖質は炭水化物の一部分
という関係です。
なぜ「炭水化物=太る」と言われるのか
現代の食生活では、白米・白パン・菓子類・砂糖など、精製され、食物繊維がほとんど取り除かれた形の“糖質だけ”が多く摂られています。
そのため、炭水化物全体が「太る」というイメージを持たれがちですが、正しくは「糖質の質と摂り方」の問題です。
食品表示における「糖質」
食品成分表では、
糖質 = 炭水化物 − 食物繊維
という計算で示されています。
近代に生まれた「炭水化物」という言葉
「炭水化物」という言葉は、古代から使われてきたものではありません。
実は、この語の誕生は意外と新しく、19世紀の化学研究に由来します。
19世紀と聞くと少し距離を感じるかもしれませんが、日本史でいえば江戸時代の末期、ちょうどペリー来航の頃にあたります。
つまり「炭水化物」という言葉は、伝統的な食文化の中で長く使われてきた概念ではなく、近代科学によって新しく生まれた分類なのです。
19世紀以前:穀物は重要だったが「栄養」という考えはなかった
人類の食生活において、穀物は太古から主要なエネルギー源とされてきました。
しかし、「でんぷん」「糖」「繊維」といった分類はなく、それらがどのように体に作用するのかは理解されていませんでした。
1840年代:リービッヒが「炭水化物」と名付けた
19世紀に入り、化学分析が発展すると、糖やでんぷんの分子構造に共通点があることが明らかになります。
そこでドイツの化学者ユストゥス・フォン・リービッヒらによって、
Carbohydrate(炭素 + 水)=炭水化物
という分類が生まれました。
この時点では、炭水化物はあくまで「化学物質としてのまとまり」の名称にすぎませんでした。
「炭水化物だけ」が引き起こした病気
炭水化物は人類にとって欠かせないエネルギー源ですが、炭水化物だけでは生命を維持できないことが、近代に入って大きな問題として浮かび上がります。
白米の普及と脚気の蔓延
江戸時代後期、精米技術が発達すると、白く美しい「白米」が富や洗練の象徴として広まりました。しかし、精米によって糠に含まれるビタミンB1が取り除かれるため、白米中心の生活を続けた人々に脚気が多発します。
明治期に入ると、日本全体で脚気は深刻な国民病となり、多くの命が失われました。
森鴎外と高木兼寛:食と身体をめぐる対立
海軍は麦飯を導入することで脚気を克服しました。
しかし陸軍は「白米こそ文明的な食事」という価値観を重視し、白米中心の食事を続けました。その結果、陸軍では脚気が長期にわたり問題として残ります。
食の問題は、単なる栄養の問題ではなく、文化や価値観、国家の思想と深く結びついていたのです。
陸軍軍医総監「森鴎外」と、海軍軍医総監「高木兼寛」の脚気対策の違いとその結末については、以下の記事で詳しく解説しています。
当時の最新医学は「感染症=細菌」という視点が主流であり、まだ栄養学は現在のように体系化されていませんでした。その価値観の違いが、食と身体をめぐる判断の分岐を生みました。
脚気の克服が導いた「ビタミン」の発見
脚気の原因を追及する研究の中で、20世紀初頭、ビタミンB1(チアミン)が発見されます。
これにより、
炭水化物は、他の栄養素と“組み合わせて”はじめて身体を支える
という事実が明らかになります。
同じ炭水化物でも、含まれる栄養や食物繊維の有無によって作用が異なることがわかったのです。
日本人から始まるビタミンの発見 ― 鈴木梅太郎の研究
脚気の原因を追究する研究の中で、1910年、日本の研究者・鈴木梅太郎は、米ぬかから脚気を防ぐ成分を抽出し、これを「オリザニン」と名付けました。
これは、ちょうど日露戦争(1904~1905)後の時期にあたります。
当時の陸軍では白米中心の食事が続けられていたため、脚気による死者が多く、食と健康の関係が社会的な課題として強く認識されていました。
のちに同じ成分はヨーロッパの研究者によって「ビタミン」と呼ばれるようになり、脚気だけでなく、壊血病やペラグラなど、栄養欠乏による病気の理解を大きく進めることになります。
つまり、近代における「栄養」という考え方は、病気の原因を探りながら徐々に形作られていったということです。
関連記事:人々を苦しめた栄養欠乏による病気
このビタミンの発見は脚気だけでなく、壊血病やペラグラなど、栄養欠乏による病気の理解を大きく進めることになります。ビタミンがどのように発見され、なぜ「栄養の常識」が生まれたのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「糖質」という再分類の必然
こうした脚気や壊血病の研究を通して、20世紀の栄養学では「炭水化物」という分類の中に、役割の異なる成分が混在していることが明確になっていきました。
炭水化物には、身体のエネルギー源となる成分もあれば、ほとんど吸収されず消化の調整に関わる成分もあります。前者は生命活動のために欠かせない存在であり、後者は腸内環境を整え、血糖値の急上昇を防ぐ役割を持っています。
しかし、これらはどちらも同じ「炭水化物」という一語でまとめられていました。
そこで、炭水化物の中でも“身体が利用できるエネルギー源となる部分”を切り出して表すために、後から導入された概念が「糖質」です。
つまり「糖質」という言葉は、単なる新しい呼び方ではなく、
炭水化物の中身をより正確に理解しようとした結果、生まれた再分類の言葉なのです。
炭水化物は化学の言葉であり、糖質は栄養の言葉である。
その誕生には、食と病気を通して人間が学んだ長い歴史があるのです。
本記事のまとめ
- 「炭水化物」は19世紀に化学の中で生まれた言葉です。
- 「糖質」は炭水化物の中で、エネルギーとして利用される部分を示す、より新しい言葉です。
- この再分類の背景には、白米と脚気、そしてビタミンB1の発見という歴史上の出来事がありました。
- 炭水化物は、単なるエネルギー源ではなく、人類の文化と社会を形づくってきた根源的な食べ物でもあります。
炭水化物を理解することは、私たち人間が、「何を食べて生きてきたのか」を理解することでもあるのです。
炭水化物や食べ物に関する以下の記事も、是非あわせてご覧ください。