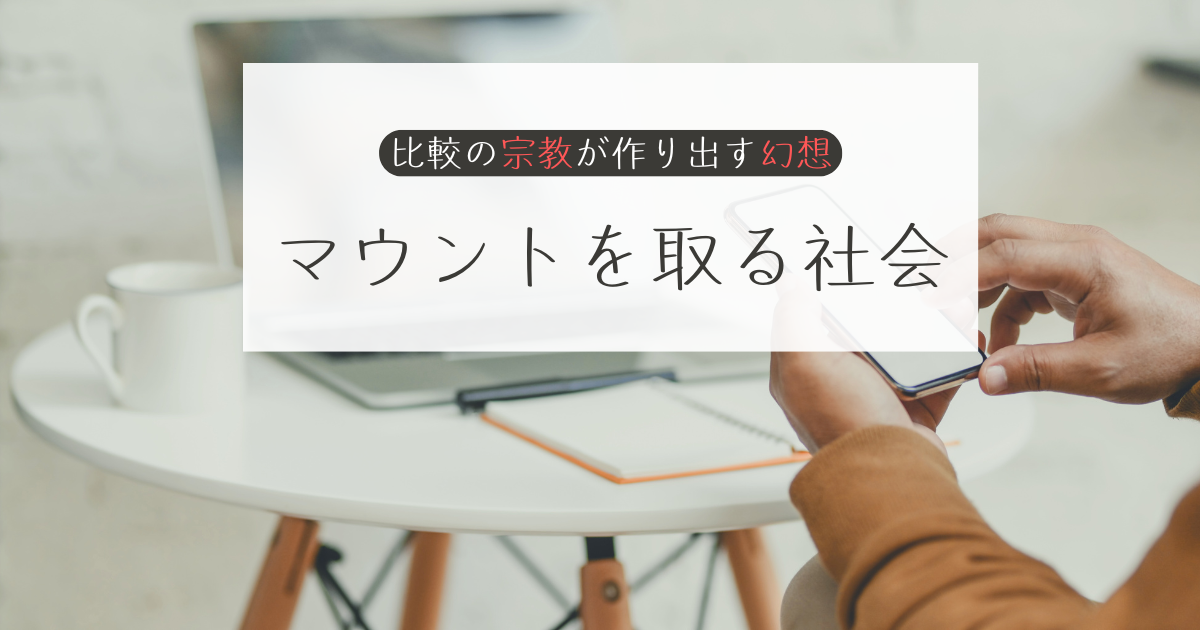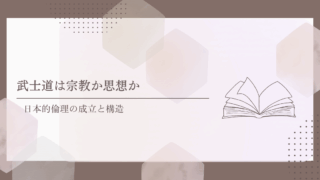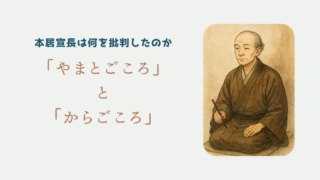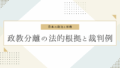「マウントを取る」という言葉が、日常の中にすっかり定着しました。
職場でもSNSでも、他人より優れていることを示したり、相手を下に見るような態度を指して、よく使われます。
「他人より上に立ちたい」と感じる社会。
その背景には、儒教的な“比較の宗教”が現代まで根を張っています。
私たちはなぜ、終わりのない競争に苦しみ続けるのか――。
その幻想を解きほぐし、自由になるための視点を探ります。
「マウントを取る」とは ― 優越を示す行為の背景
マウントという言葉は、本来は格闘技で「上に乗る姿勢(マウントポジション)」を意味します。
そこから派生して、他人より上に立ちたいという心理的な行動を指す比喩として広まりました。
たとえば、年収や学歴、恋人、容姿、フォロワー数といったあらゆる要素を使い、「自分の方が上だ」とアピールする。
それが、現代のマウント行動です。
こうした行為は、SNSの普及によってより顕著になりました。
自分の生活や成果を他人に見せることで、「承認」を得るはずが、いつの間にか「比較」に変わっていく。そして、人々は他者の投稿に「負けた」と感じ、焦燥や劣等感を抱くようになります。
この構造は偶然ではなく、私たちの社会そのものが「比較によって秩序を作る」仕組みを内面化しているからです。
儒教的価値観が作り出した序列の社会
東アジア社会、とりわけ日本や韓国、中国の文化には、儒教の影響が深く根付いています。
儒教は、道徳と秩序を重んじる思想として社会の根幹を支えてきました。
人は努力によって徳を積み、地位を上げ、上の者は下を導き、下の者は上に従う。
そうした上下関係を「正しい」とする教えが、長い年月をかけて社会の隅々にまで浸透しました。
儒教の作り出す「勝ち組」「負け組」
この考え方は、一定の秩序を保つためには有効でした。
しかし同時に、「上に立つことが善」「下にいることは未熟」といった価値観を生み出します。
その結果、人々は絶えず他者と比較し、上を目指さなければならないという無意識のプレッシャーを抱えるようになりました。
これは、努力や競争を肯定する社会的原理となり、現代にまで残っています。
韓国では過酷な受験競争が社会問題化し、日本では「勝ち組」「負け組」という言葉が定着しました。
この構造は、まさに儒教的な序列社会の延長線上にあると言えるでしょう。
上に立つことが善であるという信念――それこそが、「マウント社会」を支える見えない宗教的信仰なのです。
比較の宗教 ― 現代に息づく“信仰”
ここで言う「宗教」とは、信仰対象を持つ特定の宗教ではなく、社会の中で“当然の前提”として受け入れられている思想体系を指します。
つまり、「他者より優れていなければならない」「上に立つことが正しい」という信念が、現代の人々の無意識を支配しているのです。
信仰が生み出す苦しみ ― 努力が足りない
この比較の宗教は、儒教から発展し、近代以降の“努力信仰”とも結びつきました。
「努力すれば報われる」「頑張れば上に行ける」という考えは、一見ポジティブに見えますが、
裏を返せば「報われない人は努力が足りない」という責めにもつながります。
それがやがて、「マウントを取られる側」の苦しみとして現れます。
こうして、社会全体が終わりのない比較の輪の中で回り続けるのです。
「マウントを取る」という幻想
他者よりも優位に立つことが良いことで、劣位に立たされることを悪い事とする価値観は、儒教という宗教に由来する「一つの考え方」でしかありません。
マウントを取ることで満たされたり、マウントを取られて悔しいという気持ちは、絶対的な真理からくるものではなく、宗教が作り出した「幻想」でしかないのです。
優越のために必要な「比較対象」
他者にマウントを取って優越を感じるためには、比較対象となる劣位の存在が必要です。
年収が高い事や、フォロワー数が多い事などで優越を感じるためには、自分よりもそのステータスが低い人間が必要になります。
マウントを取る人は、儒教的価値観によって「自分が優位に立つことで幸福を感じる」のです。
しかしこれは同時に、自分が劣位に立たされる価値観でもあります。
年収でマウントを取ることで幸福を感じる人は、年収でマウントを取られることで不幸を感じる事でしょう。そのステータスで最上位にならない限り、この苦しみは続くことになります。
そして努力の果てに得られた優越は、「比較対象がいない」状況下では得られません。
蔑む相手がいて初めて愉悦を感じられる――これがマウントを取る行為の幻想たる所以です。
自分が良ければ「それでいい」
他人と比較して、努力して上を目指す儒教的価値観は、組織運営や社会発展においては都合の良いことも多く、かつて日本も教育勅語などで国民の努力を奨励し、上下関係を重視する国づくりを進めてきました。
しかし、人は組織や国家のために生きているのではありません。
人の幸福とは、本来他人と比較して得るものではないでしょう。
人に「マウントを取る」ことなく幸福を感じられるものは、それは幻想ではなく、間違いなくあなた自身の幸福でしょう。
自分が良ければ「それでいい」のです。
日本は信教の自由を保証している国です。他者の宗教は最大限尊重しましょう。
比較の宗教で得られる幻想的幸福ではなく、自分の幸福を大事にする生き方をしていれば、マウントを取る人の行動もまた違って見えるのではないでしょうか。
間違っても、比較の宗教を蔑んではいけません。
それはまた、儒教的価値観による「マウントを取る」ことと同じなのです。
人は人、自分は自分です。
関連記事:日本に根づいた儒教思想をたどる
現代社会の価値観の根底にある儒教思想は、特に江戸時代の日本で国家の基盤として体系化されました。江戸幕府が「朱子学」を奨励したことで、広く日本人の道徳として浸透します。
儒教がどのように日本の思想へと根づいていったのか、関心のある方は是非以下の記事もご覧ください。