日本の江戸時代。幕府の政策・制度や庶民文化や学問など、近世日本の社会に関連したものを扱います。
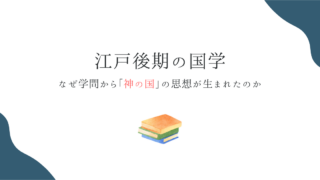 思想
思想 江戸後期の国学 ― なぜ学問から「神の国」の思想が生まれたのか
江戸後期の国学は、なぜ「神国日本」という思想に至ったのか。江戸中期国学の方法論、平田篤胤の思想と時代背景を手がかりに、学問が思想へと変化した過程を整理します。
 思想
思想 江戸中期の国学 ― 全てを理屈で説明できるのか
国学というと尊王思想や愛国主義を連想しがちですが、その始まりは人の心の動きを見つめ直す学びでした。江戸中期の国学を、契沖・賀茂真淵・本居宣長の思想の流れから読み解きます。
 思想
思想 江戸中期の陽明学 ― なぜ社会は良くならないのか
江戸時代、朱子学が広がる社会の中で「なぜ正しさが行き届かないのか」という違和感が生まれました。本記事では、江戸中期に陽明学がどのように受容され、社会や思想の中でどのような意味を持ったのかを読み解きます。
 言語
言語 意外と新しい「宗教」という言葉・概念 ― religionの翻訳史
宗教という言葉は、実は近代日本で西洋の religion を翻訳する中で再定義された概念でした。語の歴史から、日本人の宗教観と現代的な違和感を考えます。
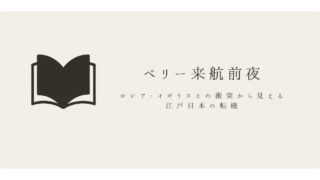 歴史
歴史 ペリー来航前夜 ― ロシア・イギリスとの衝突から見える江戸日本の転機
ペリー来航以前、日本はすでにロシアやイギリスと接触し、外圧を経験していました。衝突の歴史とその影響を通して、江戸後期日本が迎えつつあった転機を整理します。
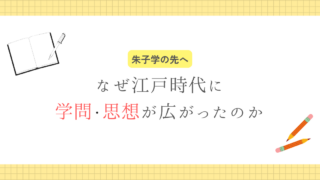 思想
思想 なぜ江戸時代に学問・思想が広がったのか ― 朱子学の先へ
江戸時代には、朱子学を基盤としながらも多様な学問・思想が広がっていきました。朱子学の成功とその限界、識字率や出版文化の発達から、その背景を読み解きます。
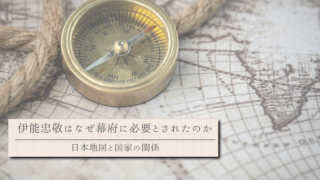 歴史
歴史 伊能忠敬はなぜ幕府に必要とされたのか ― 日本地図と国家の関係
伊能忠敬は、なぜ幕府に必要とされたのでしょうか。私的な学問として始まった測量が、国家事業へと転化し、日本列島の見え方を変えた背景を解説します。
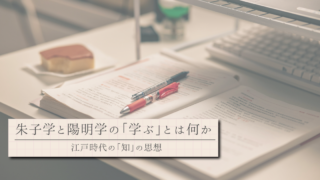 思想
思想 朱子学と陽明学の「学ぶ」とは何か ― 江戸時代の「知」の思想
朱子学と陽明学は、「知」や「学び」をどう捉えていたのか。格物致知・心即理・知行合一を手がかりに、江戸時代の学問観と「学ぶとは何か」を読み解きます。
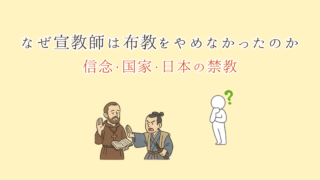 歴史
歴史 なぜ宣教師は布教をやめなかったのか ― 信念・国家・日本の禁教
江戸幕府の禁教下で宣教師たちはなぜ布教を続けたのか。救済の信念、国家の制度、国際情勢、そして日本との価値観のすれ違い──善悪を超えて、その行動の背景構造を読み解きます。
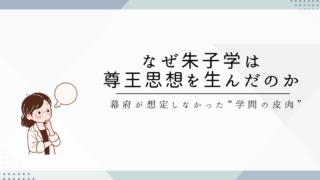 思想
思想 なぜ朱子学は尊王思想を生んだのか ― 幕府が想定しなかった“学問の皮肉”
幕府が奨励した朱子学は、理を追究するほど忠の正統性を問い直し、やがて垂加神道や水戸学を通じて尊王思想へとつながりました。学問が権威を揺るがす“皮肉な構造”を読み解きます。