私たちの常識へと昇華している宗教由来の思想を紐解いたり、海外の宗教の考え方を学ぶことで、自分の常識が「普遍の真理」ではないことを再認識します。
また、宗教に関連した歴史上の出来事についても扱います。
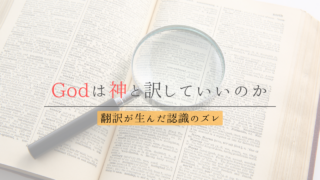 言語
言語 Godは神と訳していいのか ― 翻訳が生んだ認識のズレ
Godはなぜ日本語で「神」と訳されたのか。その翻訳の背景と、英語と日本語における「神」の捉え方の違いから、言葉が生んだ認識のズレを整理します。
 言語
言語 divineとsacredの違い ― 「神聖な」にまとめてしまう日本語の感覚
divineとsacredの違いを、辞書的な意味だけでなく英語話者のニュアンスから整理します。言葉の違いを手がかりに、文化や宗教観の背景にも目を向けてみます。
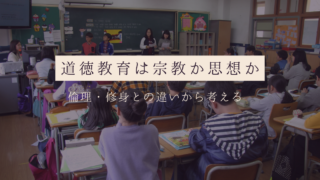 社会
社会 道徳教育は宗教か思想か ― 倫理・修身との違いから考える
道徳教育は宗教や思想なのか。それとも社会に必要な教育なのか。倫理・修身との違いや、憲法が保障する思想の自由との関係から、道徳教育の位置づけを冷静に考えます。
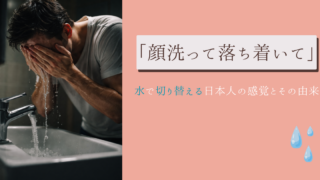 思想
思想 「顔洗って落ち着いて」― 水で切り替える日本人の感覚とその由来
感情が乱れたとき、日本人はなぜ水で気持ちを切り替えるのでしょうか。禊に通じる神道的な発想と、顔を洗う・風呂に入るといった日常習慣の由来を、海外との違いも交えて解説します。
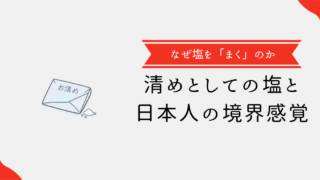 思想
思想 なぜ塩を「まく」のか ― 清めとしての塩と、日本人の境界感覚
葬儀の後に塩をまくのはなぜか。清めとされる塩の意味や、「まく」という行為が持つ役割を、境界という視点から読み解きます。
 言語
言語 意外と新しい「宗教」という言葉・概念 ― religionの翻訳史
宗教という言葉は、実は近代日本で西洋の religion を翻訳する中で再定義された概念でした。語の歴史から、日本人の宗教観と現代的な違和感を考えます。
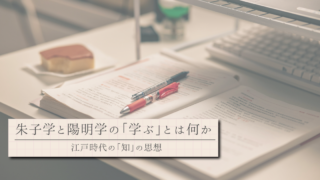 思想
思想 朱子学と陽明学の「学ぶ」とは何か ― 江戸時代の「知」の思想
朱子学と陽明学は、「知」や「学び」をどう捉えていたのか。格物致知・心即理・知行合一を手がかりに、江戸時代の学問観と「学ぶとは何か」を読み解きます。
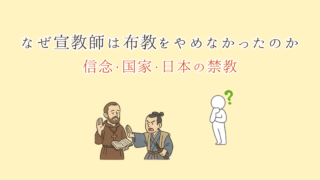 歴史
歴史 なぜ宣教師は布教をやめなかったのか ― 信念・国家・日本の禁教
江戸幕府の禁教下で宣教師たちはなぜ布教を続けたのか。救済の信念、国家の制度、国際情勢、そして日本との価値観のすれ違い──善悪を超えて、その行動の背景構造を読み解きます。
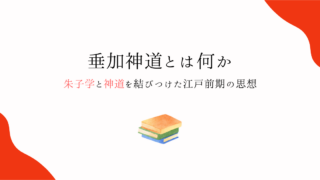 思想
思想 垂加神道とは何か ― 朱子学と神道を結びつけた江戸前期の思想
江戸時代初期に山崎闇斎が説いた垂加神道は、朱子学と神道を結びつけた独自の思想です。その成立背景や特徴、後の水戸学・尊王思想との関係をわかりやすく解説します。
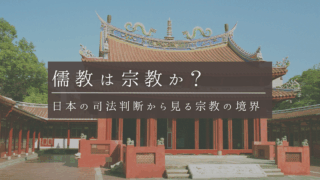 思想
思想 儒教は宗教か? 日本の司法判断から見る宗教の境界
儒教は宗教と言えるのでしょうか? 日本では「儒教の宗教性」が司法判断の対象となった孔子廟訴訟の判決がありました。本記事では、憲法20条の政教分離の観点から、儒教と宗教の境界を分かりやすく解説します。