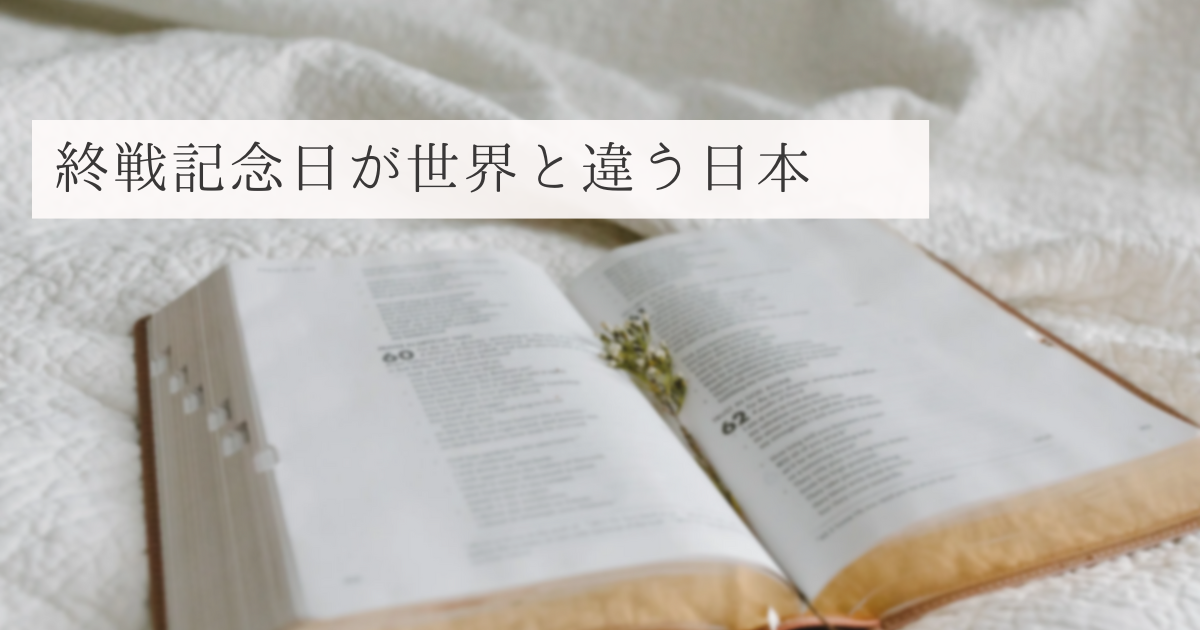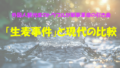日本の過去の歴史について話をしている際に、「ペリーっていい人じゃないの?」と突然聞かれたことがあります。かなり前の出来事ですが、あまりの衝撃に今も忘れることが出来ずにいます。
学校教育の過程などでは、ペリーが日本にやって来たという事実を強烈に印象付け、歴史的な意味があまり正確には伝わらないのかもしれません。私自身も子供の頃はペリーとザビエルを間違えていたような気もします。
今回は、ペリー提督というアメリカの軍人が何をしに日本に来て、それは日本にとって良かったことなのか、彼はいい人だったのかを改めて考えてみたいと思います。
ペリー来航という出来事
ペリーという人は、1853年に浦賀に現れたアメリカの軍艦・通称黒船に乗っていた提督です。

ペリーの目的 – 軍事力による「開港」
ペリーの目的は日本の港を開港させることにありました。この当時のアメリカは、日本の近海まで鯨(くじら)などの漁をしに来ていましたが、その際に遭難する事故などもあり、運良く日本人に救われたりもしていました。そのため、アメリカとしては日本の港を利用することが出来れば、事故の予防や遠征地での補給など、多くのメリットがありました。
彼らは黒船から大砲を放って威嚇し、強大な軍事力を喧伝することで、日本に対して開港の承諾を迫りました。
この軍事力によって圧力をかける外交を「砲艦外交」と呼び、覇権争いをしていた欧米諸国が1800年代くらいから行うようになっていました。
文明レベルが遅れていた日本 ― 電気のある世界とない世界
当時の日本は江戸時代で質素倹約の時代です。武器は主に刀や槍で、遠隔武器は弓と火縄銃といった時代です。
対して欧米諸国は産業革命を終えて急速に発展している文明社会で、工場で大量に製品が生み出されていた時代です。
この頃のアメリカでは、電気の活用が進められ始め、まさに新世界と呼べるほどに別次元の文明へと進化しつつありました。日本は強大な道の文明の前に成す術もなく、選択の余地はありませんでした。
当時のアメリカについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
不平等条約の締結
翌年(1854年)に再度訪れたペリーとの間には、日本のいくつかの港を開港するという内容が含まれた、表向き平和な日米和親条約という約束を交わすことになります。その後日米修好通商条約のような「不平等条約」を、欧米列強諸国と締結させられることとなります。
同様の不平等条約をアメリカ、フランス、イギリス、ロシア、オランダの計五か国と締結しており、これらは総称して「安政の五か国条約」と呼ばれます。
不平等条約は江戸時代だけでなく、明治時代にも追加で様々な国と締結します。
その背景については以下の記事で紹介しています。
💡関連記事:オーストリアやスイスとも? ― 明治に結んだ追加の不平等条約
アジアにおける欧米諸国の勢力圏
この頃の欧米諸国は、大航海時代~産業革命を終えた後で、大量に作られるようになった製品を売りつける海外市場を求めて、植民地の獲得競争が行われていた時代です。
この時代のアジア諸国の勢力圏がまとめられた素敵な地図がありますので、ここで紹介します。
(明治時代に入ってからの地図のため、日本は台湾と韓国を領有しています。)

今も存在するアジアの国家としては、日本とタイしか記されていないことは、特に衝撃的なのではないでしょうか。
清国の敗戦で焦る日本 – アヘン戦争
アヘン戦争は1840-1842年にイギリスと清(中国)との間で起きた戦争です。
結果は近代兵器を持っているイギリスの圧勝でしたが、日本は特に関与していません。しかし、当時の日本からすると、お隣の巨大国家である清国がヨーロッパの国に成す術もなくやられたという報せは衝撃的だったでしょう。
アヘン戦争は、ペリーが日本に来航する約10年前の出来事です。日本の未来を考える有識者(吉田松陰など)の中には、この報せを聞いて「日本も将来危ないかも」と危機感を募らせたといわれます。
ペリーが日本に来る以前から、日本国内では「外国勢力に対する懸念」というものが存在していましたが、ペリー来航によって日本人が団結し、突き動かされていったとも言えるでしょう。
ペリー来航は日本の人々を驚かせたと言われています。一方で、幕府はこの事を知っていたと、近年の教科書などでは書き換えが進んでいるようです。友好関係にあったオランダが江戸幕府に情報を提供していました。
江戸時代の日本とオランダの関係については、以下の記事で詳しく紹介しています。
💡関連記事:なぜオランダだけ?江戸時代の鎖国と日蘭関係の歴史
ペリー来航後の日本
ペリーが日本に来航した後の日本は「激動の時代」を迎えていきます。
高まる幕府批判と外国勢力の排除(尊王攘夷運動)
強大な軍事力を持って脅されたうえ、幕府は天皇の許可を得ずに不平等条約に調印したため、「幕府批判」や「外国勢力の排除」という動きが活発化します。
ペリー来航の50年ほど前に、本居宣長の手によって「古事記」が解読されています。
多くの庶民が知らなかった「天皇」や「日本の創世神話」が広く知られ、日本の歴史を「大日本史」として編纂していた水戸藩の「水戸学」にも大きな影響を与えます。
水戸藩の過激派は、天皇の許可なく不平等条約を調印した井伊直弼を桜田門で襲撃します。
ペリー来航で改元され、井伊直弼が亡くなったことで終わる「安政」という時代は、幕末の前半期にあたり、以降は更に混沌とした時代を迎えます。
今回はあまり触れませんが、ペリー来航後には令和の時代にも話題になることが多い「南海トラフ地震」が起こっており、度重なる余震で不安な日々が続きました。
幕末の地震については以下の記事で詳しく紹介しています。
💡関連記事:南海トラフ地震とペリー来航 – 「安政」という皮肉な元号
15年の歳月 ― ペリー来航から明治維新まで
ペリーが日本の浦賀に来たのが1853年で、日本が江戸幕府を倒して明治政府を樹立した(明治維新)のが1868年です。
その間には「15年」しか歳月が流れていません。
義務教育過程などで歴史を学んだ際には、記号的にこの年号を覚えたものですが、大人になってから改めてこの15年の歳月の事を考えると、非常に短いと感じるものです。
日本政府である江戸幕府を武力で打倒して、新しい国を作ろうというのですから、これは一般的にはクーデターと呼ばれる行為ですが、その後に国の制度自体を完全に作り替えたことから、明治維新は一般的には「軍事革命」に分類されることが多いようです。
幕末の動乱については、以下の記事で流れを詳しく解説しています。
「ペリー来航」を真似た日本の末路
急速な発展をしていく日本国内では、朝鮮半島への進出(征韓論)について政府内で意見が割れてしまい、その結果分断・内乱になってしまいました。(西南戦争)
ペリー来航と同じ手口「砲艦外交」によって、「朝鮮の(清からの)独立」を推し進めていきますが、この事は清国との軋轢を強め、結果として日清戦争という軍事衝突を招きました。その後は戦争の結果が次の戦争に繋がっていき、最終的に日本は大東亜戦争に敗戦する結末を迎えます。
問われる「日本が戦争をした理由」― 東京裁判
敗戦した日本では、戦争犯罪者を裁くための「東京裁判」が行われました。この裁判では、日本の戦争を指導した政治家や軍人が多く裁かれたことが知られています。
東京裁判では、事実関係を明らかにするために多くの人が証言をしています。
中でも印象的なのは、満州国の溥儀(ふぎ)や日本の軍人である石原莞爾(いしわらかんじ)が証言台にたっていたことです。
「ペリーを連れてこい!」 ― 石原莞爾
東京裁判について、本件とも関連していて、とても分かりやすくまとめられている動画を一本紹介します。
この動画では、東京裁判で戦犯とされた各区分の解説や、裁判の内容、そして犯罪者とされた人たちのその後などが詳しく、そして分かりやすく解説されています。
サムネイルにもありますが、石原莞爾が証言台に立った際に、
戦争犯罪を遡って裁くのであればペリーを連れてこい
と証言したことが紹介されています。
ペリーが日本に来航していなければ、日本は戦争へ歩んでいくことはなかったかもしれません。
正しい歴史教育の必要性
ペリー来航という出来事は、ペリー個人の判断で行われたものではありません。
欧米列強国と呼ばれる国の、政治的な判断によって引き起こされた当時の外交に他なりません。
しかし、ペリー来航は「当時の日本にとって」良い出来事ではなかったでしょう。
軍事力によって他国の主権を奪うような外交は、現代の国際社会では許されません。
幼い子供に正しい歴史を教えることは難しい事でしょう。
しかし、ペリー来航が良い出来事で、「ペリーはいい人」といったイメージがつくような教育は、改善すべき点があるように思えてなりません。
関連記事:尊王攘夷思想に至るまで
本記事でも登場した「尊王攘夷」思想。
江戸時代を終わらせ、明治維新を成し遂げるに至った思想が、どのように形作られて行ったのかを、以下の特集記事でまとめています。
学問・思想の観点から詳しく解説していますので、関心のある方は是非ご覧ください。


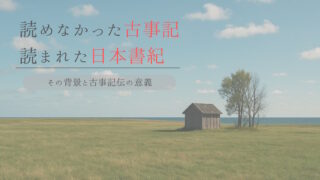


-160x90.png)