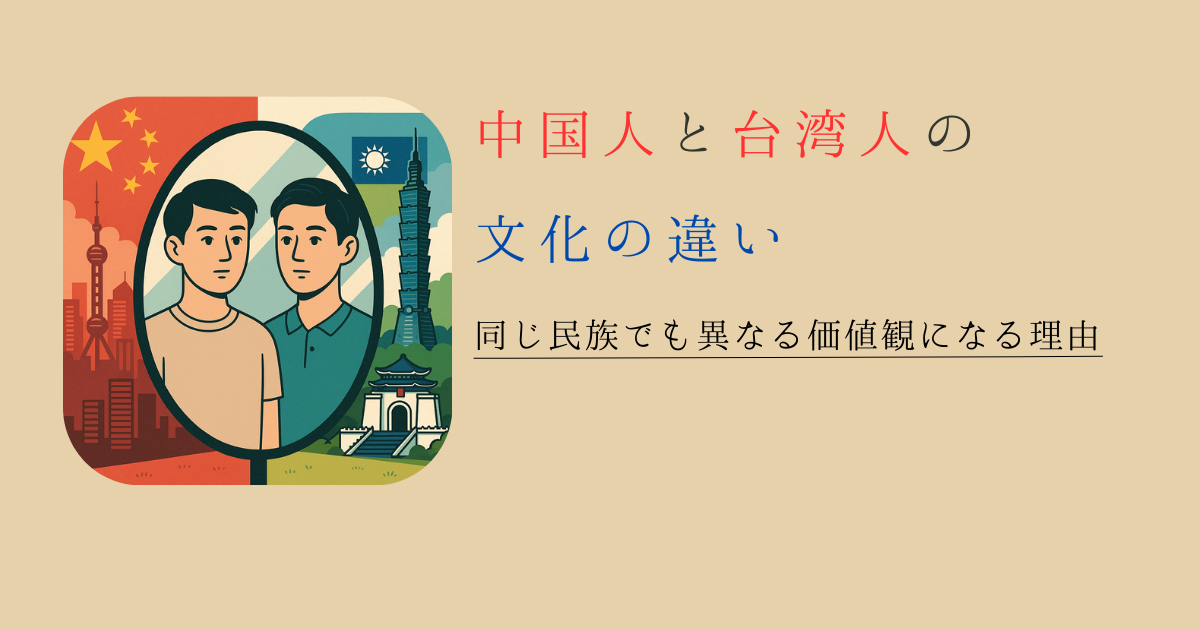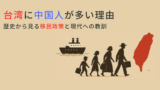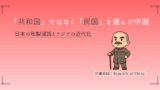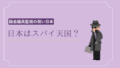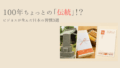日本に住む私たちから見れば、中国と台湾の人々はどちらも同じ「漢民族系」で、外見や言語も似ているように映ります。しかし実際には、旅行者や留学生との交流、あるいは観光地でのエピソードを通して、文化や価値観の違いを感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
例えば、奈良公園の鹿に対する観光客の接し方を見ても、中国本土出身の観光客と台湾出身の観光客には行動やマナーの違いが見られるという声があります。なぜ同じ民族でありながら、こうした違いが生まれたのでしょうか。
この記事では、歴史や教育、社会制度の背景をたどりながら、中国と台湾の文化的な違いを読み解いていきます。
奈良の鹿が映す観光客マナーの差
奈良公園の鹿は、日本の観光地の象徴的な存在です。しかし近年、鹿に対する不適切な接し方や暴力行為が問題となり、ニュースやSNSで話題になったことがあります。
YouTuber出身の政治家「へずまりゅう」氏が、鹿を守る活動を行い注目を集めたことも記憶に新しいでしょう。(2025年7月の奈良市議選で3位当選)

この問題は一部の観光客による行為に過ぎませんが、「どこの国の観光客か」という議論に発展し、中国本土からの旅行者によるマナー違反が指摘されることもありました。一方、台湾からの旅行者には比較的落ち着いた行動が目立つという声もあります。もちろん、国籍で一括りに評価するのは危険です。しかしこのような違いは、歴史や教育の背景を知ると理解しやすくなります。
台湾独自の価値観を育んだ歴史背景
中国と台湾の人々はどちらも漢民族系でありながら、その価値観や社会意識には違いがあります。
その背景を理解するためには、台湾の歴史を振り返り、どのように独自の文化や社会観が形成されてきたのかを見ていく必要があります。
台湾が漢民族社会になった経緯
台湾はもともと先住民族が暮らす島でした。
17世紀、オランダやスペインが一時期占領し、その後、明朝の遺臣・鄭成功が拠点を築いたことで漢民族の移民が増えました。さらに清朝時代には福建省や広東省からの移民が本格化し、台湾は中国本土の沿岸文化を受け継ぐ島となります。
この時期の台湾は、中国本土の一地方のような存在であり、住民の価値観や生活様式も本土南部の農村文化と深く結びついていました。つまり、台湾社会の基礎には古くからの漢民族文化が根付いていたのです。
台湾への移民については、以下の記事で詳しく紹介しています。興味のある方は是非こちらもご覧ください。
日本統治がもたらした公共意識
1895年、日清戦争の結果、台湾は日本の統治下に入りました。
日本政府は台湾を植民地としてインフラ整備や教育制度の導入を進め、鉄道や上下水道、学校などを整備しました。この時代に台湾では衛生観念や公共インフラの利用ルールが広まり、都市部を中心に「公共意識」が根付いていきます。
この経験は戦後も台湾社会に影響を残し、公共の場でのマナーや秩序を大切にする文化形成に寄与したと指摘されています。

日本統治時代に建設された建築物で、現在は台湾の総統府として使用されている
一方で、中国本土は清朝崩壊後に戦乱期を経て共産党政権が成立するなど、政治的混乱が続き、公共意識の形成には別の歴史をたどることになりました。
戦後の社会体制の違い
第二次世界大戦後、台湾は中華民国政府のもとで戒厳令体制に入りましたが、1980年代以降は急速に民主化が進みました。言論の自由や多元的な価値観を尊重する社会が形成され、教育やメディアを通じて多様な意見に触れることができる環境が整っています。
一方の中国本土では、1949年に成立した中華人民共和国のもとで社会主義体制が確立され、国家が人々の価値観や思想に強く影響を与える構造が続いています。このような社会体制の違いが、現代の中国と台湾の文化的差異を生み出す土台となっています。
以下に、中国と台湾の社会体制について比較してみます。
| 項目 | 中国本土(中華人民共和国) | 台湾(中華民国) |
|---|---|---|
| 成立年 | 1949年(共産党政権樹立) | 1945年以降、中華民国政府が台湾を統治 |
| 政治体制 | 共産党一党独裁 | 戒厳令期を経て1980年代以降民主化 |
| 選挙制度 | 実質なし(党主導) | 自由選挙(総統・議会ともに直接選挙) |
| 国際的な立場 | 国連常任理事国 国家承認多数 | 国連非加盟 限定的な外交承認 |
雑学:共和国と民国 – 中国の国号と和製漢語
中華人民共和国という国号に使われている「人民」と「共和国」は、どちらも日本で作られた「和製漢語」です。一方、中華民国に使われている「民国」は、和製漢語ではありません。
以下の記事では、アジアの近代化に役立てられた日本の和製漢語と、中華民国に「民国」という言葉が使われた背景を解説しています。興味のある方は是非ご覧ください。
なぜ台湾は国連非加盟なのか:歴史と日本の対応
台湾は実質的に独自の政府と民主主義体制を持つにもかかわらず、国連に加盟していません。
その背景には、1971年の国連総会決議2758号(通称アルバニア決議)があります。
この決議により、国連は「中国の唯一の代表権」を中華人民共和国に付与し、中華民国(台湾)の議席を失いました。以降、国連加盟国の大多数は「一つの中国」政策を採用し、台湾を正式な国家として承認していません。
この「アルバニア決議」は、賛成76・反対35・棄権17で採択され、日本は棄権票を投じました。(「アルバニア決議」という呼称は、アルバニアが提案国の一つであったことに由来)
当時の日本は中国との国交正常化前で、米国寄りの立場を維持しつつも、国際情勢の変化を見極めようとした結果、棄権票を投じるという形になりました。この決議によって台湾は国連の議席を失い、以後加盟が認められていません。
現在の日本も外交方針として「中華人民共和国を唯一の中国と認める立場」をとっています。ただし、台湾との間では実務的な外交・経済関係を深めており、事実上は非常に密接なパートナーです。
こうした国際関係の背景は、台湾の独自性や価値観を理解するうえで重要な要素です。表面上は国連加盟国ではない台湾ですが、経済力や民主主義体制、国際的な影響力は非常に大きく、日本との関係も緊密さを増しています。
台湾は孤立していない:承認国と交流ネットワーク
台湾は国連に加盟していないものの、2024年時点で13か国が正式に台湾を国家として承認しています。これらの国々とは正式な外交関係を結び、大使館に相当する「駐在機関」を置いています。
一方で、米国や日本、EU諸国など多くの国は「一つの中国」政策を踏まえ、台湾を正式な国家としては承認していません。しかし実際には、「台北駐日経済文化代表処」や「米国在台協会(AIT)」のような機関を通じて、実質的な大使館機能を持った外交関係を維持しています。
このように台湾は、国連非加盟であっても、国際的に経済・文化・安全保障などの面で重要な役割を果たしており、完全な孤立状態ではないことがわかります。
教育と社会制度が形づくる価値観の違い
台湾と中国本土の人々が異なる価値観を持つようになった背景には、歴史だけでなく現代の教育や社会制度のあり方も大きく関わっています。
それぞれの国や地域で、どのような教育方針や社会システムが価値観の形成に影響しているのかを見ていきましょう。
教育と価値観形成の違い
社会体制の違いは教育方針にも大きく影響しました。台湾では民主化以降、歴史教育も多角的な視点を重視するようになり、日本統治時代を含めて客観的な議論がなされやすい土壌が育まれました。近年は台湾人の若者の中に、日本文化への親しみや歴史的な関係の理解が比較的広まっています。
一方、中国本土では、近代史の授業で戦争や侵略の歴史を強調する傾向があり、これは国家統合のためのナショナリズム教育の一環ともいわれます。こうした教育は人々の国際感情や外国への印象にも影響を及ぼし、日本に対する歴史認識の違いを形作る要因の一つになっています。
| 項目 | 台湾 | 中国本土 |
|---|---|---|
| 政治体制 | 民主主義(自由選挙) | 共産党一党体制 |
| 教育方針の特徴 | 多様な価値観を尊重、討論型授業も多い | 国家観・集団意識を重視、記憶中心の教育 |
| 歴史教育の内容 | 中国史・台湾史を幅広く扱い、国際関係史も比較的客観的 | 近代史・戦争被害を強調し、愛国教育に重点 |
| 言論・報道環境 | 表現の自由が保障され、異なる意見が表に出やすい | 政府の管理が強く、言論空間が制限されやすい |
| 価値観形成の傾向 | 個人の自由や多様性を重視 | 集団や国家の利益を優先しやすい |
| 国際感覚 | 民主主義国との交流が盛ん、アジア・欧米志向も強い | 自国中心の視点が強く、国家主導の情報が多い |
台湾と日本に見られる文化・教育の共通点
現代の台湾と日本には、「表現の自由」や「教育方針」において共通する価値観が多く見られます。
どちらの社会も民主主義を基盤とし、異なる意見を持つことや議論することが比較的自由に許される環境が整っています。こうした環境は、国民一人ひとりの価値観や判断力を育てる土壌となっています。

教育面でも、日本と台湾は多様性を尊重する傾向が強く、歴史教育でも複数の視点を取り入れる工夫がなされています。たとえば、台湾では台湾史や国際関係史を幅広く扱い、日本でも国内外の歴史を多角的に学ぶ機会があります。
両国とも「一つの価値観を押しつける」のではなく、考える力を養うことを大切にしています。
このような環境の共通点は、単に文化的な親近感を生むだけでなく、社会全体の寛容さや議論のしやすさにつながっています。結果として、日本人が台湾社会を「近い」と感じるのは自然なことだと言えるでしょう。
「文化差」を国籍で単純化しないために
奈良の鹿の事例に見られるような観光客マナーの違いは、単なる個人の資質の問題ではなく、歴史や教育、社会背景が複雑に絡み合った結果です。
「中国人はマナーが悪い」「台湾人は優しい」といった単純化したイメージは、現実を誤解させかねません。
むしろ、そうした違いが生まれる背景を理解することで、国際交流や観光地でのトラブルを冷静に捉えられるようになります。
同じ民族や言語圏でも、社会体制や教育が異なれば価値観が変わる――これは台湾と中国の違いだけでなく、世界中で見られる普遍的な現象です。
日本でも、近代化の過程で大きな価値観の変化が起こりました。人は社会体制や教育で簡単に価値観を変化させてしまいます。以下の記事では、日本でも「女性の裸を性的だ」と考えるようになった歴史的背景について解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
違いの背景を知ることの大切さ
中国と台湾の文化や価値観の差は、民族や遺伝の違いではなく、歴史や社会制度、教育の影響で生まれたものです。奈良の鹿のような観光地でのエピソードも、その背景を理解すれば単なる偏見に陥ることなく、より冷静に受け止められます。
国や地域の文化差を理解することは、異なる価値観を持つ人々と共に生きる現代社会において欠かせない視点です。台湾や中国への関心をきっかけに、歴史や教育の役割を改めて考えてみると、私たち自身にも役立つ改善点が見つかるかもしれません。
関連記事:台湾に中国人が多い理由 – 台湾の歴史
記事中でも紹介しましたが、台湾に中国人(漢民族系の人)が多い理由については、以下の記事で詳しく紹介しています。
日本ともつながりが深い「オランダ」による植民地の時代から、明・清時代、そして日本統治時代から終戦後まで、歴史を辿りながら解説していますので、是非あわせてご覧ください。