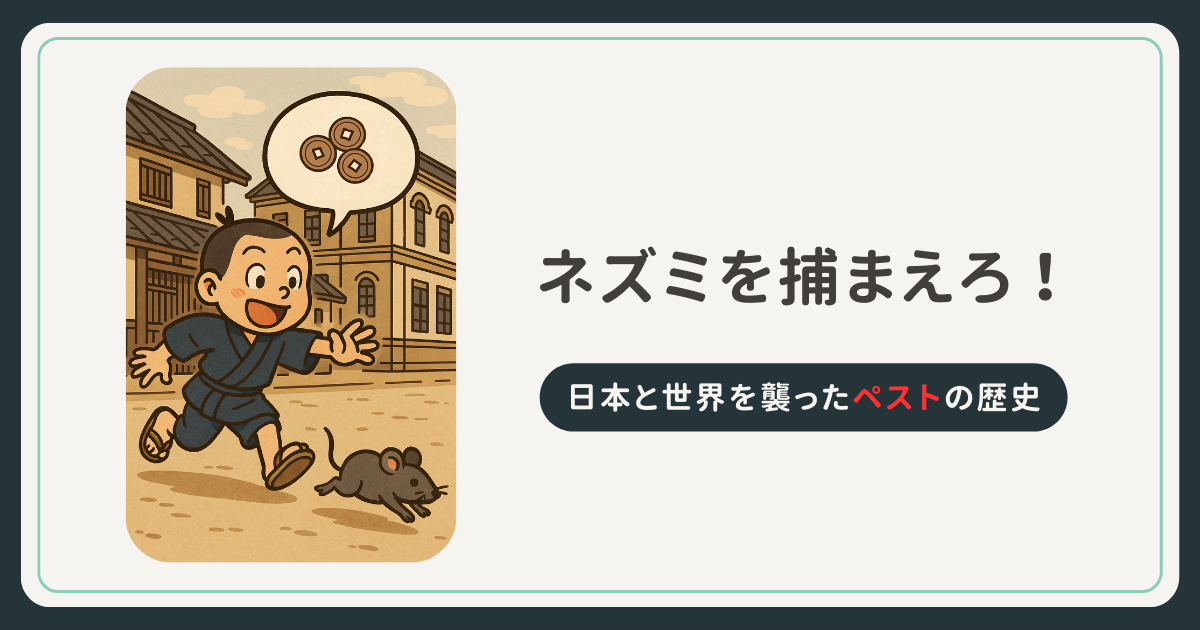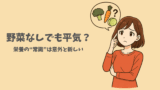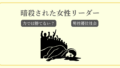ペストは人類史を揺るがした恐ろしい感染症です。
しかし日本では「ネズミを捕まえろ!」というユニークな作戦で封じ込められた時代がありました。
この記事では、ペストという感染症の基本情報や世界の歴史と共に、日本での流行と防疫(ネズミ駆除キャンペーン)についても紹介しています。
ペストとは:死亡確率100%の感染症
現代では名前を聞くことも少なくなった「ペスト」ですが、人類史の中では最大級のパンデミックを引き起こした感染症の一つです。治療をしなかった場合の死亡確率は100%です。
主にノミから感染する病気で、人間の生活圏にいるネズミやリスなどのげっ歯類に寄生するノミから人間にも感染し、感染した人の飛沫や排せつ物などからも感染します。
一度感染が広がり始めると深刻な被害をもたらす危険な感染症として、日本では最も重い「一類感染症」に分類されています。
ペストのワクチンはありませんが、現在は抗生物質を使って治療することが可能となっています。
黒死病と呼ばれた理由
ペストは、日本では黒死病とも呼ばれます。
「黒死病」という言葉は、死者の体に現れる黒い斑点や皮膚の変色をイメージしたものとされます。
ラテン語の atra mors(アトラ・モルス=「黒い死」「恐ろしい死」)が語源とされ、のちに英語で Black Death と訳されました。日本語の黒死病はその英語を訳したものです。
英語でペストはthe Plague(プレイグ)と呼ばれます。the Black Deathは後世に付けられた呼称で、俗称に近いニュアンスがあります。
英単語plagueについては、以下の記事で発音や例文などを使って解説をしています。
覚え方のコツや、theが付くかどうかのニュアンスの違いなど、言語の側面からplagueを解説していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
💡関連記事:plague(プレイグ)の覚え方:特殊な発音の解説や類似単語の紹介
「ペスト」の歴史 – history of the plague
危険な感染症ペストは、人々に甚大な被害を出したことで、歴史に深く刻まれています。
ここでは、ヨーロッパでの大流行とその経緯について紹介します。
14世紀にヨーロッパで大流行した「ペスト」
ペストは、14世紀のヨーロッパで流行したことが知られています。
ヨーロッパの人口3分の1を死に至らしめたとも言われており、当時は治療も埋葬もままならず、道端に遺体が積み重なってた地獄のような様相だったとも伝えられています。
ペストの名前は、14世紀当時のヨーロッパでは「the pestilence(疫病)」や「the great mortality(大死亡)」と呼ばれており、「the Black Death:黒死病」という言葉自体は後世(18世紀頃)の研究過程で付けられました。
ペストの感染経路
ペストの起源は中央アジアのステップ地帯と考えられています。
モンゴル帝国の勢力下でユーラシア大陸の交易網(シルクロード)が整備され、人・物・ネズミが広範囲に移動する環境が整いました。この国際的物流網により、ペスト菌を媒介するノミが寄生した黒ネズミ(Rattus rattus)がキャラバンや商隊と共に広がったとされています。
また、海上貿易も盛んだったため、ノルマンディーやロンドンなど北ヨーロッパの港湾都市も早期に感染が拡大します。
都市の人口密度が高く、衛生状態も悪かったため、都市部で爆発的に流行していきました。農作物などの移動と共にネズミも移動し、感染は更に広がっていきます。猫・犬などの動物も二次的な感染拡大に影響したと考えられています。
カッファ包囲戦:クリミア半島での戦争
また、戦争での非道な行為も、ペストの感染を広げる要因になったとされています。
モンゴル帝国がヨーロッパへ侵攻した際に、モンゴル軍内で発生したペストによって亡くなった人の遺体を、カタパルト(投石器)によって敵軍の場内に投げ入れるという恐ろしい行為が行われ、ヨーロッパ軍側でもペストが広まったとされています。(1346年 クリミア半島 – カッファ)
カッファ攻囲戦のこの戦術は、「生物兵器の初例」とされています。
実際には、攻囲戦で疫病が蔓延し、港に停泊していたジェノヴァ商人の船にネズミが乗り込み、イタリアのメッシーナ港など地中海沿岸都市に病気が広まったと考えられています。
日本でも流行したペスト
日本では、1899年(明治32年)に侵入が確認され、その後27年の間(1926年まで)流行しています。
27年間の流行の間に2,905名が感染し、2,420名の方が亡くなられています。
1927年以降は日本国内での感染は確認されていません。
日本でペストが流行した時代 – 日清・日露戦争
ペストが侵入した1899年は明治32年で、ペストが最後に国内で確認された1926年は大正15年/昭和元年です。
ペストが流行した時代は、日本が戦争の時代に突入した時期と重なります。
| 西暦 | 出来事 |
|---|---|
| 1894年 | 日清戦争 |
| 1899年 | 日本にペスト侵入 |
| 1904年 | 日露戦争 |
| 1926年 | ペスト流行の終結 |
当時陸軍省医務局長(衛生行政の最高責任者)だった「森鴎外」は、軍医としてペストの検疫や隔離政策で活躍しています。
森鴎外は、日露戦争時の脚気対策において細菌説を重視し、結果多くの犠牲者を出したことで有名です。詳しくは以下の記事をご覧ください。
💡関連記事:常識はときに人を殺す ― 森鴎外と脚気の教訓
インフラが発達途中だった日本
ペストが流行した当時の日本は、近代インフラを整備している途中の段階でした。
下水道は都市部だけで、汲み取り式便所(肥溜め)が主流の時代です。ゴミや動物死骸は路上や空き地に捨てられることも多く、ネズミが繁殖しやすい都市環境でもありました。
明治時代、日本は欧米諸国を参考に近代インフラの整備を行っていきました。
何もないところから新しい国や街を作るのは簡単ではありません。以下の記事では、日本がどのようにインフラの整備を進めたのかをまとめていますので、是非ご覧ください。
💡関連記事:「女性だけの街」から考える明治時代 – 近代インフラ整備の歴史
当時の主なインフラ整備状況について、以下にまとめます。
| 項目 | 状況 |
|---|---|
| 上水道 | 横浜など港町で始まったばかり、全国では普及途上 |
| 下水道 | ほぼ未整備、汲み取り式便所が主流 |
| ゴミ処理 | 不十分でネズミ繁殖の温床 |
| 都市構造 | 港湾都市の急成長期で衛生管理が追いつかず |
| 衛生政策 | ペスト流行が科学的防疫・消毒・検疫の本格化の契機 |
命懸けのネズミ駆除キャンペーン
日本らしいユニークな防疫の事例をひとつ紹介します。
日本政府はペスト感染拡大を抑えるために、衛生状態の改善など様々な取り組みを進めますが、その施策の一つに「ネズミの捕獲奨励金制度」があります。
ペスト菌は ネズミノミ(Xenopsylla cheopis) を介して人間に感染します。1894年、仏人医師イェルサンによるペスト菌の発見後、ネズミの駆除が最も効果的な防疫策と認識されました。日本でも1899年神戸港でのペスト発生を契機に、港湾都市を中心に全国的なネズミ駆除キャンペーンが始まります。
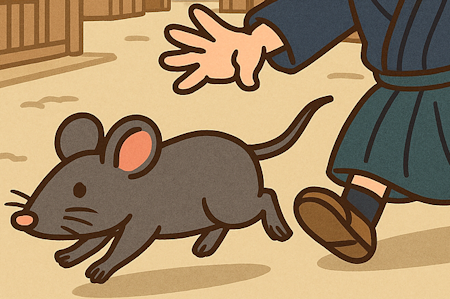
ネズミ1匹ごとに数銭単位(地域・時期により異なる)の奨励金を設定し、ネズミ捕りカゴや罠などを使って、市民参加型で防疫が進められました。
当時の新聞・ポスターでも「ネズミ一匹でも捕まえよう!」と住民に呼びかけるキャンペーンが展開されます。
一部の地域では「ネズミを捕ってお金を稼ぐ」子どもたちの姿が社会現象にまで発展します。
ゴム手袋もマスクもない時代
当時はゴム手袋もなければ、マスクやビニール袋もない時代です。市民はペスト菌を持っている可能性があるネズミを「素手で」捕まえ、役所や衛生当局に持ち込んでいました。
死んだネズミの体にもペスト菌を持ったノミが多数寄生しているため、人間にも感染する危険性がありました。ネズミ捕獲奨励金制度では、捕まえたネズミは紙や布、木箱に入れて持ち込むのが一般的でした。
日本の防疫当局(内務省・陸軍医務局)は、この危険性をある程度認識していました。
- ネズミ回収所では石炭酸(フェノール)や昇汞などの強力な消毒薬を常備
- 回収後はすぐに焼却・薬液漬け
- ネズミを持ち込む際に「袋や容器に入れる」よう指導
とはいえ、農村部や貧困層では防護が徹底されず、現代基準では極めて危険な作業でした。
この奨励金制度の効果や評価について、以下にまとめておきます。
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 短期効果 | ペスト流行の局地化に貢献、衛生意識向上 |
| 長期効果 | ネズミ個体数抑制は一時的で、恒久策にはならず |
| 歴史的意義 | 市民参加型防疫・科学的検査の基盤を築いた |
軍だけじゃない:日本の近代化の効果
日本は近代化を進めたことで、衛生環境は改善され、ペストだけでなくコレラや天然痘など、人々を苦しめていた病気を遠ざけることに成功していきます。
日本は江戸時代の鎖国政策でヨーロッパに大きな後れを取っていましたが、明治時代の近代化は世界的に見ても異常な速度で進行しており、明治中期~後期には、医学・科学など様々な分野で日本人も最先端技術に貢献し始めます。
明治後期に日本人が発見した「オリザニン」は、後に「ビタミン」と名付けられ、現代の栄養学の発展に大きく貢献しました。栄養の研究により、脚気や壊血病などの病気を克服していきます。
現代では野菜を食べないことで栄養不足となり、脚気予備軍のような人も増えていると、医学者たちも警鐘を鳴らしています。以下の記事では栄養が原因となる歴史的な病気と共に、対策に有効な食材なども紹介していますので、是非参考にしてみてください。