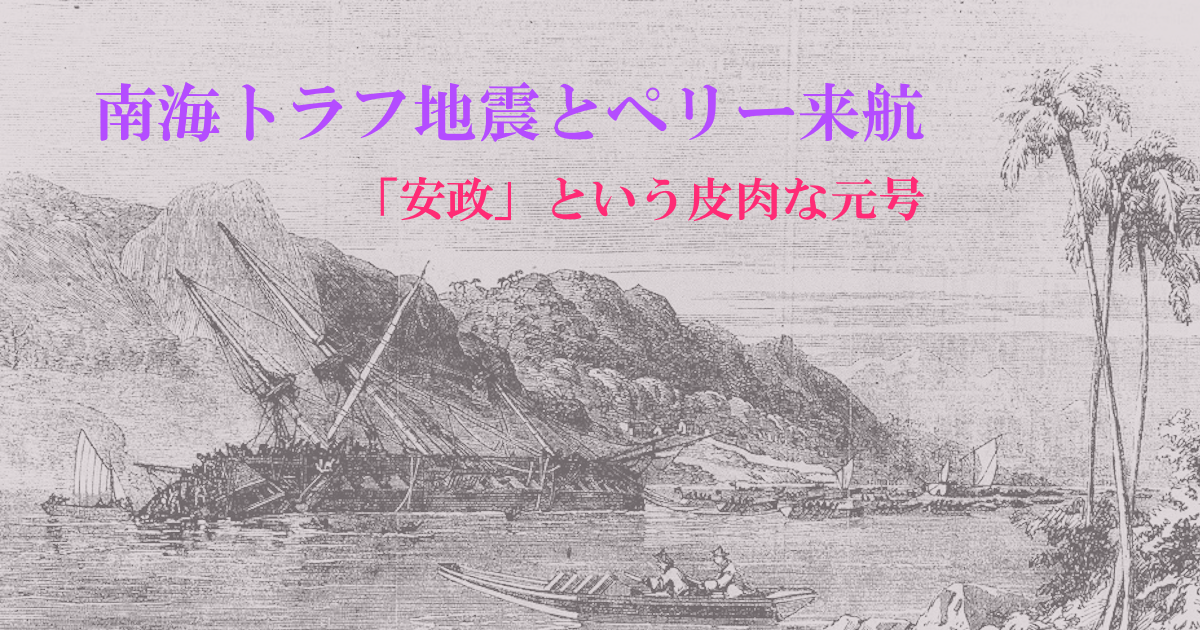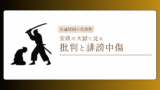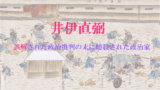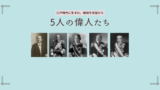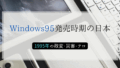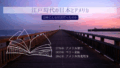歴史の中の出来事は、いつどういった事が起きたのかを学びます。関係する内容を流れで覚えることもあるでしょう。しかし、異なる分野の出来事は切り分けて学ぶことが多く、並行して起きている事象であってもそれらを合わせて考えることはあまりありません。
今回は、南海トラフ地震とペリー来航という「一見関係がなさそう」な出来事についてまとめています。幕末の激動の時代に起きた災害の状況やその後の国内外の動き、そして「安政」という皮肉な元号を知ると、歴史の捉え方に変化があるのではないでしょうか。
南海トラフ地震とは
「南海トラフ地震」は、ニュースや特集番組などで報じられることも多いため、令和に生きる多くの日本人(特に近畿・四国地方周辺)は内容を理解していると思いますが、念のためどういった災害なのかを確認しておきましょう。
南海トラフ地震とは、「南海トラフ」と呼ばれる静岡県駿河湾から九州日向灘沖にかけての海溝沿いで発生する、マグニチュード8~9クラスの巨大地震のことです。
南海トラフ地震は、およそ100~150年間隔で繰り返し発生しています。数年か数十年内の内には次の地震が発生するとみられており、災害対策や防災意識の向上などが呼び掛けられています。
過去の南海トラフ地震
南海トラフ地震は規模が大きく、影響を受ける地域が広大な事でも注目されていますが、何よりも恐ろしいのが「定期的に発生」している事ではないでしょうか。人間の寿命よりも長い間隔で発生する地震で、現代の様に「人々の記憶が薄れた頃に発生する」という恐ろしさもあります。
過去に発生した南海トラフ地震についての研究は進められていますが、古いものについては規模や地域が不確かな物もあったり、記録が残っていないものが存在している可能性もあります。
現在までの研究によって明らかになっている、代表的な南海トラフ地震には以下のようなものがあります。
| 西暦 | 名称 | 間隔 |
|---|---|---|
| 684年 | 白鳳(南海)地震 | – |
| 887年 | 仁和(南海)地震 | 203年 |
| 1096年 1099年 | 永長(東海)地震 康和(南海)地震 | 209年 |
| 1361年 | 正平東海地震、正平南海地震 | 262年 |
| 1498年 | 明応東海地震 | 137年 |
| 1605年 | 慶長地震 | 107年 |
| 1707年 | 宝永地震 | 102年 |
| 1854年 | 安政東海地震、安政南海地震 | 147年 |
| 1944年 1946年 | 昭和東南海地震 昭和南海地震 | 90年 |
令和の現代は、最後の南海トラフ地震から約80年経過していて、いつ起こってもおかしくないと言われています。また、発生確率は毎日少しずつ高まっている状況でもあります。
安政大地震 ー 「ペリー来航」の翌年に起きた南海トラフ地震
安政大地震とは「安政東海地震」と「安政南海地震」の総称で、江戸時代に発生している3回の南海トラフ地震の中では最後、幕末時期の1854年に発生した地震を指します。
安政大地震は、令和の現代から数えると、直近の昭和東南海・南海地震(約90年前)の前、つまり2個前の南海トラフ地震ということになります。
安政大地震が「発生した当時」の日本の状況
安政大地震が起きた1854年という年は、歴史の授業では「日米和親条約」が締結された年として習います。
その前年(1853年)にペリーが浦賀に来航したことで、地震発生時の日本では「黒船」騒動の真っ最中でした。
欧米列強の技術力・軍事力に注目が集まり、対外政策(鎖国の是非)について幕府だけでなく国民全体が考えていた時期でもあります。
| 西暦 | 出来事 |
|---|---|
| 1853年 | ペリー来航 |
| 1854年 | 日米和親条約 (3月) 安政大地震 (11月) |
| 1858年 | 日米修好通商条約 |
地震に巻き込まれたロシア船 – ディアナ号
日本では、アメリカのペリーが来航したことを学校で習いますが、この時期には欧米列強の他の国が次々に日本を訪れました。アメリカのペリーが浦賀にやってきた翌月には、ロシアのプチャーチンがディアナ号に乗って長崎に来航しています。
ロシアのディアナ号は、安政東海地震(1854年12月)の発生時は下田に寄港しており、そこで地震の影響で発生した津波に巻き込まれ大破します。
ディアナ号はその後修理のため戸田港に向かって曳航されていましたが、途中で嵐に遭って座礁し、沈没してしまいます。
当時の江戸幕府は、安政東海地震の発生前に、ロシアに「下田は安全な港ではない」として代港を申し入れていましたが、その会見の3日後には大地震が発生し、ディアナ号は災害に巻き込まれました。地震発生時の状況について、ディアナ号でも記録が残っています。
「安政」という時代
安政大地震の「安政」は、日本の元号です。
ちなみに、令和は232番目の元号で、安政は223番目の元号です。
安政の元号は、西暦(グレゴリオ暦)1855年から1860年の約7年間使われました。
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 嘉永7年11月27日 (安政元年) | 1855年1月15日 |
| 安政7年3月18日 | 1860年4月8日 |
安政という元号は、「安政の大獄」の名前に含まれていることで知っている人も多いでしょう。
以下の記事では、安政の大獄についてまとめていますので、興味のある方はこちらもご覧ください。
黒船・地震の災禍で変わった元号「安政」
「安政」は、黒船の来航や地震の発生などの災害が続いたために、当時の孝明天皇が改元して付けられた元号です。
つまり、南海トラフ地震が起きたことで日本の元号「安政」が生まれたともいえるのです。
地震が起きたから「安政」に元号を改めたことからも分かるように、
南海トラフ地震は「安政」になる前の「嘉永」の時代に起きています。
そのため、安政大地震という名称は嘉永大地震とするべきだという見解もあるようです。
南海トラフ後の余震と幕末外交の動き
安政年間は激動の時代で、相次いで発生する地震と欧米列強との外交交渉、そして国内の思想の錯綜による様々な事件が立て続けに起きています。
以下の表では、南海トラフ地震後の余震、それと並行して起きた外交や事件の代表的な物をまとめています。
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 嘉永7年 | 日米和親条約締結 (3月) 伊賀上野地震 (6月) 安政東海地震 (11月) 安政南海地震 (11月) 豊予海峡地震 (11月) |
| 安政元年 | 安政に改元 (11月) 日露和親条約締結 (12月) |
| 安政二年 | 飛騨地震 (2月) 陸前で地震 (8月) 遠州灘で地震 (9月) 安政江戸地震 (10月) |
| 安政三年 | 安政八戸沖地震(7月) 江戸で地震 (10月) |
| 安政四年 | 駿河で地震 (5月) 伊予・安芸で地震 (8月) |
| 安政五年 | 飛越地震 (2月) 八戸沖で地震 (5月) 日米修好通商条約締結 (6月) – 続いて蘭、露、英、仏と五カ国条約 安政の大獄が始まる (9月) 石見で地震 (12月) |
| 安政六年 | 石見で地震 (9月) |
| 安政七年 | 桜田門外の変 (3月) – 井伊直弼が暗殺される。 |
「安政」の終わり – 桜田門外の変で変わった元号
井伊直弼は、鎖国派の政治家でしたが、圧倒的に技術力の低い日本が欧米列強に対抗する「攘夷」は無謀と考え、暫定的な開国政策を進めました。日本の技術力を高めた後に、改めて鎖国政策も可能と考えての行動でしたが、誤解を受けた末に最終的には暗殺されてしまいます。(桜田門外の変)
桜田門外の変やその経緯について興味のある方は、以下の記事をご覧ください。
桜田門外の変(安政7年 3月3日)という凶事が起きた事を受けて、元号は「安政」から「万延(まんえん)」に改められます。(安政7年 3月18日)
地震と不平等条約 – 皮肉な「安政」の時代
皮肉なことに、南海トラフ地震と黒船来航という災難を払拭しようと改元された「安政」の時代は、度重なる地震と不平等条約をもたらし、安政の時代が終わる頃に地震は収束します。
安政の時代といえば「安政の大獄」が有名ですが、安政は南海トラフ地震と黒船来航によって付けられた元号であり、その後の苦しい不平等条約の交渉の間に余震が続いていたことは、あまり知られていません。
「地震の恐怖」と「外国の脅威」にさらされていた当時の日本人は、不安な日々を過ごしていたのではないでしょうか。
歴史にある「現実の日々」
歴史上の出来事や人物などは、現実に起きた出来事で存在した人であることは頭で理解していても、どこか「架空の物事」のように感じてしまうことがあります。これは、歴史に刻まれた記録が事実の一部分を切り出したものであり、人間性や生活感のような情報が含まれていないことが多いためでしょう。
しかし、歴史は現実の出来事です。今回紹介した「ペリー来航」のような事件や、「安政大地震」のような災害が起こった際にも、人々は暮らしていました。現代の私たちと同じように、何気ない噂話などをしながら日々生活していたのです。
歴史を学ぶ上では、点で出来事を拾うのではなく、時の流れ全体を捉え、そこにある「現実の日々」を想像してみると、新しい疑問や視点を得られるのではないでしょうか。
関連記事:幕末に生まれ昭和まで生きた偉人
日本の歴史の中でも特に激動の時代となった江戸時代・幕末の時代に生まれ育ち、その後の明治大正の近代化を経て、昭和まで生き抜いた偉人たちがいます。
彼らの目には、日本の急速な変化はどのように映っていたのでしょうか。
以下の記事では、代表的な5名の偉人を紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。