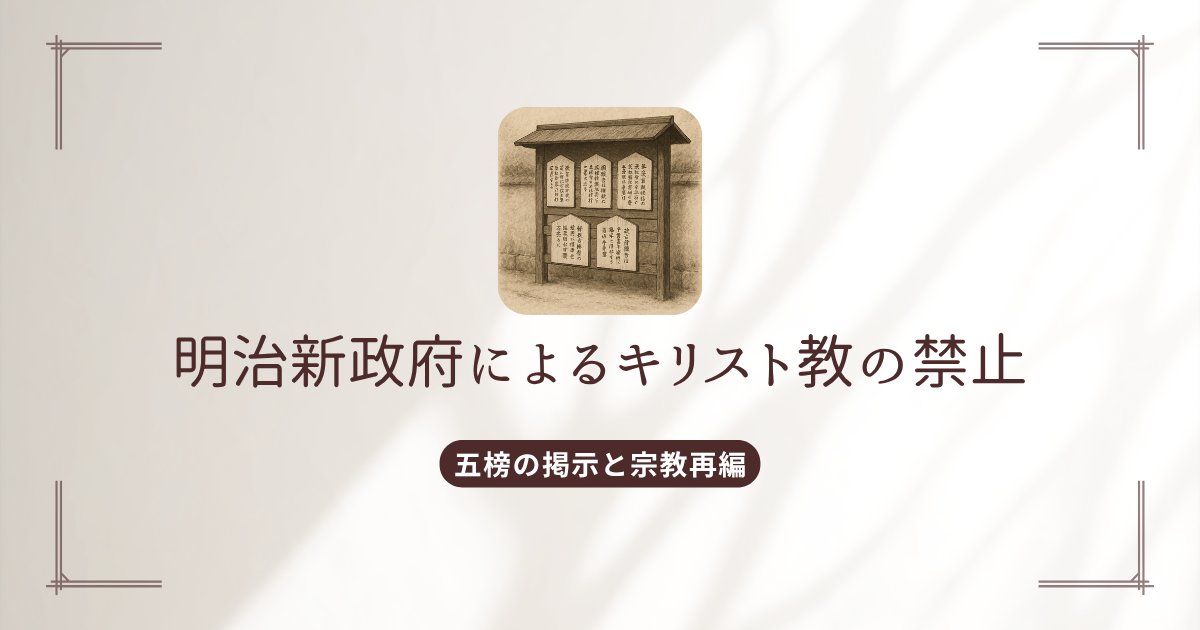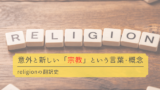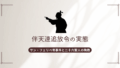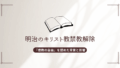💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
幕末の混乱を経て誕生した明治新政府。
近代国家をめざすその第一歩で掲げられた「五榜の掲示」には、江戸時代から続くキリスト教禁止の方針が明記されていました。新しい時代の宗教政策は、ここから始まります。
幕末の弾圧から明治へ ― 新政府が受け継いだ秩序の思想
幕末の動乱を経て、日本は明治維新を迎えました。(1868年)
政治体制は大きく変わりましたが、新政府が直面した最初の課題は、
国内の混乱を治め、法と秩序を取り戻すことでした。
そのため、旧来の統制思想や制度の多くが、新しい時代にも受け継がれていきます。
幕末動乱中の潜伏キリシタンの発見と処罰 ― 浦上事件
江戸時代の末期には、各地で潜伏キリシタンの発見や処罰が行われました。
その中でも、長崎・浦上村で発覚した摘発事件(浦上事件、または浦上四番崩れ)は、
幕府による最大規模の取締りとして知られています。(1867年)
浦上事件では、約3400人の信者が摘発され、全国20藩に流配されて改宗を強要されました。直接の処刑こそ行われなかったものの、過酷な拘禁や拷問により、およそ600人が命を落としたと伝えられています。
この出来事は、江戸幕府による統治の枠組みの中で実施されたものでした。
幕末の浦上事件については、以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:幕末のキリスト教弾圧 ― 教会に現れた隠れキリシタンの行く末(浦上事件)
法に従わない者への警戒 ― 明治新政府の基本方針
明治新政府もまた、この基本的な姿勢を引き継ぎました。
宗教を信じること自体よりも、
「禁教という法に従わない者」を警戒するという考え方です。
キリスト教は依然として“禁じられた教え”であり、信仰の自由という概念はまだ存在していませんでした。
国家にとって重要なのは、信仰よりも秩序――
それが、明治という新しい時代の出発点における現実だったのです。
五榜の掲示 ― 最初の布告に盛り込まれた禁教
明治元年(1868年)の3月に、新政府は全国に「五榜の掲示」と呼ばれる高札を立てました。
この布告が出されたのは、鳥羽・伏見の戦い(1月)から戊辰戦争が始まった直後で、国内はまだ戦乱の最中という状況でした。
「五榜の掲示」は、新しい時代の道徳と秩序を示すものであり、庶民に向けて発せられた明治政府最初の布告とされています。
その第五条には、次のような文言が含まれています。
「邪宗門を信ずることなかれ」
たった五条しかない明治新政府最初の布告に「キリスト教の禁止」が盛り込まれていたことからも、当時の政府がこの宗教をいかに警戒していたかが伺えます。
五榜の掲示の目的と位置づけ
五榜の掲示は、徳川幕府の「御触書」に相当するものでした。
新政府はこれを通じて、民衆に忠孝・仁愛・法令遵守などの徳目を示しましたが、
その中に“邪宗門禁止”を加えたのは、治安維持の一環としてでした。
キリスト教は政治的動乱をもたらす“異端思想”と見なされていたのです。
掲示の目的は宗教弾圧というより、「社会秩序の保持」でした。
学びと警戒の同居 ― 明治新政府が抱えていた二重構造
幕末から明治初期にかけて、日本はフランスという国を「世界最高の文明国家」として見ていました。ナポレオン3世のもとでの近代国家建設(法・軍・産業・建築など)は、まさにモデル国家だったのです。
その一方で、政府は外交情報を通じて、フランスがアジア各地で「宣教師保護」を口実に侵略を進めていることを知っていました。
- 1858年以降のベトナム侵攻
- 清国への共同出兵(アロー戦争)
- 宣教師殺害事件を名目とした軍事介入
- アジア諸国での教会建設・領事特権の拡大
明治新政府はフランスの「文明(技術・法・軍制)」には憧れと尊敬を抱きながらも、フランスの「宗教(カトリック)と外交(植民地主義)」には深い不信と恐怖を抱いていたのです。
| 系統 | 主な人物 | 特徴 |
|---|---|---|
| 親仏・近代化派 | 大久保利通・大隈重信・山県有朋ら | 「文明国フランスに学べ」派。制度・軍事・法を重視。 |
| 警戒派・実利派 | 岩倉具視・木戸孝允・伊藤博文ら | フランス式の統制と宗教支配を危険視。後に英米志向へ。 |
日本ではこの時代に、主に服飾関係の分野において「フランス語由来の外来語」が広まりました。
アジアでのフランスと普仏戦争 ― ドイツに学び始める日本
当時、アジアでは英仏が覇権争いをしていた時代です。
- イギリス:清国・香港・インドを支配。自由貿易と海軍力中心。
- フランス:インドシナ・中南半島に進出。カトリック布教と陸軍力中心。
明治維新後のフランスは、普仏戦争(1870–71年)の敗北によってナポレオン3世が退位し、第三共和政へと転換して「政教分離を志向する国家」へと変化していきました。
一方その頃、日本は同じ戦争で勝者となったドイツに学び、国家の秩序を重んじる“プロイセン型”の体制へと歩み始めます。
ドイツ語はオランダ語と近い言語です。明治日本にとって唯一扱うことの出来たヨーロッパの言語「オランダ語」は、近代化や外交において重要な役割を果たします。
💡関連記事:ペリーとの交渉はオランダ語? – 英語と日本語を繋いだ鎖国日本のヨーロッパ言語
💡関連記事:オランダ語からドイツ語へ – 明治日本の言語学習の変化
「邪宗門」という言葉が意味したもの
「邪宗門」とは、江戸時代から使われていた公的な表現で、主にキリスト教を指していました。
“邪”とは「正しい教えに背く」という意味であり、単なる宗教上の違いではなく、
国家に逆らう“不忠の思想”として理解されていました。
それほどまでに、キリスト教は「反体制的な危険思想」とみなされていたのです。
宗教再編の時代 ― 神仏分離と国家神道の萌芽
キリスト教の禁止は、単なる保守的な姿勢ではなく、新政府が進めた「宗教再編」の一環でもありました。
幕末の政治混乱を経て、日本の宗教体系そのものを組み直す動きが始まっていたのです。
神仏分離令と廃仏毀釈
明治元年に出された「神仏分離令」は、神社と寺を明確に分けることを目的としていました。
しかし実際には、仏教勢力を排除する政策として機能し、全国で寺院破壊や仏像の廃棄が相次ぎました。これが、いわゆる「廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)」と呼ばれる現象です。
明治新政府には、長年にわたって政治と深く結びついてきた仏教を整理し、
「日本古来の神道」を国家の中心に据え直そう
という意図がありました。
宗教の統一は、新しい国家体制を支える「精神の基礎」とされたのです。
寺請制度と戸籍制度 ― 国民を把握する手段
明治の神仏分離は、単なる宗教改革ではなく、「寺が担っていた国民管理を、国家が奪い取る」構造改革でもありました。
江戸幕府の寺請制度では、各寺が信者の名簿=宗門人別帳(宗門改帳)を作成し、幕府の行政資料としても使われていました。寺が宗教統制(キリスト教の禁止)と戸口管理という行政の役割を果たしていたのです。国民は必ずどこかの寺に属し、「寺請証文(檀那寺の証明)」がないと結婚・葬式・旅行などができませんでした。
神仏分離令によって、仏教勢力の政治的役割は剥奪されました。しかし、それと同時に行政が全国民を把握する手段もなくなってしまいます。
この「空白」を埋めるために、明治政府は1871年(明治4年)、「戸籍法」を制定し、全国統一の戸籍制度(壬申戸籍)をつくります。この戸籍は、寺院の記録を参照して編成されます。
寺請制度は、明治6年(1873)に正式廃止されます。
天皇を中心とした「大教宣布」の構想
神仏分離によって仏教勢力を排除した結果、民衆の間では「では、何を信じればいいのか?」という空白が生じました。
この空白を埋めるために、1870年1月3日に 「大教宣布の詔(たいきょうせんぷのみことのり)」 が布告されます。
これは、天皇を中心とした国家的教化政策であり、“天皇の教え=国民の道徳”という考え方に基づくものでした。
詔の骨子は以下の3点にまとめられます。
- 天地祖神(天照大神など)を敬い、天皇を尊ぶこと。
- 道徳を正し、人としての本分を尽くすこと。
- 天皇の教え(=大教)を広めることを国民の務めとすること。
排除対象となるキリスト教 ― 明治新政府の宗教政策の方針
この流れの中で、外国由来の宗教――とりわけキリスト教――は排除の対象になりました。
天皇を「天照大神の子孫」とする神道中心の国家理念(後の現人神思想)と、
唯一神を信じるキリスト教の教義は、根本的に両立しないと考えられたのです
この時期の宗教政策は、
「仏教の整理」+「神道の国教化」+「キリスト教の排除」
という三位一体の流れで進んでいます。
一般的でなかった「宗教」という言葉
この時代の政府文書には、まだ「宗教(しゅうきょう)」という言葉が一般化していません。
代わりに「教え」や「道」といった語が使われ、宗教は倫理・道徳と同一視されていました。
つまり、信仰とは個人の救いではなく、国民としての“正しい生き方”を意味していたのです。
宗教と訳されたreligionの翻訳史については以下の記事で詳しくまとめています。
秩序維持としての禁教は「時代遅れ」に
明治維新当時の日本には、「信教の自由」という概念は存在していませんでした。
キリスト教という宗教を禁止することは、国の秩序を守るための「当然の措置」と考えられていたのです。
これは日本だけの特殊な事情ではありません。
ヨーロッパでも他宗教への弾圧は長く続き、ときには戦争にまで発展しました。
しかし17世紀頃から次第に宗教的寛容の思想が芽生え、アメリカ独立宣言(1776)やフランス人権宣言(1789)では、法の下で「個人の信仰を保証する」理念が明文化されるようになります。
日本が明治維新を成し遂げて近代化を進めていたその頃、欧米諸国ではようやく「信教の自由」が憲法で保障され始めたばかりでした。
「信教の自由」という新しい理念は、やがて明治日本の前に立ちはだかることになります。
本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。