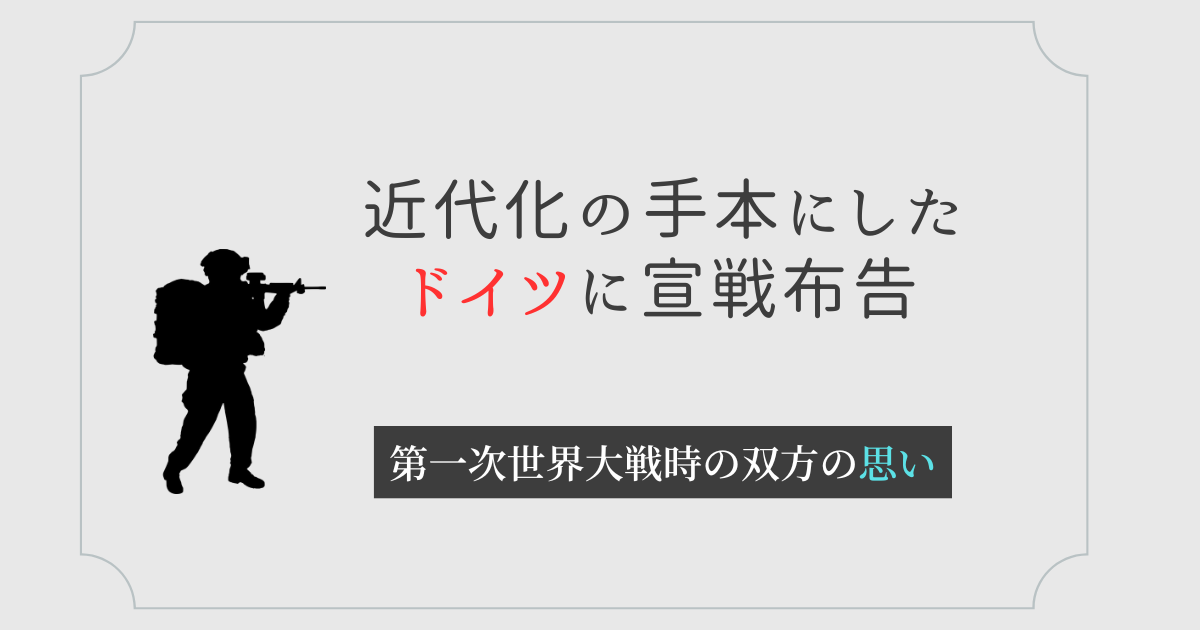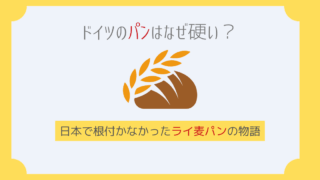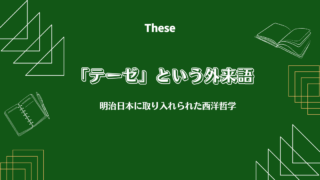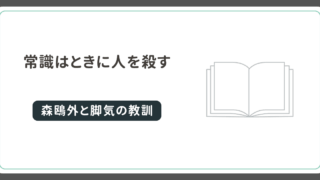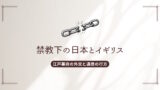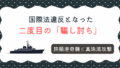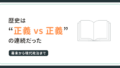明治日本は、近代国家としての制度や軍事、学問を整えるためにドイツを手本としてきました。憲法、軍制、医学教育など、多くの分野でドイツ式を採用し、国としての礎を築いていきました。
しかし、第一次世界大戦が勃発すると、その「先生」ともいえる国に日本は宣戦布告します。なぜ日本は憧れの国と戦うことになったのでしょうか。そして、当時の双方は何を思っていたのでしょうか。
ドイツは明治日本の“先生”だった
明治維新後、日本は西洋諸国を視察し、どの国の制度を取り入れるべきかを検討しました。その中で、憲法や軍事制度においてはドイツ(当時はプロイセン王国を中心とするドイツ帝国)をモデルに選びました。
1889年に発布された大日本帝国憲法は、ビスマルク憲法とも呼ばれるドイツ帝国憲法を参考に制定されています。また、陸軍制度は参謀本部や兵制、教練に至るまでプロイセン式を採用しました。

医学教育もベルリン大学出身の医師が教鞭をとり、「ドイツ語を学ばなければ医者になれない」とまで言われた時代でした。明治期の知識人や軍人にとって、ドイツはまさに「近代化の先生」だったのです。
明治期の日本がドイツに学ぼうとした背景には、当時の日本人の言語能力も関係しています。以下の記事で詳しく紹介していますので、興味のある方は是非ご覧ください。
💡関連記事:オランダ語からドイツ語へ – 明治日本の言語学習の変化
第一次世界大戦時の日本とドイツの思い
ドイツに憧れ、ドイツに学び近代化を進めていた日本が、第一次世界大戦では敵味方になって戦っています。
ここではその「政治的な背景」と共に、各国の受け止めについて紹介しています。
日英同盟と参戦要請に揺れる日本
1902年、日本はイギリスと日英同盟を結びます。
当初はロシアの極東進出を牽制するための軍事的枠組みでしたが、1911年の改訂で、「一方の同盟国が二国以上と戦う場合」にも適用されることになりました。
1914年7月、ヨーロッパで第一次世界大戦が勃発します。
イギリスは連合国側として参戦し、同盟国である日本にドイツ東洋艦隊の無力化を要請します。
また、山東半島の青島にドイツ帝国の東洋艦隊基地があり、イギリスはこれを排除する作戦を日本に依頼します。
しかし日本政府内では賛否が分かれます。
外務省や海軍は同盟義務とアジアでの影響力拡大を重視して参戦を支持しましたが、陸軍や一部の政治家は「憧れの国・ドイツと戦うのは忍びない」と反発しました。
当時の新聞にもその複雑さは表れています。
「同盟国との信義を守るべし」との論説と、「欧州の師を敵に回すべきではない」という論調が並んで掲載されたのです。
最終的に日本は、8月23日にドイツへ宣戦布告しました。
宣戦布告を受けたドイツ側の本音
日本の宣戦布告は、ドイツにとって大きな衝撃ではあったものの、ある程度予想もされていました。ドイツ外務省は、日英同盟の存在から、日本がイギリスに協力する可能性を認識していたのです。
ただし、ドイツ国内の新聞には「かつての友が敵に回った」とする失望の声や、「日本はアジアの機会主義者だ」と批判する論調もありました。
- 外交ルート
日本が8月15日にドイツへ最後通牒(青島撤退要求)を送った際、ドイツはこれを拒否。
8月23日、日本は正式に宣戦布告。 - 政府の認識
ベルリン政府は「極東での劣勢は不可避」とし、青島要塞への援軍はほぼ不可能と判断。 - 軍事面
ドイツ海軍東洋艦隊(マクシミリアン・フォン・シュペー提督)は、本国帰還または南太平洋への行動を選択し、青島は孤立。
青島守備隊の司令官マイヤー=ヴァルデック少将は、援軍が望めない状況を理解しており、「名誉ある持久戦」を目標に戦う方針をとりました。
ベルリン政府も、欧州戦線への集中を優先し、極東戦線は事実上切り捨てる判断を下します。
青島戦役とドイツ兵捕虜の運命
1914年9月、日本軍はイギリス軍とともに青島を包囲しました。海上封鎖と陸上からの砲撃で圧力をかけ、11月には激しい総攻撃を行いました。守備隊は善戦しましたが、物資や弾薬の不足から11月7日に降伏します。
日本のドイツ兵捕虜への扱い
降伏した約4,700人のドイツ兵は日本へ送られ、全国12か所の捕虜収容所に分散収容されました。
- 数:約4,700人(将校から一般兵まで)
- 国籍:主にドイツ人だが、オーストリア=ハンガリー兵も一部含む。
- 送致先:日本国内各地の捕虜収容所
- 松山(愛媛)
- 似島(広島)
- 大阪
- 名古屋
- そして特に有名なのが徳島県鳴門市大麻町の板東俘虜収容所
その中でも徳島県板東町(現・鳴門市)の板東俘虜収容所は、比較的自由な生活や文化活動が許されたことで知られています。捕虜たちはパンやソーセージ作り、音楽演奏、スポーツなどを通じて地元住民と交流し、1918年には日本初のベートーヴェン「第九」交響曲全曲演奏を実現しました。
ドイツ人捕虜と関連した文化に興味がある方は、是非以下の記事もご覧ください。
ドイツ人捕虜の文化的な活動
板東俘虜収容所では捕虜たち自身が、『日本国板東俘虜収容所新聞』(ドイツ語名:Die Baracke)という週刊新聞を発行していました。1917年10月~1918年3月の第1~26号が制作されています。娯楽や催しの案内、作品展などが掲載されており、収容所内の文化活動をうかがわせます。「鳴門市ドイツ館」のWebサイトから一つ抜粋して紹介します。
参考リンク : 『日本国板東俘虜収容所新聞』第1巻(1917 年10 月 ~ 1918 年3 月)
「鳴門市ドイツ館」は、第一次世界大戦中に鳴門市に設置された板東俘虜収容所に収容されたドイツ兵と地元住民との交流を後世に伝えることを目的とした施設です。展示では、収容所の様子やドイツ兵の活動、地域住民との交流を紹介しています。展示されている資料について、Webサイトからも閲覧できるものが多数ありますので、興味ある方は見てみてください。
参考リンク : 鳴門市ドイツ館「板東俘虜収容所」資料Web
戦争が終わっても続いた交流
第一次世界大戦の終結後、1920年から捕虜の帰国が始まりましたが、一部のドイツ人は日本に残り、技術者や音楽家として活躍しました。板東収容所で培われた交流は、地元にドイツ文化を根付かせ、現在も「第九」演奏会などの形で続いています。
第一次世界大戦終了後の数年間は、日本からの留学生や技術者の往来は一時的に少なくなりますが、それでも日本の「ドイツへの憧れ」は強く、1920年代後半にはドイツ製品や技術への需要は復活し、日本の医学者や法学者を中心にドイツ留学が再開されていきます。
1920年代のワイマール共和国期には、日独は経済や文化面で再び接近し、1930年代には第二次世界大戦に向けて軍事同盟関係にまで発展していきます。「敵だった時代」が、後の同盟関係に全く影響しなかったわけではありませんが、両国は現実的な国益のもとに関係を再構築しました。
関連記事:ドイツから学んだ哲学
ドイツから学んだものは、憲法や医学だけではありません。哲学についてもドイツから学び、明治時代の日本でも教育が始まりました。
また、日本からドイツへ留学したことで有名な森鴎外は、軍医としても文豪としても様々な活躍をしたことで知られています。以下に明治日本とドイツに関係した記事をいくつか紹介します。
国家間の関係は変わる
明治日本とドイツの関係は、「手本 → 敵 → 同盟国」という大きな変転を経ました。この歴史は、国家間の関係が固定的ではなく、時代の状況や利害によって大きく変わることを示しています。かつての憧れの国を相手に戦い、その後また手を結ぶという流れは、国際政治において珍しいことではありません。
現代においても、同盟や友好が永遠に続く保証はありません。
第一次世界大戦期の日独関係は、その現実をよく物語っているのです。
江戸時代に友好国だったオランダとは、第二次世界大戦で戦うことになりました。
以下の記事で詳しく解説していますので、関心のある方は是非あわせてご覧ください。
関連記事:江戸時代のイギリスと日本
友好関係が変わったのは、明治以降だけではありません。
江戸時代には、日本がオランダと友好的な関係を築いていたことが知られています。しかし、江戸時代初期の日本は、イギリスにも通商の許可を出していました。イギリスはその後日本市場から撤退した後、再度通商開始を要請してきますが、今度は日本がそれを拒否します。
キリスト教の禁教が外交判断に影響した事例として、以下の記事にまとめています。この歴史からは、国防のためにキリスト教布教を徹底的に禁止した、日本の慎重な姿勢が伺えます。