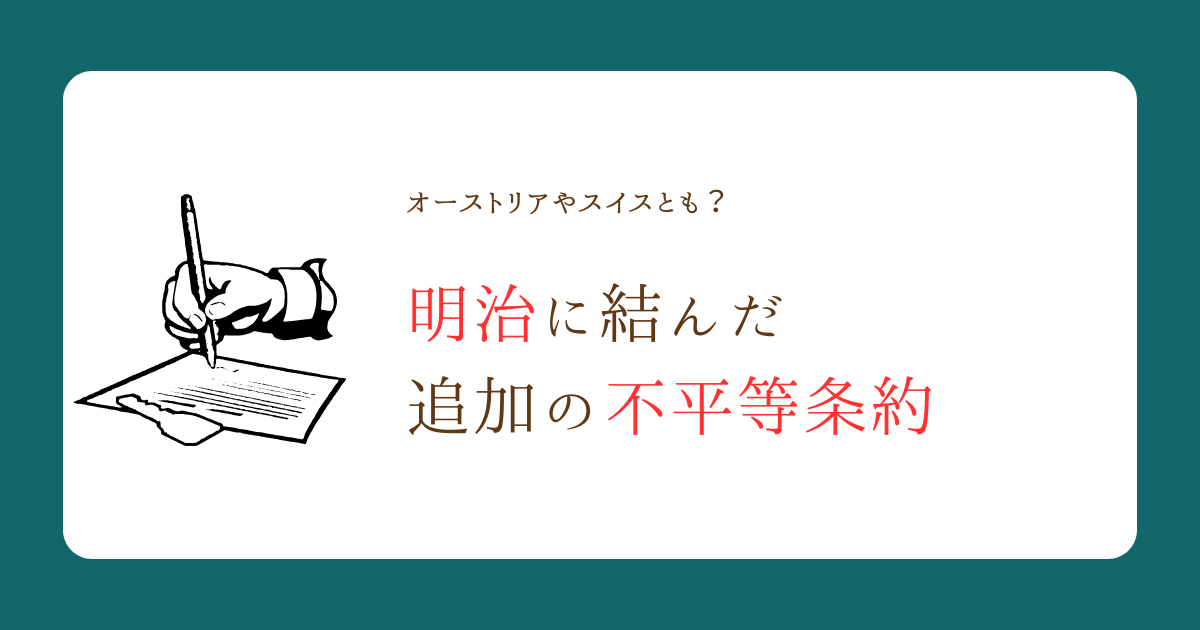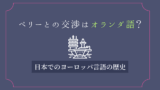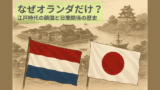教科書で必ず学ぶ「不平等条約」といえば、安政5年(1858)の日米修好通商条約です。日本が外国に開かれ、不平等な立場を強いられた象徴として語られることが多いでしょう。
しかし実際には、それで終わりではありません。
日本はその後も欧米の国々と同じような条約を次々に結び、半世紀以上にわたって「不平等条約の網」に絡め取られていたのです。
不平等条約といえば日米修好通商条約
幕末の日本が初めて「不平等条約」を結んだのはアメリカとの間でした。
1858年の日米修好通商条約 ― 開国と不平等の始まり
1858年、幕府はアメリカと修好通商条約を締結します。
この条約には二つの大きな制約がありました。
- 領事裁判権(治外法権):日本で犯罪を犯したアメリカ人は、日本の法律ではなくアメリカ領事の裁判を受ける。
- 関税自主権の欠如:日本は独自に関税を決められず、相手国と協議して決める必要があった。
これにより日本は主権を大きく制限され、幕府の威信は大きく揺らぎました。
ここから「不平等条約時代」が始まったのです。
安政の五か国条約 ― 欧米列強が横並びで要求
アメリカとだけ特別な約束を結んでしまうと、他国が不利になります。
そこで欧米列強は次々と同じ条件を日本に求めました。
1858年、五か国との修好通商条約
| 年(西暦/和暦) | 相手国 | 条約名 / 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1858(安政5) | アメリカ | 日米修好通商条約 | 治外法権・関税自主権の制限。 不平等条約の典型。 |
| 〃 | オランダ | 日蘭修好通商条約 | 〃 |
| 〃 | ロシア | 日露修好通商条約 | 〃 |
| 〃 | イギリス | 日英修好通商条約 | 〃 |
| 〃 | フランス | 日仏修好通商条約 | 〃 |
この五か国との間に結ばれた条約は、安政の時代に結ばれたことから「安政の五か国条約」という総称で呼ばれます。いずれも内容は日米修好通商条約とほぼ同一で、不平等条約の典型とされています。
列強同士が競い合う国際社会の中で、特定の国だけが突出しないように、日本に対しても外交関係の足並みをそろえる必要がありました。
こうして日本は「欧米列強と対等な関係」ではなく、「列強が横並びで権益を確保するネットワーク」に巻き込まれる形となりました。
江戸時代の友好国「オランダ」との関係
オランダは、鎖国をしていた江戸時代にも交流を続けた、ヨーロッパ唯一の国です。アメリカとの交渉においても、日本はオランダ語を介して交渉しています。
しかし、アメリカと不平等条約を締結すると、そのオランダとも不平等条約を締結することになりました。
列強国同士の政治的な事情によって、“鎖国時代からの特別な友好国”だったオランダとも、結局は不平等条約を結ばざるを得ませんでした。
以下の記事では、日本とオランダの交流開始から不平等条約の締結に至る過程や、幕末期に起きた下関戦争での軍事衝突など、江戸時代の日本とオランダの歴史について詳しく紹介しています。興味のある方は是非ご覧ください。
さらに増える不平等条約 ― 明治時代の追加締結
明治維新を迎えた新政府も、国際関係を広げるために多くの国と条約を結びました。しかしその中身はやはり「不平等条約」でした。
1869〜1880年の追加条約
幕末の五か国に続いて、明治政府は以下の国々と条約を結びます。
| 年(西暦/和暦) | 相手国 | 条約名・出来事 | 内容・備考 |
|---|---|---|---|
| 1869(明治2) | オーストリア=ハンガリー帝国 | 日墺修好通商航海条約 | 安政条約と同型。※1 |
| 1871(明治4) | ベルギー | 日白修好通商条約 | 「白耳義」 |
| 〃 | ドイツ帝国 | 日独修好通商条約 | プロイセン主導のドイツ統一後に締結。 |
| 1873(明治6) | デンマーク | 日丁修好通商条約 | 「丁抹」 |
| 〃 | スペイン | 日西修好通商条約 | 「西班牙」 |
| 1875(明治8) | スイス | 日瑞修好通商条約 | 「瑞西」 |
| 1878(明治11) | スウェーデン=ノルウェー連合王国 | 日瑞典修好通商条約 | 「瑞典」 |
| 1880(明治13) | イタリア | 日伊修好通商条約 | 「伊太利亜」 |
※1 オーストリアとの条約だけ“修好通商航海条約”と呼ばれるのは、英語原文に navigation が含まれていたため。実質的な内容は他国と同じ不平等条約。
どの条約も安政五か国と同じ形式で、治外法権と関税自主権の制限が盛り込まれていました。日本は「列強ほぼ全員」と対等でない関係を結ばされていたのです。こうしてオーストリアやスイスといった日本にとって遠い国とも、不平等な関係が始まっていきました。
補足:条約に用いられた国名の漢字表記まとめ
当時の外交文書や新聞には、以下のような漢字表記が使われていました。
- 墺太利亜(オーストリア)
- 白耳義(ベルギー)
- 独逸(ドイツ)
- 西班牙(スペイン)
- 丁抹(デンマーク)
- 瑞西(スイス)
- 瑞典(スウェーデン)
なぜ次々と不平等条約を締結したのか
日本は多くの国と同様の条約を結ばされていきましたが、なぜこんなにも次々と不平等条約が増えていったのでしょうか。
欧米列強の「横並び」意識
安政の五か国条約の相手国以外も、列強は互いに競い合うライバル関係にありました。
もしある国だけが突出した権益を日本から得れば、他国の立場が損なわれてしまいます。そのため「特定の国だけが有利にならないように」という思惑から、各国は横並びで同じ条件を日本に押しつけていったのです。
日本の事情 ― 孤立を避けたい新政府
一方の日本も、国際社会で孤立することを恐れていました。外交経験の浅い幕府から引き継いだ明治政府にとっては、諸外国と次々に条約を結ぶことが「近代国家として認められる道」だと考えられたのです。
結果的に、それは不平等条約をさらに積み重ねることにつながってしまいました。
欧州中堅国にとっての「ステータス」
また、オーストリアやベルギー、スイスのように、イギリスやフランスほどの植民地帝国ではない国々にとって、日本との条約締結は「自国も列強の一員だ」と示す手段でした。
アジアの新興国と修好通商条約を結ぶこと自体が、国際社会での体面を保つ「ステータス」になっていたのです。
こうして、欧米列強の横並び意識、日本の外交未熟さ、さらに欧州中堅国の面子という要素が重なり、日本は次々と不平等条約を結ばざるを得ませんでした。
それは日本の主権を縛る「国際条約ネットワーク」として、長く近代国家への足かせとなったのです。
条約改正への長い道のり
不平等を改めるため、日本は明治の初めから欧米諸国に交渉を重ねます。しかし成果を得るまでには半世紀以上かかりました。
岩倉使節団と改正交渉の失敗
1871〜73年に派遣された岩倉使節団は、欧米を歴訪して条約改正を求めました。
しかし各国の答えは冷たく、「日本はまだ近代的な法制度や裁判制度を整えていない」として拒否されました。
30年以上かけた改正
- 1894年 日英通商航海条約 → 治外法権撤廃の第一歩。
- 1899年 新条約発効 → 列強とようやく対等に近づく。
- 1911年 関税自主権の完全回復 → ここでようやく「不平等条約時代」が終わる。
交流史から得られる新しい視点
オーストリアやスイス、イタリアといった遠いヨーロッパの国々と日本の交流は、実は明治時代の「不平等条約」から始まりました。
そこから半世紀以上の努力を経て、日本は列強と対等な関係を築けるようになります。そして現代の私たちにとっては、これらの国々は観光・文化・経済の分野で友好的なパートナーです。
「オーストリア」と「オーストラリア」
ニュースで国名を見かけたとき、あまり馴染みのない遠い国の事だと感じる事もあるでしょう。日本では「オーストラリア」と「オーストリア」の違いが分からないという人も少なくないようです。
そんな時に、「不平等から始まった交流史」の知識は役に立ちます。
「オーストリア」は、明治時代に日本が不平等条約を結んだヨーロッパの列強国のひとつで、ドイツの南東に位置します。モーツァルトやシューベルトなど音楽の都ウィーンを思い起こすとイメージしやすい国です。
一方「オーストラリア」は南半球の大陸国家で、19世紀までイギリスの流刑植民地でした。その後は金鉱発見によって移民が急増し、現在は英語を公用語とする多文化社会になっています。
名前は似ていますが、歴史も文化も全く違う二つの国。「Austria=音楽」「Australia=カンガルー」と覚えておけば、混同を防げるかもしれません。
関連記事:ビールの歴史から得られる視点
日本の外国との交流史を知ると、現代の「国」の見え方も変わってくるものです。
私たちはBeer(ビアー)のことを「ビール」と呼びますが、これはオランダ語を基にした外来語です。ペリーは幕府にビール(エール)を献上しましたが、日本人の口には合わず定着しませんでした。明治時代に入ってから、日本はドイツ人技師を招き、ラガービールの製法を学ぶことになります。
アメリカ・オランダ・ドイツとの交流が刻まれたビールの物語からも、外交史と同じように現代社会を見る新しい視点が得られます。