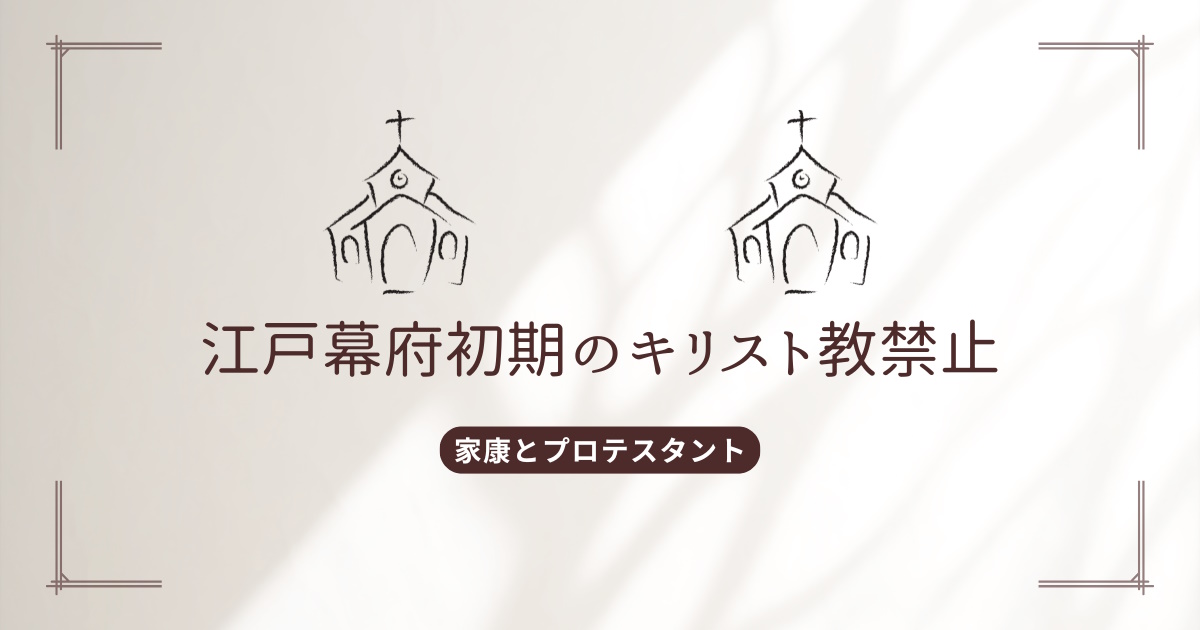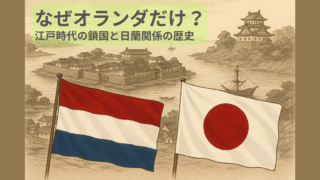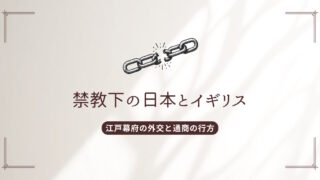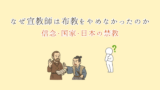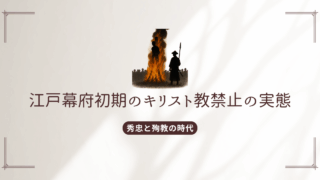💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
徳川家康がキリスト教を禁じたのは、信仰への拒絶ではなく、国家を守るための選択でした。
布教の裏に潜む植民地化の危険を見抜き、外交方針を転換した家康。世界と距離を取り、平和を保った日本の200年の始まりを、彼の決断から考えます。
本記事では以下の流れで詳しく解説しています。
- 禁教前の時代背景解説
→ 宗教に寛容で交易関係を模索した時期 - 禁教への転換
→ 警戒を強めた事件と、全国禁教へ踏み切った背景
「江戸幕府でキリスト教が禁止された背景」の節以降で解説
形骸化した伴天連追放令
豊臣秀吉が出した「伴天連追放令(1587年)」は、日本史上初のキリスト教禁令として知られています。しかし、実際にはこの法令は政治的布告に過ぎず、制度として徹底されたものではありませんでした。
秀吉が死去した1598年以降、その影響力は急速に薄れ、形骸化していきます。
伴天連追放令は、南蛮(ポルトガル)勢力の支配下にあった長崎の港を取り戻し、日本人が奴隷として海外に売られることを止めるための、国防的措置でした。
伴天連追放令についての詳細は以下記事をご覧ください。
💡関連記事:伴天連追放令の背景 ― 外国勢力に対する秀吉の決断
秀吉死後の「追放令」の実態
秀吉の死後、キリスト教徒への取り締まりも次第に緩くなっていきました。形式上は「伴天連追放令」が存続していましたが、実際にそれを執行する体制は存在していませんでした。
長崎など一部の奉行所では引き続き宣教師や信者を監視していましたが、それは現地レベルの治安維持にとどまっていました。
黙認されていた布教活動
1600年前後の日本では、キリシタン大名の領地や港町を中心に、宣教師が再び活動を再開していました。長崎、平戸、有馬、京都などには信者が集まり、公開の場でミサが行われることも珍しくありませんでした。
禁教令があっても、現実には「黙認状態」だったのです。
この時期、日本におけるキリスト教の信徒数は20万人を超えていたとも言われています。
キリシタン大名の生き残り
秀吉の伴天連追放令は、宣教師による布教や政治介入を抑えるための国防的措置であり、信仰そのものを禁じたわけではありませんでした。政治リスクのある大名は信仰が禁止されますが、庶民の信仰までは禁止されていませんでした。
そのため、キリシタン大名の中には、有馬晴信、小西行長などのように、一時的に勢力を失っても領民の信仰を守ろうとする者もいました。
国外追放されたキリシタン大名 ー 高山右近
伴天連追放令の発布後も宣教師を庇護し、信仰を棄てることを拒んだ高山右近は、摂津高槻十二万石の大名としての地位を失い、実質的に“改易”となりました。その後は各地のキリシタン大名――加賀の前田家や肥前の有馬家など――を頼って転々としながら、信徒たちの精神的支柱として知られる存在になっていきます。
徳川家康が全国禁教令を出した1614年には、家族とともにマニラへ追放され、翌1615年に現地で病没しました(享年六十三)。
| 年 | 政権 | 出来事 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 1587年 | 豊臣秀吉 | 伴天連追放令により改易(領地没収) | 国内政治措置(布教禁止) |
| 1614年 | 徳川家康 | 全国禁教令により国外追放 | 宗教弾圧・信仰排除 |
家康、プロテスタントを知る
天下統一後の徳川家康は、外国との交易に強い関心を持っていました。彼にとってキリスト教は、信仰の問題というよりも「貿易に付随する政治要素」でした。
秀吉の追放令をそのまま踏襲することもなく、むしろ外国人を積極的に受け入れて経済発展を目指していたのです。
オランダ船リーフデ号の漂着(1600年)
1600年、豊後国臼杵に一隻のオランダ船「リーフデ号」が漂着しました。

この船に乗っていたのが、のちの三浦按針(ウィリアム・アダムス)とヤン・ヨーステンです。
- ウィリアム・アダムス(三浦按針)ー(イギリス人)
- ヤン・ヨーステン(Jan Joosten)ー(オランダ人)
彼らは、当時家康が滞在していた大阪や駿府に召し出され、ヨーロッパの事情を詳しく説明しました。
三浦按針とヤン・ヨーステン ― 家康に仕えた異国の航海士
三浦按針は航海術や造船技術に秀で、外交・軍事の助言者として活躍しました。一方のヤン・ヨーステンは、通訳、海外情勢の情報提供などを担い、実務的な外交支援を行いました。
二人は、ヨーロッパ世界の構造を日本に伝える貴重な存在だったのです。
家康は両者を厚遇し、按針には三浦郡(神奈川県横須賀市付近)を与え、ヤン・ヨーステンには江戸に屋敷地を与えました。現在の東京・八重洲(Yaesu)は、ヤンの名前「ヤヨス(Yayosu)」に由来するといわれています。
カトリックとプロテスタント ― 方針の違い
家康は三浦按針とヤン・ヨーステンから、スペインやポルトガルが布教と征服を結びつけたカトリック勢力である一方、オランダやイギリスは貿易を重視するプロテスタント国家であることを学びました。
| 宗派 | 日本の関係国 | 方針 |
|---|---|---|
| カトリック | スペイン・ポルトガル | 布教と征服 |
| プロテスタント | イギリス・オランダ ※1 | 貿易を重視 |
※1 同じプロテスタントでも、イギリスは国王が頂点に立つ国教会、オランダは信仰の純粋さを重んじるカルヴァン派と、性格がやや異なっていました。
カトリックとプロテスタントは、ヨーロッパでは宗教を背景に激しく対立し、ときには戦争を起こすほどの関係にありました。
この頃のオランダは、スペインからの独立戦争の最中です。
カトリックの厳しい宗教弾圧に反発して軍を起こし、独立を宣言しました。イギリスとオランダは軍事同盟を結んで、スペインに対抗していました。
「宗教よりも商業」を優先する国家となった当時のオランダの宗教観については、以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:江戸時代のオランダの宗教観 ― スペインから独立した国家の選択
カトリック勢力の「植民地政策」
カトリック勢力であるスペインやポルトガルは、まず宣教師を送り、信仰を広め、のちに軍を派遣して現地を支配する――。
南米やフィリピンで実際に行われたその手法は、家康にとって強烈な警告になりました。
この知識は、後の外交判断――すなわち「カトリックを排除し、商業国家と手を結ぶ」という方向性――を決定づける重要な要素となりました。
オランダとイギリスとの交易 ― イギリスが撤退した理由
1609年には、三浦按針とヤン・ヨーステンの仲介によって、オランダ東インド会社(VOC)が平戸に商館を設立します。二人はそれぞれ外交顧問と通訳の立場から交渉を支え、日本が初めて「布教を伴わない貿易関係」を築くきっかけとなりました。
1613年、イギリス東インド会社の商館長ジョン・セーリスが来日し、家康から正式な通商許可(朱印状)を得ました。その結果、長崎県の平戸にイギリス商館が設立され、オランダ商館と並んで活動を始めました。
しかし、このイギリス商館はわずか十数年で撤退することになります。その最大の理由は、日本貿易がまったく採算に合わなかったことでした。
オランダがすでに貿易網を掌握していたうえ、日本で取引できる品目も限られており、イギリス側は思うように利益を上げられなかったのです。その結果、1623年(元和9年)にイギリス商館は閉鎖され、イギリスは自ら日本から撤退しました。
こうして、同じプロテスタント勢力でありながら、イギリスは去り、オランダだけが残るという形が定まりました。
オランダ・イギリスと江戸幕府の歴史
イギリス、オランダと日本の江戸時代の交流については、それぞれ以下の記事に詳しくまとめています。オランダとは長く友好的な関係が続き、イギリスは撤退後に再開を申し出ますが、江戸幕府に拒否されるという歴史を辿ります。
スペインとの接触 ― 通商関係の模索
家康はポルトガルだけでなく、スペインとも通商関係を築こうとしていました。
当時のスペインは、マニラ(フィリピン)を拠点とする海洋帝国であり、メキシコとの太平洋貿易で莫大な富を得ていました。オランダ・イギリスと対立しているカトリック勢力でもあります。
家康は、スペインと友好関係を結ぶことで、より広い国際貿易網を構築しようと考えたのです。
スペイン使節ビスカイノの来日(1611年)
1611年、スペインから使節セバスティアン・ビスカイノが派遣され、駿府で徳川家康・秀忠父子と謁見しました。(形式上は秀忠政権)
彼はスペイン王フェリペ3世の親書を携え、「日本とスペインの正式通商」を申し出ました。
しかし、彼の態度は日本側の礼法を軽視し、家康の心証を悪くします。

贈り物を粗末に扱い、金銀鉱山の所在をしつこく尋ねるなど、相手国の主権を無視する発言が多かったのです。
ビスカイノ、王の使節と称すといえども、辞儀あらず。言辞高し。物を贈るに礼を欠く。
ー 『駿府記』
さらに、彼の随行にはフランシスコ会やドミニコ会の宣教師が含まれており、通商の名目で再び布教を進めようとする意図が明らかでした。つまり、「布教は通商の前段階、通商は支配の前段階」であるという三浦按針の警告が、目の前の事実として裏付けられたのです。
| 国 | 主な布教組織 | 主な貿易ルート | 日本での活動拠点 |
|---|---|---|---|
| ポルトガル | イエズス会 | ゴア(インド) → マカオ → 日本 | 長崎(平戸・有馬など) |
| スペイン | フランシスコ会 ドミニコ会 | メキシコ(アカプルコ) → フィリピン(マニラ) → 日本 | 九州南部、江戸、京都など |
謁見に同席したオランダ人
史料『駿府記』やオランダ側の記録にも、「家康のそばにオランダ人の航海士がいた」との記述が見られます。名指しはありませんが、按針を指すと考えられています。
謁見前のスペインと日本の関係
スペインは家康と謁見していますが、それ以前に、秀吉もスペインと関係を持っています。
1596年のサン・フェリペ号の事件と、その後の二十六聖人の殉教事件は、両国にとって苦い経験となっていました。詳しくは以下の記事で解説しています。
💡関連記事:伴天連追放令の実態 ― サン・フェリペ号事件と二十六聖人の殉教
江戸幕府でキリスト教が禁止された背景
家康は慎重にカトリック勢力とも交易の道を模索し続けましたが、最終的にはキリスト教を禁ずる方策を打ち出します。
なぜ家康がその決断に至ったのか、その背景を確認します。
禁教の導火線 ― 有馬事件(1612年)
1612年(慶長17年)に起きた「有馬事件」は、禁教決定の直接的な引き金の一つでした。
事件概要 ー 不正を巡った商取引上のトラブル
スペイン領マニラから来航した商船との取引をめぐって、有馬家臣の岡本大八(おかもとだいはち)が私的な利益を得ようと不正を行い、商人との間で激しい争いを起こします。
この口論は次第に拡大し、有馬家臣がスペイン船の乗組員を殺害するという事件に発展しました。
スペインの反応 ― 宗教的圧力
マニラ総督をはじめとするスペイン当局やフランシスコ会の宣教師は、この事件を「単なる犯罪」ではなく“信徒への迫害事件”として扱いました。

「スペインの信者と修道士が、日本で不当に殺害された」という立場を取り、外交ルートを通じて幕府に以下のような「信仰を盾にした政治的圧力」をかけたのです。
- 加害者への厳罰要求
- 宣教師の安全保障
- 教会の活動再開の保証
事件後の調査で明らかになった事
事件後の調査で、岡本大八が幕府高官を装って賄賂を取っていたことが判明します。
有馬晴信は主君としての監督責任を問われ、同年に斬首。有馬家は改易となります。
また、事件後の調停や処理に、フランシスコ会の宣教師たちが深く関与していたことも明らかになります。彼らは宗教家でありながら、有馬家や岡本大八に政治的助言を与え、賄賂の仲介や外交文書の翻訳などにまで手を出していました。
宣教師に対する認識は、「宗教家」から「政治活動家・スパイ」へと改められます。
幕府による初めてのキリスト教禁制 (1612年)
この結果、家康は「宗教が貿易や外交に直接介入する危険性」を認識し、幕府直轄地(駿府・京都)に限定した禁教令(1612年)を出します。
この禁教令は、幕府による初めての「法的な禁制(布教禁止)」となりました。
慶長遣欧使節(1613年) ― 最後のチャンス
家康はそれでも慎重でした。
スペインとすぐに断交するのではなく、1613年に仙台藩主・伊達政宗を通じて支倉常長の慶長遣欧使節を派遣します。ビスカイノはこの使節に同行します。
すでに家康はスペインへの不信感を抱いていましたが、伊達政宗の希望により「通商路を開く最後のチャンス」として支倉の派遣を許可しました。家康としては、「もしスペインが真に友好的であれば、通商を認めてもよい」という姿勢を保っていたのです。
禁教を破って布教する宣教師たち (1613年~1614年初頭)
直轄地での布教行為は幕府によって禁じられていましたが、スペイン系修道会――とくにフランシスコ会・ドミニコ会――の宣教師らは禁令を無視し、京都や江戸でも再び布教を拡大します。彼らは表向き「使節随行員」や「通商関係者」を装いながら、各地で信者を増やしていたのです。
1614年7〜8月頃には、キリシタン関係者の摘発・国外追放命令も行われますが、宣教師たちは潜伏して布教を継続します。幕府に従わない彼らを、家康もさすがに許すことが出来なくなります。

関連記事:なぜ宣教師は布教をやめなかったのか
日本に滞在していた宣教師たちが、禁止されている布教をやめなかったのはなぜなのか。
彼らの信念や国家の思惑などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
悪意を持った侵略の先兵として語られることが多い当時の宣教師たちですが、彼らには彼らの信じている「正しさ」がありました。関心のある方は是非ご覧ください。
スペイン・マニラ当局との外交不信
家康は、支倉常長をヨーロッパに派遣する際、スペイン領マニラの総督宛てに通商を求める書簡を送っていました。
しかし、総督はこれを無視し、スペイン側は布教活動を優先させる姿勢を崩しませんでした。
この外交上の冷遇も、家康の不信感を決定づけました。
キリスト教の全面禁止へ (1614年 11月)
結果として、江戸幕府は支倉使節の帰国を待つまでもなく、1614年に全国禁教令を発布します。
この禁教は、宣教師は追放、日本人信徒の棄教を命令という厳しい内容です。
この段階で、キリスト教は「国禁宗教」となりました。
家康は1605年に将軍職を秀忠に譲っていますが、禁教令の草案や布告文の作成には家康の意向が色濃く反映されています。実際、1614年の全国禁教令には「駿府御判物」(家康の印判)が使われた写本が残っています。これは、家康が実質的な発令者であることを示しています。
慶長遣欧使節の顛末 ー 謁見と帰国
支倉常長は、1615年にスペイン(セビリア)へ到着し、1616年にローマ教皇パウルス5世と謁見するという外交的成功を収めました。
しかし、そのころ日本では1614年に禁教令が発布され、1616年には家康も死去してしまいます。
支倉が1620年に帰国したとき、すでに日本ではキリスト教は完全な禁止宗教となっており、彼の使命は無意味になっていました。帰国後、支倉自身も「キリシタン」として警戒され、仙台藩でも孤立気味に生涯を終えます。
江戸幕府のキリスト教禁止の意味
江戸幕府はキリスト教を禁止しましたが、それは宗教を否定した訳ではありません。
宗教を理由にした「悪影響」を排除したに過ぎないのです。
また、この禁教政策はスペイン・ポルトガルへの最終的な不信表明であり、同時に「布教を伴わない国との交易」を明確に選んだ外交方針でもありました。
関連年表:
【年表】江戸時代初期のキリスト教禁止の背景と実態 ― 家康から秀忠の時代まで
家康から秀忠の時代までの流れを、時系列で整理しています。
宗教が禁止されても続く友好関係
プロテスタントもキリスト教ですが、日本がキリスト教を禁止にした後もプロテスタント国であるイギリス・オランダとは友好的な交易・交流が続けられます。
(イギリスは前述のとおり、後に日本市場から撤退)
プロテスタント勢力と当時の日本には、現実主義的な共通点がありました。
・相手の思想に干渉しない
・互いの利益を最大化する
宗教や価値観の違いで分断が生まれる現代にこそ、彼らの「距離を保った共存」の知恵には学ぶべき点があるのかもしれません。
日本における「信教の自由」と「平和」の関係
日本は「信教の自由を制限」するかわりに、17世紀から19世紀にかけて、世界でも稀に見る長期の「平和」を手にしました。
しかし、19世紀に入って「信教の自由」を保証し、西洋と歩調を合わせていった日本は、やがて「世界戦争」という大きな苦難を経験します。
家康の禁教の歴史は、その両立の難しさを静かに語りかけているようにも思えます。
関連記事:キリスト教は禁止から弾圧へ
家康・秀忠の時代、国家より神を優先するキリスト教を禁止する決断をしました。
続く家光の時代、キリスト教禁止は制度化されていき、踏み絵などの弾圧的な手段も取られるようにもなっていきます。
以下の記事では、江戸時代のキリスト教禁止の制度を通じて、国家秩序と信仰の自由の両立という、現代にも続く課題を考えます。
また本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。