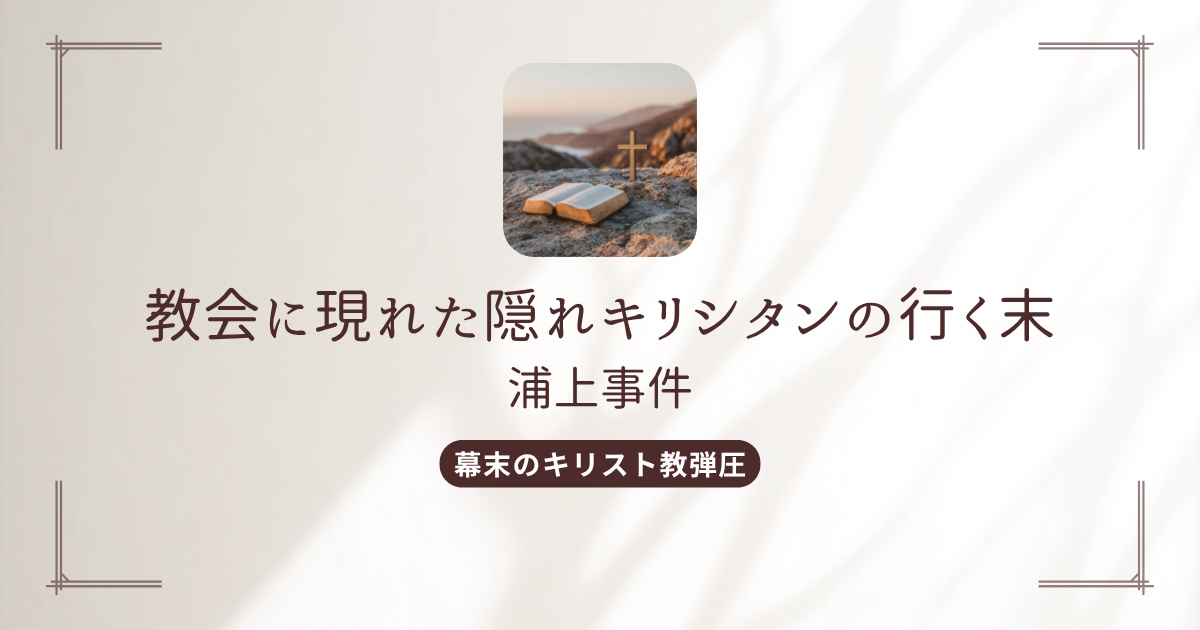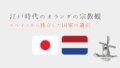💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
ペリー来航をきっかけに日本が開国すると、欧米との不平等条約の中で「外国人の信教の自由」が認められました。しかしその自由はあくまで「外国人に限られた」ものであり、日本人にとってキリスト教は依然として禁止されたままでした。
そんな中、長崎に建てられた一つの教会を舞台に、歴史を揺るがす出来事が起こります。
不平等条約で揺らぐキリスト教の禁止
1858年に結ばれた安政の五カ国条約によって、日本は外国人居留地の設置を認め、彼らには宗教活動の自由が保障されました。日本政府(幕府)は条約によって外国人の宗教活動を認めざるを得ず、居留地内での教会建設を拒否することもできなくなっていました。
💡関連記事:禁教の崩壊序章 ― ペリー来航と不平等条約の宗教条項
横浜や長崎などの居留地では次々と教会が建てられ、欧米人たちは公然と礼拝を行いました。
その一つが、1864年に完成した長崎・大浦天主堂です。
設計はフランス人宣教師によるもので、「日本二十六聖人殉教者」に捧げられた教会でした。
しかしその建設当初、日本人がこの教会に入ることは固く禁じられていました。
教会に現れた「隠れキリシタン」
1865年3月17日、長崎の大浦天主堂に、十数名の日本人女性が訪れました。
応対したのは、フランス人宣教師プティジャン神父です。
女性たちはそっと神父に近づき、こう告げました。
「わたしたちは、あなたと同じ心を持つ者です。」

プティジャンは驚きます。
250年以上前に絶えたと思われていたキリスト教の信仰が、日本に密かに残っていたのです。
その人々は長崎郊外の浦上村に暮らしており、江戸初期の禁教令以来、仏教徒を装いながらも、密かに祈りと儀礼を守り続けていました。
こうして起きた「信徒発見」は、沈黙の250年を破った歴史的な出来事となりました。
「隠れキリシタン」は、現在では「潜伏キリシタン」と呼ばれます。
2018年に世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を機に、より実態を正確に表す言葉として使われるようになりました。
・隠れキリシタン:弾圧を避けて信仰を“隠した”キリシタン
・潜伏キリシタン:禁教のもとで、信仰を密かに守り続けた集団
フランスの驚きと歓喜 ―「東洋のルルド」
この報告はすぐにフランスへと伝えられ、世界のカトリック社会を震撼させました。
プティジャンが送った報告書はパリ外国宣教会を通じてヨーロッパ中に広まり、ローマ教皇ピウス9世もこれを「神の摂理」として称えました。
当時のフランスでは、1858年に少女ベルナデットが聖母マリアを見たとされる「ルルドの奇跡」が話題となっており、信仰復興の熱気に包まれていました。

そのため、日本で250年の沈黙を経て信仰が甦った出来事は、まさに「東洋のルルド」として世界的に報道されたのです。
フランス国内では「信仰が再び息を吹き返した奇跡」として大きな感動を呼び、宣教会の士気を高めました。
しかしその一方で、プティジャン本人は深い懸念を抱いていました。日本では依然として禁教令が有効であり、この知らせが幕府に知られれば、信徒たちが危険にさらされることを理解していたのです。
幕府の判断 ― 外国を警戒しつつ禁教維持
信徒発見の報はすぐに長崎奉行所に届き、幕府の中央にも報告されました。
当時、長崎奉行を務めていたのは小笠原長行。
外交問題にも通じた人物でしたが、彼はこの件を「非常にまずい」と感じていました。
江戸では老中の稲葉正邦や外国奉行の竹内保徳らが協議を行い、次のような方針を決めます。
「禁教を維持する。ただし、外国を刺激するような処刑は避ける。」
幕末のキリスト教再弾圧 ― 浦上四番崩れ
浦上村の信者たちは「流罪」という形で処分されることになりました。
幕府は信仰を“折る”ことを目的に、浦上の信徒約3400人を全国の藩に分散して送り込み、強制的な改宗指導を命じたのです。
| 年 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1865年(慶応元年) | 信徒発見 | 浦上村の信徒が大浦天主堂を訪れ、 プティジャン神父に信仰を告白。 |
| 1865〜1866年 | 幕府の調査・取り調べ | 長崎奉行が信徒の名簿を作成。 取り調べを実施。信仰放棄を迫る。 |
| 1867年(慶応3年) | 浦上四番崩れ(本格弾圧) | 幕府が信者約3400人を摘発。 全国20藩に流配。 死刑は行わず、改宗を強要。 |
直接の処刑は行われなかったものの、過酷な拘禁や拷問によって約600人が命を落としたとされます。それは「殺さずに殺す」ような弾圧でした。
「浦上四番崩れ」の“崩れ”とは、江戸時代の行政用語で「一団が摘発され壊滅した事件」を指します。つまり「浦上の信徒共同体が当局によって崩された」という意味を持ち、信仰共同体の崩壊を象徴する言葉として記録に残っています。
幕府はなぜキリスト教を再度弾圧したのか
幕末の弾圧は、信仰への敵意からではなく、「法を守る」という体制原理に基づいていました。
江戸初期から続く禁教令は依然として有効であり、浦上の信徒発見はその「違法行為」として扱われたのです。幕府にとって法は秩序そのものであり、これを破れば体制の根幹が揺らぐと考えられました。
つまり、弾圧は宗教的ではなく行政的な行動でした。
信仰よりも法を優先する姿勢――それが、幕末の幕府を最後まで動かしていた原理だったのです。
幕末動乱のただ中で
この浦上事件は、幕末の政治的混乱と同時進行で起こっていました。
| 年 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 1858年 | 日米修好通商条約 (安政の五カ国条約) | 外国人居留地の設置と、 外国人の「信教の自由」を容認。 |
| 1859年 | 横浜・長崎・函館が開港 | 外国人宣教師が来日し、 居留地内に教会建設を開始。 |
| 1862年 | フランス人宣教師 プティジャン来日 | 長崎で宣教活動を準備、 大浦天主堂の建設に着手。 |
| 1863年 | 八月十八日の政変 | 長州藩が京都から追放され、 国内政治が動揺。 |
| 1864年 | 大浦天主堂完成 | 外国人向けの教会として 長崎に建設される。 |
| 1865年 | 信徒発見 | 浦上の隠れキリシタンが プティジャン神父に信仰を告白。 |
| 1865〜1866年 | 幕府による調査・取り調べ | 信徒の身元調査と取り締まりが進む。 |
| 1866年 | 第二次長州征討・薩長同盟成立 | 政情不安が高まり、幕府の統制力が低下。 |
| 1867年 | 浦上四番崩れ | 約3400人の信徒が摘発され、 全国の諸藩に流罪処分。 |
| 同年 | 一橋慶喜が将軍に就任 | 幕府体制の最末期、 弾圧は外交・治安維持の名目で続く。 |
浦上事件は、幕末時期に武力や権力だけでなく、「思想と信仰の自由」をめぐる闘いが同時に進んでいたことを示す象徴的な出来事でした。
信仰に揺れる「もう一つの幕末」
幕末というと、薩長同盟や倒幕戦争など、政治や軍事の動きに注目が集まりがちです。
しかしその裏では、国家と宗教、統制と自由のせめぎ合いが続いていました。
浦上事件は、江戸初期から続いた禁教体制の最後の抵抗であり、
同時に“信仰が国家を超えて生き延びた”ことを証明する出来事でもありました。
日本流にアレンジされたキリスト教
長い禁教の時代、潜伏キリシタンたちは信仰を守るために独自の工夫を重ねました。
マリア像を仏像や観音像に見立て、地蔵の前でキリストに祈りを捧げるなど、仏教の形式を借りながら信仰を続けたのです。祈りの言葉(オラショ)はポルトガル語が変化し、意味がわからなくなっても口伝で受け継がれました。
こうして彼らの信仰は、教義よりも「先祖の祈りを絶やさないこと」を重んじる、日本的な信仰形態へと姿を変えていきました。それは外来宗教の模倣ではなく、日本人の心と生活に根づいた、もう一つのキリスト教だったのです。
潜伏キリシタンは英雄?弾圧は悲劇?
幕末に再び姿を現した潜伏キリシタンたちは、禁教の中で信仰を守り続けた人々でした。その歩みは確かに奇跡的であり、現代の私たちの目から見ても、その信念と忍耐には心を打たれるものがあります。
しかし、当時の価値観で見れば、彼らは「法に背いた人々」でもありました。江戸幕府の禁教令は厳然とした国家法であり、信仰の有無にかかわらず、それを破ることは犯罪と見なされたのです。弾圧は悲劇であり、信徒発見は美談として語られがちですが、実際には「ルールを破って裁かれただけ」ともいえます。
人の作った法と、神への信仰がぶつかるとき、どちらを優先すべきなのか――。
潜伏キリシタンの歴史は、私たちに「正義の法」とは何かを、静かに問いかけているのかもしれません。
この記事は、「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本がキリスト教を禁止にした歴史を通じて、多文化共生社会ともいわれる現代を見つめ直す、新しい視点を見出します。