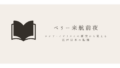明治期の日本では、「脚気(かっけ)」という病が多くの人命を奪っていました。
特に軍隊では深刻で、日清・日露戦争期の陸軍では、戦死者を上回る数の脚気患者が出たとも言われています。
この脚気に対して、当時の日本海軍で決定的な成果を挙げた人物が、高木兼寛です。
彼は脚気の原因を特定できないまま、食事内容を変えることで脚気をほぼ抑え込むという結果を出しました。
しかしこの判断は、当時の医学の常識から見れば、きわめて異質なものでした。
なぜ高木は、その「前提」を疑うことができたのでしょうか。
高木兼寛とは、何をした人物なのか
まずは、高木兼寛が何を成し遂げた人物なのかを整理しておきます。
日本海軍に蔓延していた脚気という病
脚気は、手足のしびれや脱力、心不全などを引き起こす病気です。
明治期の日本では特に都市部や軍隊で多発し、「近代化の病」とも呼ばれていました。
当時は、脚気の原因は分かっていませんでした。
細菌による感染症ではないか、あるいは風土病ではないかと考えられており、決定的な説明は存在しませんでした。
食事改善によって脚気を抑え込んだ海軍軍医
高木兼寛は日露戦争(1904–1905)時には、日本海軍の軍医総監として、
海軍医療全体の方針に責任を持つ立場にあった人物です。
高木は、軍医総監に着任する(1898年)以前から、
一人の海軍軍医として、長期航海中の兵士たちの脚気発生率を詳細に観察していました。
その結果、航海条件がほぼ同じであっても、食事内容によって脚気の発生率が大きく異なることに気づきました。
そこで高木は、白米中心の食事に麦飯や副食を加えるという改善を行います。
すると、脚気の発生は劇的に減少しました。
この成果によって、日本海軍では脚気がほぼ克服されます。
なぜその成果は「非常識」に見えたのか
問題は、この成果が医学的に説明できなかったことです。
高木は脚気の原因物質を特定したわけでも、理論を構築したわけでもありません。
ただ、「食事を変えたら結果が変わった」という事実を示しただけでした。
当時の医学界から見れば、それは「理由の分からない成功」であり、科学的とは言い難いものでした。
なぜ「脚気」は医学の常識を突き崩したのか
高木の判断が異質に見えた理由は、当時の医学が依拠していた前提にあります。
当時の医学が前提としていた脚気感染症説
19世紀後半の医学では、病気は病原体によって説明されるべきだと考えられていました。
細菌学の発展により、多くの感染症が解明されつつあった時代です。
脚気についても、同じ枠組みで理解しようとするのは、きわめて合理的でした。
日本へのペスト(黒死病)の上陸は日清・日露戦争の間の出来事です。
ペスト防疫については、以下の記事で詳しくまとめています。
💡関連記事:ネズミを捕まえろ!日本と世界を襲ったペストの歴史
なぜ理論は、現実を説明できなくなったのか
しかし現場では、その理論では説明できない事実が積み重なっていきます。
感染症を想定した対策を講じても、
脚気の深刻な状況に、明確な改善は見られませんでした。
同じ船、同じ航路、同じ環境で生活しているにもかかわらず、
食事の内容が違うだけで、脚気の発生率が明確に変わる。
理論は正しく見えても、現実がそれに従わない。
この乖離が、医学の前提そのものを揺さぶっていきました。
高木兼寛は、なぜ医学の前提を疑えたのか
高木が前提を疑えた理由は、個人の性格や直感だけでは説明できません。
その背景には、いくつかの構造的な要因がありました。
日本とイギリス、二つの医学文化
高木は日本で医学を学んだ後、イギリスに留学しています。
そこでは、臨床や統計を重視する海軍医学、公衆衛生の考え方に触れました。
理論の完成を待つよりも、人命を守るために有効な手段を先に採用するという姿勢は、英国海軍医学の特徴でした。
ドイツで医学を学んだ森鴎外(日本陸軍)は理論重視で、高木とは対照的な姿勢でした。
脚気を感染症として扱った陸軍では、結果的に多くの犠牲者がでることになります。
💡関連記事:常識はときに人を殺す ― 森鴎外と脚気の教訓
壊血病対策という「理論なき成功例」
明治時代の日本では脚気が深刻な被害をもたらしていましたが、
それより以前、イギリス海軍では壊血病に長く苦しめられていました。
高木がイギリスに留学していた時代、
壊血病の原因は依然として特定されていませんでした。
しかしイギリス海軍では、柑橘類を摂取するという対策が、原因不明のまま制度化されていました。理由は分からなくとも、効果があることは明白だったからです。

ライミー と呼ばれたイギリス海軍の水兵
この「説明できなくても正しい判断はあり得る」という前例は、高木の思考の土壌になっていたと考えられます。
壊血病はビタミンCの欠乏症で、長い船旅をする航海士たちを苦しめていました。
💡関連記事:壊血病はどこいった? ― 今、そこに在るビタミンC
現場責任者という立場
もう一つ重要なのは、高木が現場で判断しなければならない立場にあったことです。
判断を先送りすれば、確実に兵士が死ぬ。
この状況では、「間違えない選択」を待つこと自体が、最大のリスクになります。
高木は医学を否定したのではありません。
医学の前提が、現実に適用できなくなった瞬間を、直視したのです。
結果を重視する海軍という組織
日本海軍は、長期航海という特殊な任務を前提とした組織でした。
一度出港すれば、途中で方針を修正することは容易ではありません。
そのため、理論の完成を待つよりも、「結果として人命が守られるかどうか」が重視される傾向がありました。
高木の食事改善策が採用された背景には、こうした海軍の実務的・結果主義的な判断基準があったと考えられます。
高木の問いに答えた科学
高木兼寛は、脚気の原因を説明する理論を持っていたわけではありません。
彼が示したのは、「この前提では説明できない」という事実でした。
その問いに、後の科学はどのように答えていったのでしょうか。
従来の栄養の常識
当時の栄養学では、栄養とは主に「量」の問題でした。
たんぱく質・脂質・炭水化物を十分に摂取すれば、人は健康でいられると考えられていました。
白米中心の食事は、むしろ合理的で先進的なものと捉えられていたのです。
ビタミンが変えた栄養の世界
20世紀初頭、栄養に「微量だが不可欠なもの」が存在することが、次第に明らかになっていきます。
高木が実証によって示した「欠けている何か」は、
1910年、鈴木梅太郎によって、
米ぬかに含まれる有効成分として、科学の言葉で示されることになります。
その後、世界各地で同様の性質を持つ物質が見出され、
Vital amine(生命に必須なアミン)という言葉から、
「ビタミン」という名称が生まれました。
鈴木梅太郎が発見した「オリザニン」は、後にビタミンB₁と呼ばれるようになります。
高木が実証によって示した「欠けている何か」は、
ここで初めて、「栄養素」という科学の言葉で説明されることになりました。
私たちは、どんな前提を疑えていないのか
高木兼寛の判断は、医学を破壊したものではありません。
むしろ、医学が更新されるための条件を示したものでした。
専門性が高くなるほど、前提は見えにくくなります。
正しいと信じてきた枠組みほど、疑うことは難しくなります。
前提を疑うことは、否定や反抗ではありません。
現実に合わせて、知を更新する行為です。
脚気という病が突き崩したのは、医学そのものではなく、
「正しさは常に通用する」という思い込みだったのかもしれません。
栄養や脚気に関心のある方には、以下のような記事もオススメです。