普段の生活で食べる「食べ物」全般に関する記事です。現代の生活の知恵や雑学だけでなく、食べ物の由来や歴史などについてまとめている記事も含まれます。
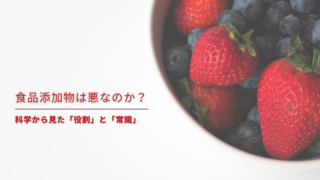 社会
社会 食品添加物は悪なのか? ― 科学から見た「役割」と「常識」
食品添加物は本当に「体に悪い」ものなのでしょうか。酸化防止剤や香料、安定剤、乳化剤を例に、食品添加物の役割と栄養的な意味を科学的な視点から整理し、私たちの常識を見直します。
 社会
社会 人はなぜ白米を食べ続けるのか ― 非合理の中の合理「おかず文化」
白米は栄養を失った「非合理」な食べ物。それでも日本人が白米を食べ続けるのは、おかず文化という新たな合理が生まれたから。脚気の歴史と共に、白米食が定着した背景をわかりやすく解説します。
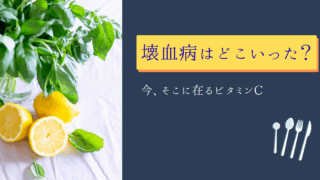 社会
社会 壊血病はどこいった? ― 今、そこに在るビタミンC
かつて致命的だった壊血病は、なぜ現代ではほとんど見られないのか。歴史と科学の視点から、ビタミンCの役割と現代の食生活に潜む「見えないビタミンC」を分かりやすく解説します。
 言語
言語 「妻」は女性? ― 刺身のツマに残る語の記憶
刺身のツマに残る「妻」の語源を手がかりに、かつて性別中立だった「つま」という言葉が、どのようにして「既婚女性」を指す語義へと変化したのかをわかりやすく解説します。
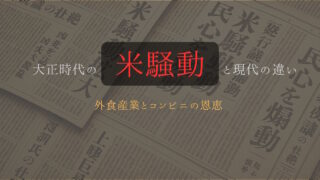 歴史
歴史 大正時代の米騒動と現代の違い – 外食産業とコンビニの恩恵
大正の米騒動は「米がなければ飢える」社会の象徴。外食産業や小麦食品が広がった現代日本との比較から、食料の安定供給と自給の重要性を問いかけます。
 社会
社会 野菜なしでも平気?栄養の“常識”は意外と新しい
野菜不足でも平気? 栄養学の常識は意外にも100年ほどの歴史しかありません。脚気や壊血病などの事例から、飽食時代に潜む偏食のリスクを考えます。
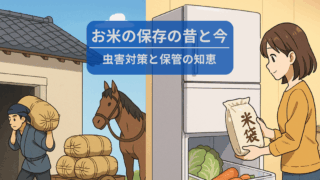 社会
社会 お米の保存の昔と今 ― 虫害対策と保管の知恵
虫やカビを防ぐお米の保管方法を徹底解説。江戸時代の米屋の工夫から現代の冷蔵保存まで、日常で活かせる保存の知恵を紹介。
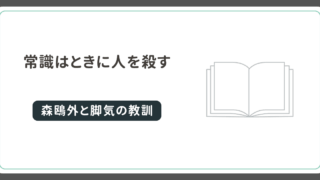 歴史
歴史 常識はときに人を殺す ― 森鴎外と脚気の教訓
森鴎外が陸軍軍医総監として下した脚気対策の判断は、科学の常識を信じたがゆえの悲劇でした。歴史を振り返り、常識や権威を疑う重要性を考えます。
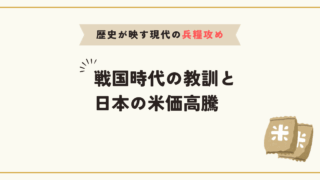 社会
社会 歴史が映す現代の兵糧攻め ― 戦国時代と現代の米価高騰比較
日本の米価高騰を「現代の兵糧攻め」と捉え、戦国時代の教訓から備蓄米や輸出政策の課題を考え、市民の監視の重要性を提起します。
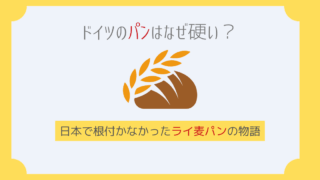 社会
社会 ドイツのパンはなぜ硬い?──日本で根付かなかったライ麦パンの物語
ドイツの硬いライ麦パンと日本の柔らかいパン文化の違い、歴史的背景や原料、定着しなかった理由をわかりやすく解説します。