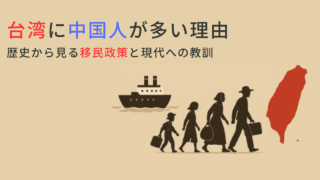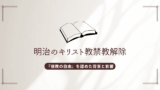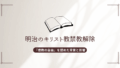💡この記事は、「日本とオランダ特集」の一部です。
アンボイナ事件は、オランダとイギリスの対立として語られることが多い出来事です。
しかしその背景には、宗教観やアジア情勢、そして日本との意外な結びつきがありました。
近世の価値観を踏まえ、この事件が日蘭関係に与えた意味を整理します。
アンボイナ事件とは ― スパイス諸島で起きた拷問と処刑の衝撃事件
アンボイナ事件は、1623年にモルッカ諸島アンボイナ島で起きた、イギリス商館員と日本人傭兵が裁判の末に処刑された事件です。
モルッカ諸島は現在のインドネシアに位置し、クローブやナツメグの原産地として、歴史的に“スパイス諸島”とも呼ばれました。
オランダ東インド会社(VOC)が“陰謀の摘発”を理由に行いましたが、その実態は不当な拷問に基づく裁判で、後世には冤罪の可能性が高いと考えられています。
事件の概要:オランダが摘発した「イギリスの陰謀」
アンボイナ島は、当時オランダが香料(特に丁子:クローブ)の独占を目指していた拠点です。
そこにイギリス商館も進出していたため、島内は常に緊張状態にありました。
クローブは肉料理の臭み消しや防腐に使われ、当時はモルッカ諸島がほぼ唯一の原産地でした。
その希少性は極めて高く、ヨーロッパでは金や銀と同等の価値を持つ高級品とされ、ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリスといった列強が奪い合っていました。
1623年、VOCの現地司令官は「イギリスが砦を襲撃する計画を立てている」という情報を得たとして、イギリス商館員を次々と逮捕します。根拠は曖昧で、ほぼ疑心暗鬼に基づくものでした。
拷問による自白と、イギリス側の強い反発
逮捕されたイギリス人たちは、ムチ打ち、高温の水責め、指への圧迫具など過酷な拷問を受け、自白を強いられます。
その証言を根拠として、オランダは二十名以上を処刑しました。
イギリス側は強く抗議し、本国では“アンボイナの虐殺”として大問題になります。しかし東アジアでの軍事力は圧倒的にオランダが優位であり、イギリスは有効な報復ができませんでした。
“根耳に水”の事件 ― イギリスとオランダの勢力図
イギリス商館側には陰謀に心当たりはなく、彼らからすれば寝耳に水の事件でした。島内の勢力図を見ても、イギリスが武力で砦を落とすなど不可能に近い状況でした。
アンボイナ島には、堅牢なオランダの石造りの砦(カステル)があり、火器・兵力ともにVOCが圧倒的に優位でした。
一方のイギリスは、砦の外に木造の小規模な商館を間借りしているだけで、兵力も十数名程度に過ぎません。地の利も軍事拠点もないイギリスが、オランダの砦に挑む現実的な可能性はほとんどありませんでした。
イギリスではこの事件は「冤罪の悲劇」として長く記憶され、19世紀まで歴史教科書に載り続けるほどの深い衝撃を残しました。
事件の背景 ― 宗教と戦争が生んだ“カトリック恐怖”という土壌
アンボイナ事件を理解するには、オランダが抱えていた“宗教不信”、特にカトリックへの恐怖を押さえる必要があります。これこそが事件を過剰にさせた根本要因でした。
カトリック勢力(スペイン・ポルトガル)と戦争状態にあったオランダ
当時のオランダ共和国は、カトリック強国スペインとの独立戦争の最中にありました。
ポルトガルはスペインに併合されていた時代だったため、オランダにとってスペインとポルトガルは一体の敵勢力でした。
そのため、オランダはヨーロッパでの独立戦争と並行して、アジアでもスペイン・ポルトガル勢力と軍事衝突を繰り返していました。
- カトリック勢力=オランダの国家的敵
- 布教=侵略の前段階
- 宣教師=スパイの疑いが常につきまとう
こうした価値観が、VOCの現場判断にも濃厚に影響します。
オランダの宗教観やスペインとの独立戦争については、以下の記事で解説しています。
💡関連記事:江戸時代のオランダの宗教観 ― スペインから独立した国家の選択
疑われた日本人傭兵 ― 問題視された“宗教経歴”
アンボイナ事件では、VOCが雇っていた日本人傭兵も“陰謀の共犯”とされて処刑されました。
彼らはオランダ側の兵力であり、イギリス商館とは無関係でしたが、事件の過程で疑いの対象として巻き込まれていきました。
日本人傭兵は、当時の東南アジアでは高い戦闘力で知られ、VOCからも一定の信頼を得ていました。実際、バタヴィアや各地の拠点では、門番や護衛、急襲部隊など重要な任務を任されていました。
しかし同時に、彼らの宗教的背景(かつてポルトガル勢力の傭兵として働いた経験や、カトリック信仰との関わり)は、VOCにとって不安材料でもありました。
オランダ(VOC)は「商船に宣教師を乗せない」という規則を設けるほど徹底して宗教を排除した“非宗教的な商業国家”でした。
そのため、日本人傭兵の中にカトリックへの接点を持つ者がいる可能性は、スペイン・ポルトガルと戦争状態にあった当時のオランダにとって、決して軽視できない疑念として映ったのです。
つまり、日本人傭兵は「軍事的には最も頼りになる存在」である一方、「宗教的には最も疑われやすい存在」でもあったと言えます。
事件が“整理”したオランダの不安
アンボイナ事件は、現地司令官の過剰な判断や宗教不信が重なった結果として生じたと考えられています。
計画性を示す証拠はありませんが、結果としてVOC(オランダ東インド会社)が抱えていた不安材料のいくつかが、この事件を機に“整理”されていったことも確かです。
経済的側面:イギリス撤退で競争相手が消えた
当時、アンボイナ島を含むモルッカ諸島は、世界のクローブ供給の中心地でした。ここを押さえることは巨額の利益を意味し、イギリスはVOCにとって最大の競争相手でした。
事件後、イギリス商館は撤退を余儀なくされ、
スパイス貿易は事実上オランダの独占状態
になります。
宗教的側面:カトリックへの不安が“解消”された
日本人傭兵の中には、ポルトガル勢力と関わりを持った者や、かつてキリシタンだった可能性のある者もいました。スペイン・ポルトガルと戦争中のオランダにとって、宗教的に不確定な人材は不安の種でもありました。
事件では、拷問や誤訳が重なった中で“共犯”とされ、彼らも処刑されました。
これは意図的な排除とは断定できませんが、
宗教的に不安視されていた要素が結果的に取り除かれた
のは事実です。
軍事・統制面:混乱の中で生じた“整理”
アンボイナ島では、
- 砦の防備への不安
- VOC内部の指揮系統の混乱
- 現地司令官の焦り
などが重なり、平時よりも疑心が高まっていました。
事件を通じて、司令官の判断は「陰謀摘発」として正当化され、島内の統制は強化されます。また、イギリス撤退と日本人傭兵の不在により、VOC側の不安材料が相対的に減少しました。
結果として現地の緊張と混乱が“収束”した形になりました。
事件後のアジア情勢
アンボイナ事件は、アジア全体の勢力図にも大きな影響を与えました。
イギリス:東アジアからの撤退を加速させた
当時、イギリスは東アジアに十分な軍事力を投じられず、アンボイナ事件をめぐってオランダと争うだけの余力がありませんでした。インドに資源と兵力を集中させる方針が強まり、モルッカ諸島のような遠隔地でVOCと対立することは現実的ではなかったのです。
そのため、イギリスはモルッカ諸島から撤退し、日本(平戸商館)からも手を引いていきます。日本市場では先行していたオランダに優位を取られ、十分な利益が見込めない状況が続いていました。
| 年 | 出来事 | 備考 |
|---|---|---|
| 1609年 | オランダ商館が平戸に開設 | 後の長崎・出島移転につながる、日蘭貿易の起点 |
| 1613年 | イギリス商館が平戸に開設 | 国王ジェームズ1世の許可を受け、EICが進出 |
| 1623年 | アンボイナ事件 | イギリス・日本人傭兵が逮捕・処刑され、英蘭関係が急激に悪化 |
| 1623〜1624年 | 日本からイギリス商館が撤退 | 事件と収益悪化が重なり、日本市場から正式撤退 |
インドで大きな利益が出始めていたこの時期、軍事的にも不利なオランダと争うより、収益性の高いインドへの集中を選ぶ方が合理的と判断されました。
こうして、日本には最終的にオランダだけが残る形となります。
撤退したイギリスは、その後の1673年に日本との通商再開を申し入れてきますが、日本は宗教的な懸念からこれを拒否しました。
通商開始から撤退・再開拒否までの日英関係については、以下の記事にまとめています。
💡関連記事:禁教下の日本とイギリス ― 江戸幕府の外交と通商の行方
オランダ:勢力圏を拡大し、台湾へも進出
モルッカ諸島の独占を強化したオランダは、1620〜30年代には台湾南部にも進出し、東アジア海域での影響力を急速に高めていきました。のちに台湾拠点は、中国の政変(明→清)に伴い、1662年に明の遺臣・鄭成功によって攻め落とされ、撤退を余儀なくされます。
この頃のオランダは、世界最大の海運国として繁栄し、「オランダ黄金時代」と呼ばれる最盛期にありました。莫大な富が市民に蓄積し、証券取引や先物取引が発達したことで投機熱が高まり、やがて世界初のバブルとされる「チューリップ・バブル」が1630年代に発生します。
ポルトガル・スペイン:アジア圏の主導権を失っていった背景
16〜17世紀前半のアジアでは、かつてポルトガルとスペインが“先行勢力”として存在感を持っていました。
しかし、アンボイナ事件の頃には、両国の影響力は急速に低下していました。
理由のひとつは、新大陸運営に主要な資源を割く必要が生じたことです。
特にスペインはアメリカ大陸の銀山(ポトシ)や大規模植民地の統治に追われ、遠隔地であるアジアへの積極関与を維持できなくなっていきます。ポルトガルもインド洋・アフリカ沿岸の広大な海域を抱えており、限られた軍事力と財政ではアジア全域を支える余裕がありませんでした。
さらに、両国はカトリック勢力として宗教布教と一体化した経営を続けていましたが、これは宗教軋轢を嫌うアジア諸国(特に日本)との関係を悪化させる要因にもなります。その隙を突くように、宗教色の薄いオランダ・イギリスが台頭し、貿易主導権を奪っていきました。
オランダからも”安心”された江戸時代の日本
ここまでの流れを踏まえると、日本とオランダがなぜ安定した関係を築けたのかが見えてきます。
オランダの安心:キリスト教(カトリック)を禁止する日本
17世紀のアジアでは、
「カトリックを受け入れる国」=スペイン・ポルトガルの影響圏
と見なされていました。
しかし日本は、
- キリシタン大名の排除
- 布教禁止
- 宣教師追放
- 取り締まり強化
と、徹底した禁教を進めていました。
これはオランダからすれば「この国にカトリックの影響力は浸透していない」という最強の安心材料でした。
日本の安心:布教を行わないオランダ
日本にとっての利点も明確でした。
- オランダは布教を行わない
- 宣教師を乗せない
- 商業目的のみ
つまり、宗教的な脅威が全くない。
「宗教を嫌う国」と「宗教を禁止した国」が自然に結びついたという構図です。
日蘭関係に影響しなかったアンボイナ事件
日本にとってアンボイナ事件は、“遠い島での外国同士のトラブル”にすぎませんでした。
処刑された日本人浪人について幕府が情報を得ていた可能性はありますが、禁教政策の文脈では「問題視すべき事案」とは判断されませんでした。
当時は、主に東南アジア各地で働く日本人傭兵が多数存在しており、彼らが現地トラブルに巻き込まれる事例は珍しくありませんでした。
アンボイナ事件も、そうした数多い“海外での日本人関係事件”の一つとして処理されたと考えられます。
オランダと日本には、カトリックに対する“宗教不信”という共通点がありました。
そしてアンボイナ事件を経て、
オランダはモルッカ諸島と日本市場の“貿易独占”を確かなものにしていきます。
近世と現代の”信教の自由”
現代において「宗教の禁止」は重大な権利侵害とみなされます。
しかし、アンボイナ事件が起こった近世には、現在のような“信教の自由”という概念はまだ存在していませんでした。
宗教を禁止して得られた信頼
当時のオランダや日本にとって、「宗教(特にカトリック)=危険」という価値観は共有されたものでした。
そのため、日本がキリスト教を禁止したことは、むしろオランダからの信頼を高める結果につながっています。
現代の私たちから見ると、きわめて興味深い現象と言えるでしょう。
変化する国家と宗教、そして日本
やがてキリスト教(カトリック)は、軍事的な“国家宗教”から、個人が持つ“信仰”へと大きく姿を変えていきます。
日本も明治時代に入り、国際社会の中で新しい宗教観と向き合う必要に迫られ、最終的にはキリスト教の禁教政策に終止符を打つ決断をしました。
禁教解除の背景や影響について関心のある方は、是非以下の記事もご覧ください。