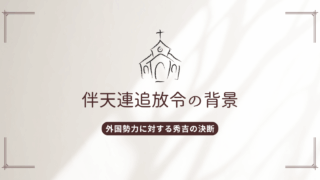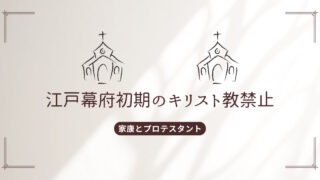💡この記事は、「日本のキリスト教禁教史特集」の一部です。
江戸幕府によるキリスト教弾圧が最も厳しくなった17世紀前半。
九州・島原と天草の地で、人々は絶望の果てに立ち上がりました。
それが、日本史上最大の一揆であり、唯一「キリスト教」を旗印に掲げた反乱――島原の乱です。
信仰と飢えが交錯したこの事件は、幕府の支配構造と宗教政策を大きく変える転機となりました。
島原の乱が起きた時代背景
幕府による禁教政策が制度化された中で、信仰を捨てきれなかった人々の生活は過酷を極めていました。飢えと弾圧の中で、どのようにして反乱の火がともったのでしょうか。
キリスト教弾圧と重税の二重苦
江戸幕府の三代将軍・徳川家光の時代、キリスト教への弾圧はすでに全国的な制度として定着していました。踏み絵や寺請制度が広まり、信者たちは表向き仏教徒を装って密かに祈りを続ける“隠れキリシタン”となっていました。
信仰を守ることは、命をかける行為そのものでした。
さらに、島原藩主・松倉勝家と、隣接する唐津藩主・寺沢堅高による苛政が追い打ちをかけます。
両領主は幕府への忠誠を示すために巨額の城普請を行い、その費用を領民に重税として課しました。
凶作と飢饉が重なり、領民の多くは飢えと病に苦しみました。
「神にすがるしかない」――そんな絶望が、やがて信仰を旗印とする蜂起へとつながっていきます。
補足:松倉勝家の苛政
松倉勝家は悪名高い苛政で知られ、民を「生かさず殺さず」に支配するどころか、過酷な搾取によって追い詰めました。城普請での過労や重税は、島原の人々を飢餓の瀬戸際に追い込んだと伝えられています。
人は飢えには耐えられません。
大正時代の日本でも、食料を求めた全国的な暴動「米騒動」が起きています。
💡関連記事:大正時代の米騒動と現代の違い – 外食産業とコンビニの恩恵
「島原の乱」の顛末
信仰を抑えつけられ、生活を奪われた人々の中から、ついに反乱の火が上がります。
1637年(寛永14年)、島原と天草の農民たちはついに武器を手にしました。
神の子「天草四郎時貞」と宗教色の濃い反乱軍
反乱の旗頭となったのが、16歳ほどの少年・天草四郎時貞です。
彼は「神の子」「救世主」として信じられ、人々の信仰の象徴となりました。

画像出典:天草四郎時貞像 (天草パールガーデン) – フォートラベル
投稿写真より
一揆軍は十字架の旗を掲げ、「我ら神のために戦う」と唱えながら進軍します。
祈祷にはラテン語の「デウス(神)」や「アーメン」が響き、戦場は祈りと熱狂に包まれました。
それは単なる農民一揆ではなく、信仰を再び取り戻そうとする聖戦だったのです。
補足:原城が選ばれた理由 ― 反乱軍の籠城先
反乱軍が立てこもった原城は、かつてキリシタン大名・有馬晴信の居城でした。
信仰の記憶が残る聖地であり、人々にとっては“神の守護”を象徴する場所だったのです。
有馬晴信が改易された「有馬事件」は、幕府(家康)に最初の禁教令を出させる原因となった事件です。以下の記事で詳しく解説しています。
💡関連記事:禁教の導火線 ― 有馬事件(1612年) – 以下記事の該当箇所へ
「江戸幕府初期のキリスト教の禁教政策 ― 家康とプロテスタント」
原城の戦い ― 籠城と壊滅
民衆蜂起は、幕府にとって想定外の規模となりました。
幕府は全国から大軍を動員し、信仰による反乱を徹底的に鎮圧します。
(幕府軍) 約12万 vs 4万弱 (一揆軍)
幕府軍は譜代・外様合わせて12万の兵を集め、原城を包囲しました。
対する一揆軍は約3万7千人。
女性や子どもも多く、兵糧は乏しい中で祈りとともに耐え続けました。
人々はマリア像に祈り、十字を切って戦場へ赴いたと伝えられています。

3か月に及ぶ籠城戦の末、1638年2月、原城は総攻撃によって陥落します。
天草四郎は捕らえられて処刑され、城内の人々はほとんどが殺害されました。
幕府はその首を長崎にさらし、再びキリシタンが立ち上がらぬよう見せしめとしました。
参考年表:伴天連追放令から島原の乱まで
秀吉の伴天連追放令から、島原の乱の鎮圧までで、日本のキリスト教禁教に関係する出来事を、以下年表にまとめます。
| 年 | 出来事 | 概要・背景 |
|---|---|---|
| 1587年 | 伴天連追放令 | 豊臣秀吉が宣教師(伴天連)の追放を命じる。 布教そのものは黙認され続け、形式的禁令にとどまる。 |
| 1609年 | 平戸にオランダ商館設立 | 家康がオランダ(プロテスタント)との交易を許可。 スペイン・ポルトガルとの関係に慎重姿勢を示す。 |
| 1612年 | 有馬事件 | キリシタン大名・有馬晴信が貿易トラブルにより処刑。 幕府はキリスト教を「国家秩序の脅威」と認識。 |
| 同年 | 禁教令(幕府領) | 家康が直轄地(駿府・江戸)でキリスト教を禁止。 以後、全国的禁教の布石となる。 |
| 1614年 | 全国禁教令 | 宣教師追放と教会破壊を命じ、全国的弾圧が始まる。 多くの信者が潜伏し「隠れキリシタン」化。 |
| 1616年 | 家康死去 秀忠政権安定 | 外交方針がより閉鎖的に。 キリシタン取締が地方にも波及。 |
| 1619年 | 京都 キリシタン52人処刑 | 「元和の大殉教」と呼ばれる。 信仰弾圧が都市部に拡大。 |
| 1622年 | 長崎の大殉教 | 宣教師・信徒55人が処刑。見せしめとして公開火刑。 |
| 1623年 | 秀忠死去 家光が将軍に就任 | 禁教政策を制度化・常態化させる方向へ。 |
| 1624年 | スペイン人追放令 | 宣教師の潜入を防ぐため、スペインとの国交を断絶。 |
| 1627年頃 | 宗門改の実施開始 | 各地でキリシタン摘発のための 信仰調査(踏み絵・改帳)が行われる。 |
| 1633年 | 日本人の 海外渡航禁止令 | 帰国者を含めたキリシタン潜入を防止。 鎖国体制の第一歩。 |
| 1635年 | 日本人の海外渡航・ 帰国完全禁止令 | 海外布教や留学を全面的に禁ずる。 禁教と鎖国政策が一体化。 |
| 1636年 | 出島築造開始 | 外国人の居留をオランダ商館に限定。 キリスト教監視体制が確立。 |
| 1637年 | 島原の乱勃発 | 島原・天草の農民・信徒が蜂起。 天草四郎を中心に原城へ籠城。 |
| 1638年 | 原城陥落 島原の乱鎮圧 | 約3万7千人が殺害される。 以後、キリスト教は完全地下化。 寺請制度・宗門改が全国的に恒久化される。 |
それぞれの時代・出来事については、以下の記事に詳しくまとめてありますので、是非あわせてご覧ください。
島原の乱がもたらした影響
幕府はこの事件を「信仰による秩序の崩壊」と受け止め、禁教を国家の根幹とする方針をさらに強化しました。それと同時に、弾圧の仕方も「宗教の排除」から「宗教を利用した統治」へと変化していきます。
キリスト教禁教と仏教での統治
島原の乱を経て、それまで一部地域で臨時的に行われていた寺請制度や宗門改(しゅうもんあらため)は、全国的・恒久的に実施されるようになりました。すべての人がどこかの寺の檀家であることを証明しなければならず、寺院が発行する「寺請証文」がなければ婚姻も葬儀も許されません。
また、毎年作成される宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)によって、出生から死亡までの宗旨が記録されるようになりました。(明治以降の戸籍制度の基)
幕府は宗教(仏教)を「民を管理する行政の一部」として組み込みました。
寺や僧侶は幕府統治の末端機関として機能し、宗教は支配を補完する装置へと変わっていきます。
つまり、島原の乱は単なる反乱鎮圧ではなく、江戸社会の統治システムが完成する契機でもあったのです。
補足:一向一揆から寺請制度へ ― 仏教が「反乱の宗教」から「秩序の宗教」へ
戦国時代の日本では、仏教もまた信仰を旗印にした民衆運動の中心にありました。
一向一揆のように「神仏の正義」を掲げて領主に抵抗した例は、島原の乱と構造的に似ています。
しかし江戸幕府の成立後、寺請制度によって寺院は行政の一部として組み込まれ、檀家制度により経済的にも安定します。
その結果、仏教は反乱の大義名分を失い、国家秩序を支える“統治の宗教”へと姿を変えました。
仏教徒を装う「隠れキリシタン」
島原や長崎の一部では、外見上は仏教徒として寺に属しながら、家庭の奥で密かに祈りを続ける人々がいました。十字架を彫った貝殻を拝み、仏像の中にマリア像を隠すなど、信仰の形を変えて生き延びた人々です。
彼らの存在は後に「隠れキリシタン」と呼ばれ、日本の信仰史の中で特異な足跡を残しました。
長い時間をかけて教義が曖昧となった特殊な宗教観は、現代では「カクレキリシタン(潜伏キリシタンの後裔)」と呼ばれ、文化人類学や宗教史の分野で研究対象になっています。
家光実権掌握から鎖国体制の完成までの流れを、時系列で整理しています。
「政教融合」による安定と「政教分離」の是非
日本を含め、現代の民主国家は政教分離を原則としています。
しかし江戸時代の幕府は、寺請制度によって全国民を宗教組織の傘下に入れ、寺院に戸籍や治安維持、倫理教育の一部を担わせました。つまり宗教を国家の末端行政として利用し、「信仰の自由」を奪う代わりに「社会の安定」を得たのです。
近代国家の政教分離は、“宗教の代わりとなる倫理・教育・行政制度を整えた”という前提に立っています。けれども、本当にそれは機能しているのでしょうか。
政教分離は本当に正しいことなのか。
江戸時代の、あの二百年に及ぶ平和の歴史が、私たちに静かに問いかけています。
また本記事は、以下の「日本のキリスト教禁教史」特集の一部です。
日本のキリスト教禁教の背景や実態を詳しく知りたい方は、是非こちらもご覧ください。