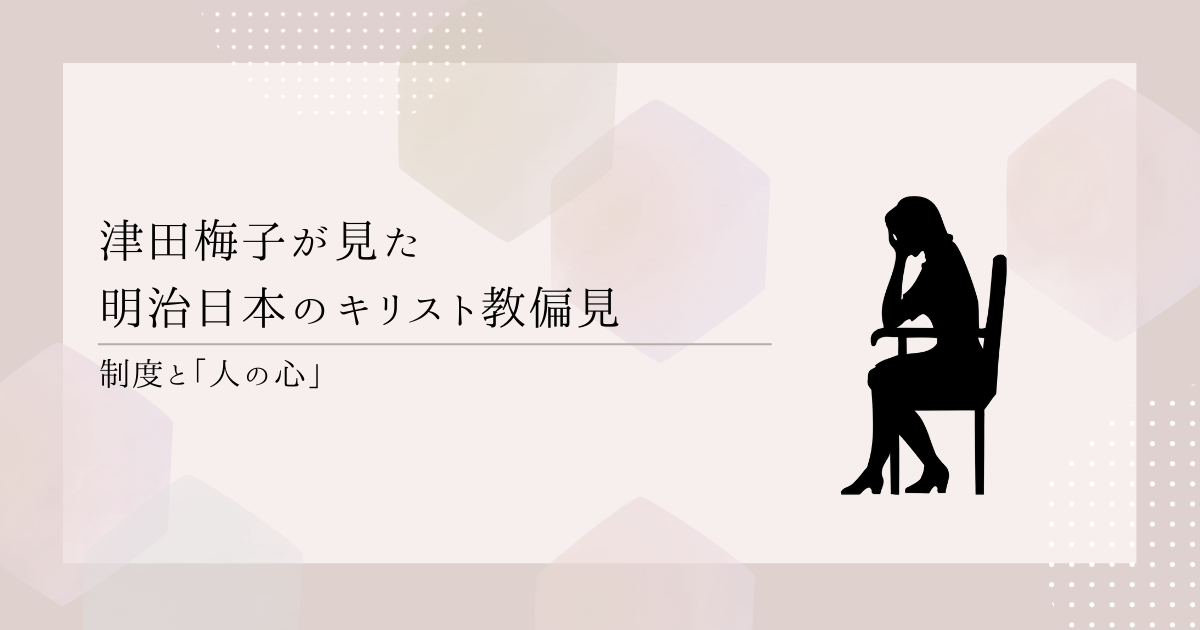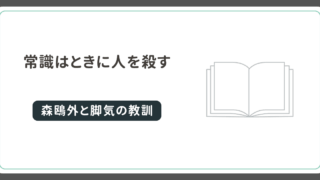明治時代、キリスト教は依然として警戒の対象でした。
留学を終えて帰国した津田梅子も、その偏見の中で苦しむことになります。
なぜ日本人は、禁止が解かれた宗教をなお恐れ続けたのでしょうか。
歴史の背景から、差別と警戒の境界を考えます。
アメリカ帰りの少女・津田梅子
現在の5000円札紙幣に採用された津田梅子は、明治日本の女子教育を切り拓いた人物として知られています。
女性が高等教育を受けることが珍しかった時代に、自ら女子英学塾(現・津田塾大学)を設立するなど、女性の自立と学問の道を広げた先駆者でした。
津田梅子が大きな転機を迎えたのは、まだ幼い6歳の頃です。
岩倉使節団とともに渡米した「女子留学生」
1871年(明治4年)、日本政府は不平等条約の改正交渉を最重要目的として、岩倉使節団を欧米へ派遣しました。併せて、欧米の制度を視察し、近代国家づくりの参考にする使命も担っていました。

左から木戸孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通
出典:Wikimedia Commons / Public Domain
この派遣に伴い、将来の国づくりを担う国際人材育成として、少年を中心に留学生の長期派遣が企画されます。その中で、女子教育の必要性が議論され、急きょ少女5名が選抜されました。
津田梅子(当時「うめ」)は、その女子留学生の最年少でした。
津田梅子が選ばれた経緯
女子留学生の募集は全国公募でしたが、
- 長期(10年以上)の留学に耐えられる若さ
- 家庭の協力と経済力
- 洋学への理解と人脈
など、条件を満たす家庭は多くありませんでした。
梅子の父・津田仙は、通訳官として外国と接触し、新政府要人とも交流がありました。
政府の意図を理解した上で、自ら積極的に娘を推薦したとされています。
さらに梅子は当時わずか6歳で、
「柔軟な適応力を持ち、将来日本女性の模範となる」
と期待されての選抜でした。
アメリカで育まれた価値観と学び
梅子はアメリカ・ワシントンD.C.のキリスト教徒家庭に預けられ、教会を中心とした生活を送りました。

ワシントンD.C.で撮影
出典:Wikimedia Commons / Public Domain
- 英語の習得
- 教会活動と信仰教育
- 女性にも開かれた学びの環境
こうした経験は、彼女の人格と価値観を形づくっていきます。
当時のアメリカの女子教育は、
「自立した女性」を育てる教育として梅子に強い影響を与えました。
帰国と、新しい時代の始まり
約10年の留学生活を終え、梅子が帰国したのは1882年(明治15年)。
日本は急速に近代化が進み、伝統と西洋がせめぎ合う時代の真っ只中にありました。
この時期の日本は、
- キリスト教禁制の解除から間もない
1873年(明治6年):キリスト教禁止の高札撤去
1882年(明治15年):津田梅子の帰国
1889年(明治22年):大日本帝国憲法発布 ― 条件付きの”信教の自由” - 伝統と西洋がせめぎ合う社会情勢
- 近代化改革が進む一方で混乱も続く
そんな環境の中で、梅子は再び日本社会と向き合うことになります。
帰国後に待っていた「居場所のない現実」
アメリカで学び、帰国後すぐに教師として教壇に立った津田梅子。
しかし、その場所は、彼女が夢見た “帰る場所” ではありませんでした。

前列の左端が梅子 : 1886年(明治19年)
出典:Wikimedia Commons / Public Domain
遠く離れた国で育まれた価値観と信仰は、母国で “異質” と映り、
彼女を深い孤独へと追い込みます。
言葉を失った少女
約10年を海外で過ごした梅子は、日本語をほとんど忘れていました。
同僚との会話にも苦労し、授業にも支障が出るほどでした。
- 「日本人なのに日本語が話せない」
- 「西洋かぶれの特殊な少女」
そういった見方が付きまとい、異質な存在として距離を置かれます。
日記には、
「私はどこの国の人間なのだろう」
と、自分の拠り所を失った心境がにじみます。
「奇妙な宗教」を信じる少女
帰国後の大きな壁のひとつがキリスト教への偏見でした。
日本では長くキリスト教が「邪宗門」とされてきた記憶が残り、
禁教の撤廃からわずか数年。社会の不信は根強いままです。
- 信仰を語ることを避けるよう求められる
- 生徒への影響を懸念される
- 「扱いづらい教師」と見なされる
信仰が支えだったはずの梅子にとって、
信仰ゆえに疎まれる現実は、痛烈な矛盾でした。
日記が語る孤独
「私はどこにも属していないように思う」
「この国で、私は何者として生きるのか」
信仰を隠す毎日は、彼女の心を追い詰めていきます。
苦悩と向き合い、前へ進む決意
信仰を抑えながら教壇に立つ毎日は、梅子にとって自分らしさを失う日々でした。
しかし彼女は、それを「仕方のないこと」と受け入れませんでした。
「私が変わらなければ、状況は変わらない」
と、再びアメリカへ学びに戻る決断をします。
- 教育学を深めるため
- 信仰と教育を両立できる自分になるため
再渡米は 逃避ではなく、戦う準備でした。
信仰と教育の“切り分け”という選択
再渡米後の彼女は、信仰を失わぬまま、しかしそれを表に出さず、
- 生徒一人ひとりの人格を尊重する教育
- 学問によって女性の人生を切り拓く姿勢
を前面に据えるようになります。
これは、結果として信仰と教育を切り分ける形につながっていきます。
心の中には信仰を
社会に示すのは教育を
この新しいバランス感覚が、後の学校設立へとつながります。
夢を形に ― 女子英学塾の誕生へ
帰国後、梅子は女性の高等教育を実現するため奔走し、
1898年(明治31年)、ついに 女子英学塾 を創立します。
それは彼女の信仰と理想を、誰も排除しない教育の形へと昇華させた結果でした。
明治日本の「キリスト教偏見」の背景
当時の日本人がキリスト教に抱いた不安と警戒は、単なる偏見ではありませんでした。
長い歴史と政治が生み出した、ごく“自然な”反応でもあったのです。
禁教が常識になった日本
江戸時代の日本では、キリスト教は禁止されていました。
その期間は、実に 250年以上 におよびます。
- 1612年:キリシタン禁制(幕府による弾圧開始)
- 1614年:伴天連追放令、宣教師追放と弾圧強化
- 1639年:ポルトガル船来航禁止 ― 鎖国体制へ
- 1868年:明治維新後も禁教政策が継続
- 1873年:キリスト教禁制の高札が撤去
これほど長い間、「キリスト教=危険」という認識が国全体に浸透していたのです。
日本がキリスト教を禁止した理由
そして、その理由は単純ではありません。
- 外国勢力による侵略の恐れ
- 内部の秩序が乱れるという治安不安
- 伝統的価値観との摩擦
国を守るための“国防政策”としての禁教でした。
こうした歴史の中で、日本人の多くはキリスト教に触れる機会すらなく、
「怖いもの」「不穏なもの」と信じて疑わなかったのです。
日本の禁教史に関心のある方は、是非以下の特集記事もご覧ください。
多文化共生が議論される現代において、かつての日本が宗教を禁止した背景や実態を知ることは、公平な視点を得ることに役立ちます。
禁教解除は「本音」ではなかった
1873年(明治6年)、キリスト教禁止を示す高札は撤去されます。
表向き、日本は信仰に対して寛容になったように見えました。
しかし――
政府がキリスト教を歓迎していたわけではありません。
キリスト教解禁の背景には、
- 欧米諸国が求める「信教の自由」
- 不平等条約改正のための外交戦略
- 欧米との協調が欠かせない国際情勢
という、外からの圧力がありました。
一方で、国内統治においては
- 天皇を中心とする新しい国家理念を浸透させる必要
- 国家神道による国民統合政策
が強く推し進められていました。
つまり、政府の本音は――
「海外に向けては容認するが、国内では管理する」
という二重構造だったのです。
育まれた「合理的な偏見」
こうした状況の中、日本社会では
- 禁教の記憶:治安を乱す宗教
- 時代の不安:外国の影響を受ける危険
- 国家理念:天皇を中心にまとまる国
が重なり合いました。
その結果、キリスト教を警戒するのは「当然で自然なこと」と、多くの人が感じていたのです。
ここにあるのは
- 無知ではなく
- 教育の欠如でもなく
- 悪意ですらなく
歴史と政治によって育てられた“合理的な偏見” でした。
津田梅子への偏見や差別は悲劇ではありますが、
これは当時の日本人の「常識」から生み出された差別ともいえるのです。
差別と警戒の境界線
現代では、「差別は絶対に悪である」と語られることが多くなりました。
しかし、その価値観すらも疑ってみる必要があるのではないでしょうか。
明治日本でキリスト教が警戒されたのは、決して理不尽な差別感情からではありません。
外国勢力への不安、国を守るための危機感、社会秩序を維持したいという願い――
そうした“合理的な警戒心”が根底にあったのです。
ただ、その警戒がいつの間にか“目の前の人を傷つける差別”に変わってしまう。
ここにこそ、問題の本質があります。
疑う事の重要性 ― 常識が生み出す差別
差別は悪だからやめよう――
それは一見正しい言葉です。
しかしその言葉が、背景や理由を考えることを放棄し、「警戒」と「差別」を短絡的に同一視してしまうなら、それもまた新しい差別を生む土壌になるかもしれません。
大切なのは、単純な基準に頼らず、「なぜその判断が必要とされたのか」を問うことです。
社会を守るための警戒と、無自覚な偏見がもたらす排除は紙一重です。
歴史は、その境界が曖昧になったときに悲劇が生まれることを示しています。
無自覚な常識こそが差別を生む――
明治日本の歴史は、それを静かに教えてくれます。
関連記事:常識とは何なのか
私たちの判断基準になることもある「常識」は、普遍の真理ではなく、時代と共に変化する価値観でもあります。歴史は、「科学的に証明されている常識」でさえも悲劇的な結末に繋がる可能性があることを示しています。
「常識を疑う事の大切さ」に関連した以下の記事も、是非ご覧ください。