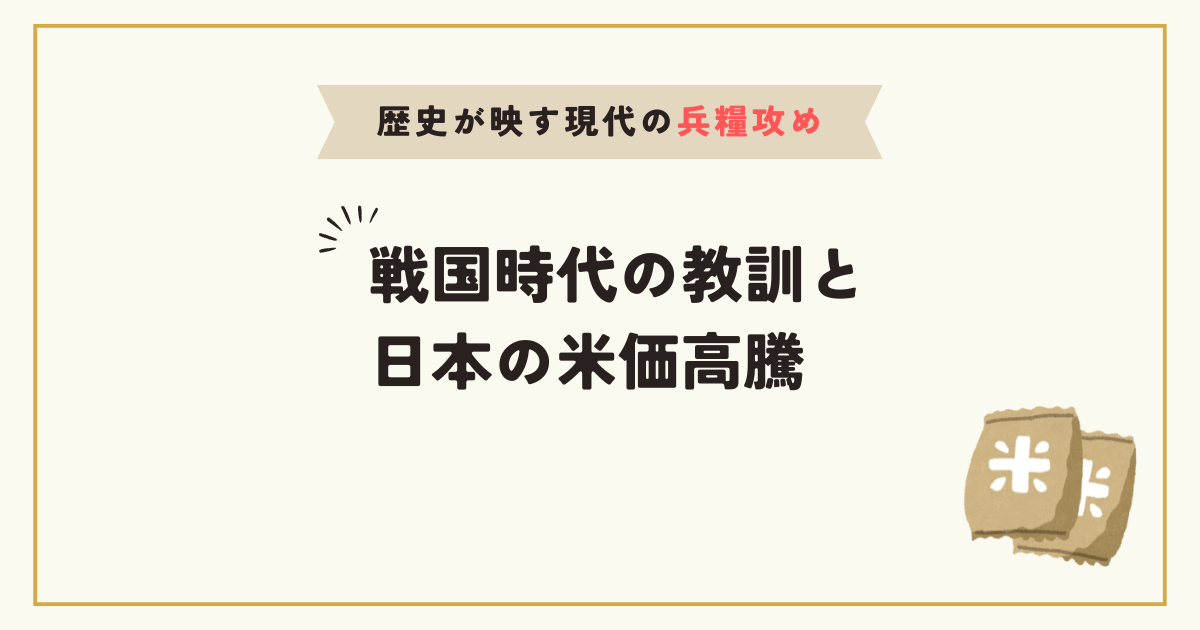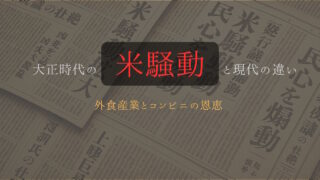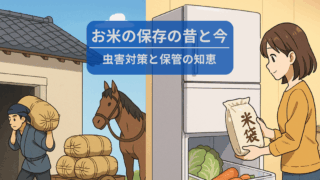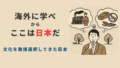2023年以降、日本の米価格は異常な高騰を続けています。わずか2年で2倍となり、2025年の新米もさらに高値で取引されるようになりました。備蓄米の放出や輸入対応が進められていますが、価格は下がらず、国民生活を直撃しています。
この状況を「現代の兵糧攻め」と捉え、戦国時代の歴史から学びつつ、政府の機能、そして私たち国民の役割を考えてみましょう。
戦国時代の兵糧攻めとは
戦国時代、多くの武将が城攻めに用いた戦術が「兵糧攻め」です。敵城を包囲し、補給路を断ち、内部の食料が尽きるのを待つ――力で攻め落とすのではなく、時間をかけて敵を弱らせる方法でした。
代表的な例としては、信長の石山本願寺攻めや、秀吉の備中高松城攻めが知られています。
重要なのは、兵糧攻めが「ただ包囲して飢えを待つだけの戦略」ではなかったことです。
攻撃側は、敵をより短期間で窮地に追い込むため、周辺の村々の米を押さえたり、ときに市場での買い上げや徴発を行ったりして、外部からの補給を徹底的に封じました。
こうして兵糧不足を人工的に加速させることで、戦わずして勝利を得ようとしたのです。
戦国時代の「高直し」(米価高騰)
兵糧攻めの副作用として、地域の米価が高騰する現象がありました。当時は「高直し」と呼ばれ、買い占めや需給の逼迫によって庶民の生活を直撃しました。

米は貨幣経済とも直結していたため、米価の乱高下は戦場だけでなく市井にも大きな不安をもたらしたのです。
現代の米価高騰と政府対応
戦国の話は遠い昔のこと。しかし、2023年以降の日本に目を向けると、思いがけない類似点が見えてきます。
現代の米価高騰
- 2023~2025年で2倍以上
スーパーで売られる5kg袋が4,000円を超えるようになりました。 - 新米も高騰
2024年秋には前年の1.5倍、2025年もさらに値上がりが続いています。
背景には、猛暑による不作、災害、害虫被害に加え、観光客の急増や買いだめによる需給の混乱が指摘されています。
売り切れない備蓄米
2025年8月17日には、YouTubeチャンネル「ANNnewsCH」では「今年の新米5kg7800円も 異常な高値に業者も困惑 「備蓄米売り切れない」悲鳴も」といったタイトルのニュースが報道されましたが、現在は削除されているようです。
削除された動画の内容は、以下となっていました。
2023年までは、5kg2500円程度だった米が、2024年には5kg5000円台(2倍)まで高騰し、今年2025年は5kgが7800円になるところもあるという状況のようです。その一方で放出された備蓄米は、政府からの提供時期が遅く、販売期間が定められていることも相まって、大量に売れ残りそうな見通しであることが伝えられています。
米価高騰の抑止(備蓄米と農水省の監視)
日本は米価格の高騰を抑止するための体制を整えています。大枠としては以下のようなものが挙げられます。
- 米の流通は農水省の監視が行われている
- 国内需要が高まっていれば、国外輸出を抑える
- 米の急騰を防ぐために「備蓄米」があり、抑止弁として緊急時に放出する
他国からの買い占めのような動きは、農水省の監視下で行うのは難しく、また国内需要が高まっている場合には制度上は輸出を減らして価格高騰を抑えることが可能です。さらに、米価急騰を防ぐ「備蓄米」があり、緊急時には市場に放出されます。
ただし2025年の現実を見ると、備蓄米を放出しても効果が限られ、在庫も大幅に減少してしまいました。それと同時に、政府は「米輸出促進」方針を変えていません。
制度としては存在していても、実際に十分機能しているのかどうかは検証が必要です。
政府対応と兵糧攻めの共通点
この政府の対応は、国内の価格高騰を抑える動きとは真逆に見えます。まるで戦国時代の兵糧攻めのように、国民がじわじわと締め付けられている状況です。
戦国時代の兵糧攻めでは、敵が周囲の米を買い上げるなど、外部からの圧力がありました。現代では農水省の監視があり、怪しい卸売業者の動きは表面化しやすい「はず」です。
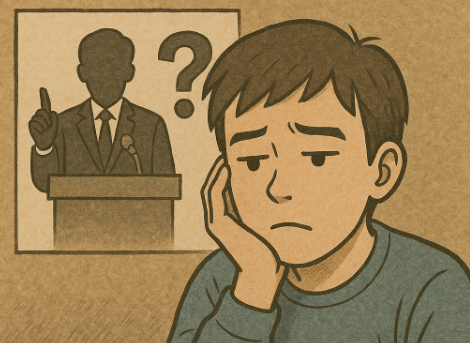
しかし、備蓄米を放出しても効果が出ず、輸出促進が同時に進められる今の状況を見ると、果たして政府の仕組みは本当に国民生活を守れているのか――この問いを、私たち市民が投げかけ続ける必要があります。
政府は正しく機能しているか
ここで問うべきは、「政府の仕組みは本当に国民を守れているのか」という点です。
政府の抑止が効かないという現実
備蓄米は本来、価格高騰を抑えるための最後の砦であるはずです。しかし、放出しても価格は下がらず、在庫も減少するばかり。
さらに矛盾するように、政府は依然として「米輸出拡大」の旗を降ろしていません。国内消費者が苦しむ一方で、国外に米を供給する政策は、多くの人に疑念を抱かせています。
歴史から見る「内部からの脅威」
戦国時代、城が落ちる最大の要因は外部からの攻撃ではなく、内部の裏切りでした。城内の者が門を開き、米蔵に火をつければ、いくら堅牢な城も崩壊しました。
現代に置き換えれば、政策決定の中に「国益よりも外部利害を優先する意思」が入り込めば、それは「内部の裏切り」に等しいものです。
もし現代の日本が“見えない兵糧攻め”に直面しているとすれば、米の流通や備蓄米、輸出政策といった仕組みが本当に機能しているのかを、市民が常に問い直す必要があります。農水省や卸売業者、さらには政府や政治家の判断も、疑うというよりは説明責任を求め、透明性を確保する姿勢が不可欠です。
戦国時代でも現代でも、「大丈夫なはず」と楽観的に構えていると、内部の脆弱性が外敵に突かれ、危機が現実化する可能性は高まります。だからこそ、私たちは制度や政策を監視し続ける目を持たなければならないのです。
まとめ ― 陰謀論ではなく「現実」を
強調したいのは「陰謀がある」と決めつけることではありません。問題は、制度や政策が国民生活を守るには脆弱であるという現実です。
食料はエネルギーや軍事と同じく国家の基盤です。日本はカロリーベース自給率38%前後と低く、米が唯一の自給的基幹作物であるにもかかわらず、その安定供給が揺らいでいます。
だからこそ、国民は「備蓄米は本当に機能しているのか」「輸出政策は誰のためか」と問い続ける必要があります。政治任せにせず、監視し、説明責任を求めることが、未来の食卓を守る唯一の方法です。
戦国の教訓はこう伝えています。外からの攻撃よりも、内部の油断こそが最大の脅威であると。
「現代の兵糧攻め」に立ち向かう力は、私たち国民の監視と関心にかかっています。
本サイトには米問題を取り上げた記事が他にもありますので、興味のある方は是非ご覧ください。