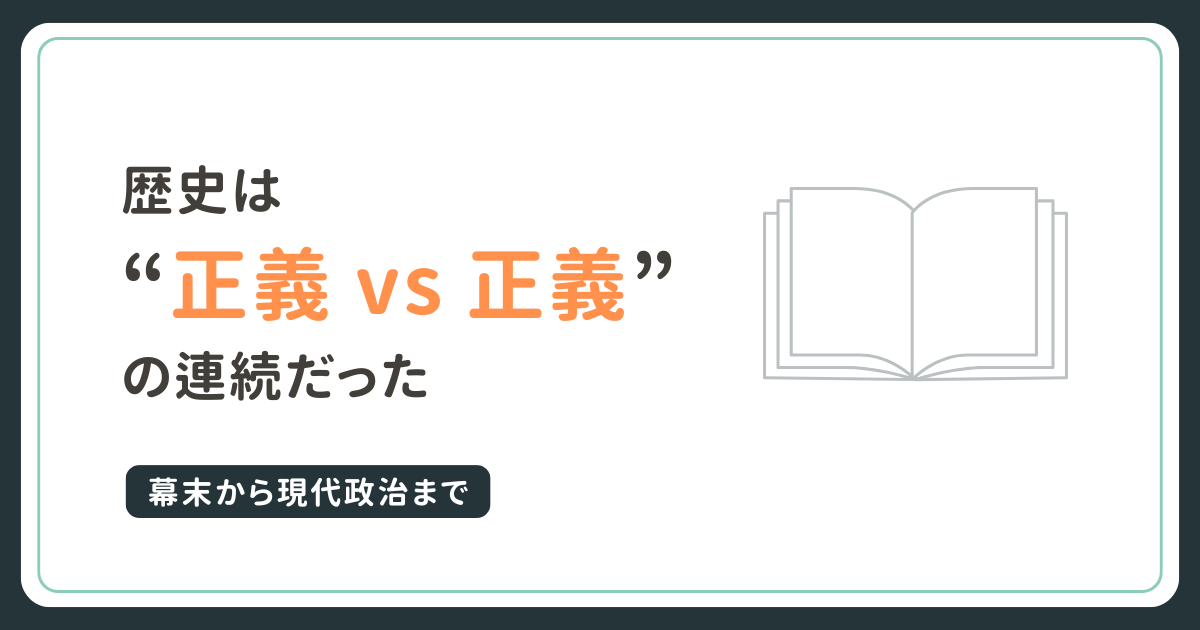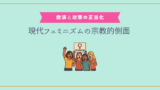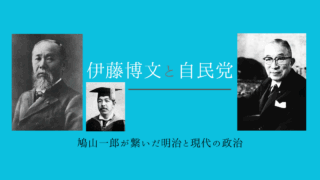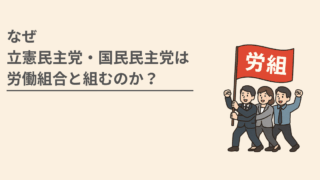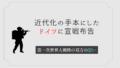「正義の反対は悪」――子どものころ、そんな風に教わった人は多いでしょう。けれども歴史を紐解くと、どうもそう単純ではないことがわかります。
江戸時代の終わり、日本を開国へ導こうとした人々も、外国勢力を追い払おうとした人々も、それぞれが「国を守る」という正義を掲げていました。アメリカの南北戦争でも、奴隷制を廃止しようとした北部と、それを生活基盤としていた南部の双方が「自分たちこそ正しい」と信じていました。
このように、歴史はしばしば「正義 vs 正義」の衝突で動いてきました。本記事では、なぜ正義同士がぶつかるのか、そしてその構造が現代にも続いているのかを探っていきます。
なぜ正義同士が衝突するのか
歴史を振り返れば、「善と悪」の単純な物語よりも、立場や背景の違いによって生まれる「正義と正義の衝突」の方が多く見られます。
ここでは、なぜ同じ「正義」という言葉が、全く異なる行動や結果を生み出すのか、その構造を探っていきます。
正義の定義と主観性
「正義」とは何か――哲学者たちは何千年も議論を重ねてきました。
しかし現実には、正義は絶対的なものではなく、多くの場合は社会や文化、時代背景によって形を変えます。
ある国の正義は、別の国にとっての不正義になり得るのです。
立場・利益・文化背景による価値観の違い
人は自分や自分の属する集団の利益を守ろうとします。
その利益を守るための行動が「正義」と呼ばれることもあれば、「利己的」と非難されることもあります。
価値観の違いは、同じ事象を正反対の評価に分けます。
「古い正義」と「新しい正義」の入れ替わり構造
歴史上の政変や革命は、古い価値観に基づく正義と、新しい価値観に基づく正義の衝突として現れます。
- 古い正義:
長年社会を安定させてきた秩序や制度。既得権益や伝統を守る立場。
→ 例:王権、封建制度、宗教的支配、軍政など。 - 新しい正義:
現状を変えて、より良い社会を作ろうとする理念や改革。
→ 例:民主化、人権拡大、民族独立、平等社会。
当時の人々の目には、両方とも真剣な「正義」だったのです。
権力闘争における“理念”の役割
理念や正義は、時に権力闘争の旗印として利用されます。
純粋な信念の場合もあれば、権力維持や拡大のための方便となる場合もあります。
歴史が示す「正義 vs 正義」の事例
理論としての「正義の衝突」が分かったところで、実際に歴史上どのような形で現れたのかを見ていきましょう。
異なる時代、異なる国で起きた具体的な事例を通して、この現象の普遍性を確かめます。
幕末の開国派 vs 尊王攘夷派
19世紀半ば、ペリー艦隊の来航で日本は大きな選択を迫られました。
- 開国派は、外国と交易し近代化を進めることで国力を高め、日本を守ろうとしました。
- 尊王攘夷派は、外国勢力の侵入を排し、伝統と独立を守ることが国を守る道だと考えました。
攘夷(じょうい)とは、一般的に「外国人を排斥し、国を外国の影響から守ろうとする考え方や行動」を指します。
両者とも「日本を守る」という同じ旗を掲げながら、具体的な行動は正反対でした。
結果的に明治新政府は開国路線を選びましたが、尊王攘夷の理念は別の形で維持され、後の国家政策にも影響を与えました。
南北戦争(アメリカ)
1861年から1865年にかけてのアメリカ南北戦争も、「正義 vs 正義」の典型例です。
- 北部は奴隷制廃止と国家の統一を正義とし、南部の分離独立を認めませんでした。
- 南部は自治権の維持と生活基盤である奴隷制を守ることを正義と考えました。
北部が勝利し、奴隷制は廃止されましたが、南部の人々にとっては「侵略者による支配」という感情が長く残り、現在でも地域文化や政治的立場に影響を与えています。
補足 : 現代では理解し難い「南部の正義」
南部側は、合衆国は各州の合意によって成り立っており、州は自らの判断で連邦を脱退する権利(States’ Rights)を持つと主張。また、綿花プランテーション経済は奴隷労働に依存しており、その廃止は経済と生活の崩壊を意味すると考えていました。さらに、農業中心の社会や伝統的な階級秩序を北部の価値観から守ることも「南部の誇り」とされました。
南部は、奴隷を含んだ階級社会を「理想的な社会構造」と見なしていたのです。
当時は聖書や歴史を根拠に奴隷制度を正当化する論も存在しましたが、現代的には明確に不当であり、彼らの掲げた自由と権利は差別を前提にしたものでした。
それでも当時の南部人にとっては、北部の干渉は圧政と映り、自らの正義のために戦う動機となったのです。
フランス革命と王党派
1789年のフランス革命では、革命派が「自由・平等・博愛」を掲げ、旧制度を打倒しました。
一方で、王党派は「秩序と安定」「長年培われた社会構造」を守ることを正義として戦いました。
革命派は旧体制を打破して近代民主主義の礎を築いた一方で、深刻な負の側面も伴いました。
新たな暴力を生み出す「正義」の危うさ
1793〜1794年にはロベスピエールらによる恐怖政治が展開され、わずかな反革命の疑いでも革命裁判所にかけられ、約16,000人がギロチンで処刑、さらに数万人が獄死や暴力で命を落としました。
ヴァンデ地方などでは反革命派と革命軍の内戦が激化し、多数の民間人が犠牲に。国外では周辺諸国との戦争が拡大し、国力が消耗する中でナポレオンが台頭し独裁へと移行しました。
革命は新しい正義をもたらすと同時に、大量処刑や戦争、社会混乱という新たな暴力を生み出し、「正義」が極端に振れたときの危うさを示す歴史となったのです。
人は「正義の側にいると確信すると、攻撃性が増す」ことが知られています。
以下の記事では、現代のフェミニズムの「救済と攻撃の正当化」といった点を、宗教的側面としてまとめています。宗教が「人々を救済し、時に攻撃の正当化に使われた」歴史を知ると、現代フェミニズムとの共通点が見えてきます。
冷戦の米ソ対立
第二次世界大戦後、アメリカとソ連はそれぞれ自由主義と社会主義を掲げて世界をリードしようとしました。両者とも自国の体制こそ人類を幸福に導くと信じ、相手を「悪の帝国」と呼びました。
プロパガンダは市民の意識を固定化し、互いに歩み寄る余地を狭めました。
冷戦は1991年に終結しましたが、その価値観の溝は21世紀にも影を落としています。
現代における「正義の衝突」の事例
歴史の中だけではなく、現代の社会や国際関係にも「正義 vs 正義」は息づいています。政治対立から国際紛争まで、その構造はほとんど変わっていません。
ここでは現代の事例を見ていきます。
リベラル vs 保守 – 左派と右派の対立
現代の多くの民主国家では、政治的スペクトルの両端にリベラル(左派)と保守(右派)が存在します。
- リベラルは多様性の尊重や社会的平等を重視します。
- 保守は伝統や秩序、国家アイデンティティを重視します。
SNSの普及によって、こうした価値観の違いが可視化され、拡散スピードも加速しました。結果として、互いの弱点を突く形で議論が過熱し、相手の「正義」を認めない傾向が強まっています。
国際紛争における正義
現代の国際紛争も、多くは双方が自国の正義を掲げています。
領土や民族、宗教の問題において、一方の「安全保障」は他方から見れば「侵略」になる場合があります。
国連や国際法は中立的な解決を目指しますが、実際には大国の利害や各国の立場の違いによって、真に公平な仲裁は難しいのが現状です。
「正義 vs 正義」を理解する意味
歴史と現代の事例を踏まえると、「正義の反対も正義」であることを理解する意義が見えてきます。
「正義 vs 正義」の歴史を学ぶことで、私たちは以下のような視点を得られます。
- 相手の立場を理解する想像力
自分と異なる背景や価値観を持つ人が、なぜその選択をするのかを理解できます。 - 善悪二元論から距離を置く
単純な善悪の物語は分かりやすいですが、現実を正しく捉えるには不十分です。
二元論から距離を置くことで、複雑な問題をより冷静に判断できます。 - 分断を減らす手がかり
対立を単なる「敵」と見るのではなく、「異なる正義」と見ることで、対話の可能性が広がります。
「正義 vs 正義」の構造について理解が深まれば、議論などで「落としどころ」を探るのに役立ちます。「自分だけが正義だ」という相手を見下したような主張では、建設的な議論にはならないでしょう。相手にも正義があると分かれば、折衷点を見出せるのではないでしょうか。
以下の記事は、「考え方」を主軸とした「正義vs正義」に関する記事となっています。経験に基づく個人的な見解が多い古い記事ではありますが、興味のある方は是非ご覧ください。
💡関連記事:正義の反対は悪ではなく、それもまた正義 – 相手を受け入れる考え方
結論 ― 歴史の教訓から未来へ
歴史は勝者の正義で語られます。しかし、負けた側にも守ろうとした価値や理由が必ず存在します。
幕末の開国派と尊王攘夷派、南北戦争の北部と南部、現代のリベラルと保守――すべてが、自らの信じる「正義」を掲げていました。
「正義の反対も正義」という構造を理解することは、単なる歴史の知識ではなく、現代社会での対立や分断を乗り越えるための重要な視点となります。
そしてそれは、未来を少しでも平和にするための第一歩かもしれません。
付録:年表で見る「正義 vs 正義」
- 1789年 フランス革命:革命派 vs 王党派
- 1861年 アメリカ南北戦争:北部 vs 南部
- 1853年 ペリー来航:開国派 vs 尊王攘夷派
- 1947年〜1991年 冷戦:自由主義陣営 vs 社会主義陣営
関連記事:政治の世界も「正義 vs 正義」
経済界を背景に社会の発展を進める「自民党」と、労働組合を背景に労働者を守ろうとする「立憲民主党・国民民主党」。信念は違えど、どちらも正義と言えるでしょう。
政治と歴史に関心のある方は、是非以下の記事などもご覧ください。